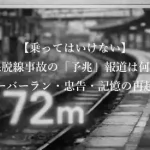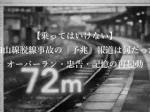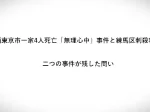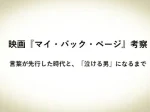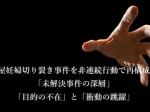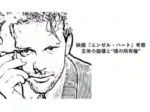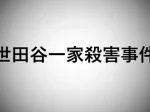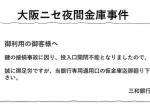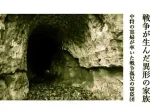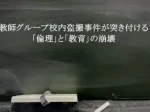1954年12月、東京・新富町の印刷所に現れた謎の男Xが、「宗教団体の寄付領収書」と称して奇妙な「紙幣のようなもの」1000枚の印刷を依頼した。そこには「白衣の騎士」「昇る太陽」「イスラエルのマーク」「判読不能な文字と100の数字」が描かれていた。警視庁は実在しない外国紙幣や詐欺目的の小道具の可能性を疑い、ICPOに情報提供。専門家鑑定でも文字は判読不能で、宗教的・結社的シンボルとの関連も浮上したが、動機も意図も不明のまま事件は迷宮入りした。
事件史を紐解くと、常識や経験則では説明できない未解決事件に出くわすことがある。犯人の姿はおろか、その動機すら闇の中に沈んだままの事件だ。
今回取り上げるのは、戦後復興期の東京で発生した、奇怪な印刷物をめぐる「謎のニセ札事件」である。
白衣の騎士、昇る太陽、イスラエルのマーク――紙片に刻まれた不可解な図像は、宗教か、結社か、それとも全く別の目的か。
本稿では、その正体と真意に迫り、歴史の陰に消えた不思議な事件を検証する。
謎のニセ札事件 概要
1954(昭和29)年12月初旬、東京都中央区新富町1丁目所在の個人経営印刷所に、見知らぬ男(以下、X)が現れた。
同店は、現在のJR東京駅八重洲口から南西方向へ直線距離約500メートルに位置する印刷所である。(地図は、現在の「東京都中央区新富町1丁目」内)
Xは某興信所の調査部長を名乗った(名刺を残した可能性がある)が、年齢や身体的特徴に関する情報は一切残されていない。名乗った氏名や興信所の実在の有無についても確認できなかった。
Xは店主に対し次のように説明し、10ドル札程度(縦6.5センチ、横15.5センチ)の「紙幣様印刷物」の見本を提示、1枚50円で1,000枚(計5万円)の印刷を発注したと報じられている(参考:朝日新聞1955年2月6日付「外人がナゾの紙幣 印刷屋に依頼す 警視庁初提訴 国際刑事警察委へ」)。
――知り合いの外人(外国人)から頼まれた。宗教団体の寄付の領収書に使うもので、別に怪しいものではない――
――警視庁の公安部長とも親しいので、すでに了解をもらっている――
提示された見本はきわめて奇妙で特異だった。表面左右には「100」のアラビア数字、その脇に判読不能の「文字様記号」。中央には「旗を掲げた白衣の騎士」、その下に「鮮やかな色彩で昇る太陽」と「イスラエルのマーク」が配されていた。
この「文字様記号」について、東京大学・東京教育大学の学者および宗教学者による鑑定が行われたが判読不能とされ、「一部の者にのみ通用する特殊符号の可能性」と結論づけられた。イスラエル公使館は、この種の紙幣は存在しないと回答している。
朝日新聞(前掲紙)は、この印刷物を「ユダヤ系団体が世界政策を目的として秘密資金獲得に用いる一種の証券」または「秘密宗教結社」に関連する可能性があるとする説を紹介し、「不思議な事件」と評している。
本件は、印刷完了後に商品を受け取ったXの動向が不明となったため、店主が不安を覚えて警視庁へ通報したものと推察される。
警視庁三課は、外国由来の印刷物を国内で製造した点、及び印刷物の行方が不明である点(Xの氏名・肩書・勤務先の興信所はいずれも虚偽の可能性が高い)を考慮し、警視庁として初めて国際刑事警察機構(ICPO)へ情報提供を行った。これは、印刷物が各国通貨の偽造品である可能性、または詐欺事件の小道具として使用される懸念によるものであったと考えられる。
当時の報道によれば、「たとえニセ札と断定できなくとも、紙幣に紛らわしいものとして捜査対象となる」との判断であった。捜査当局は、日本政府発行紙幣とは外観が明らかに異なるものの(前述の図像はいずれも日本紙幣には存在しない)、実在する外国紙幣に類似する、あるいは日本人に外国紙幣と誤認させる可能性を理由に、捜査対象としたものとみられる。
謎の「紙幣のようなもの」は、そもそもニセ札だったのか?
ここからは、この奇怪な「紙幣様印刷物」について考察する。
前述のとおり、Xが依頼した印刷物の表面には「旗を掲げた(原文ママ)馬上の白衣の騎士」、「鮮やかな色彩で昇る太陽」、「イスラエルのマーク」、および「100」のアラビア数字と判読不能の記号様の文字が描かれていた。裏面に関する情報は一切なく、何も印刷されていなかった可能性もあれば、図像や肖像が配されていた可能性も否定できない。ただし、もし肖像が存在したならば報道で触れられたと考えられるため、その可能性は低い。
さらに、多くの国の紙幣に備わる「すかし」や固有記号番号の存在も確認されていない。領収書や会員証といった印刷物でさえ記号番号が付される場合が多いが、本件にはそれがない。旧日本政府発行の「軍票」にも番号のないものが存在するが、そもそも軍票は貨幣ではなく証券に分類される。
すなわち、この印刷物は1,000枚すべてが同一仕様であり、同一人物が複数枚を手にした瞬間に「紙幣ではない」と看破される性質を有していたと推察される。
以上を踏まえれば、Xが発注した印刷物は、当初から紙幣としての機能や外観を意図したものではなかった可能性が高い。
では、この「紙幣様印刷物」の真の性質は何であったのか。以下、さらに検討を進める。
描かれていたシンボルマークを考察する
繰り返しとなるが、本件印刷物に描かれていた主なシンボルは以下の四点である。
- 旗をささげ(原文ママ)馬に乗った白衣の騎士
- 鮮やかな色で太陽が昇ろうとしている図
- イスラエルのマーク
- 100のアラビア数字と判読さえ不能な文字のようなもの
これら四つの要素を手掛かりとして、本印刷物の性質および背景について、さらに検討を加える。
旗をささげ(原文ママ)馬に乗った白衣の騎士
「白衣の騎士」から直ちに想起されるのは、聖地奪回を目的とした中世の宗教騎士団、例えばテンプル騎士団などの存在、あるいは米国の白人至上主義団体クー・クラックス・クラン(KKK)の忌まわしい白装束である。
騎士団は、本来キリスト教の聖地エルサレムを防衛し、キリスト教徒を保護し、異教徒(イスラム教徒)から聖地を奪還することを目的として結成された組織である。11世紀以降、テンプル騎士団、聖ヨハネ騎士団、ドイツ騎士団の三大騎士修道会が台頭し、その構成員は修道士であった。
現代においても、聖ヨハネ騎士団の流れを汲むマルタ騎士団(エルサレム、ロードス及びマルタにおける聖ヨハネ主権軍事病院騎士修道会)は、「領土を持たない国家」として主権を認められ、カトリック世界における大きな権威を保持している。
一方、KKKは夜な夜な白装束を纏い、暴力と弾圧を繰り返した過激集団であり、WASP(白人・アングロ=サクソン・プロテスタント)の優位性を盲信する思想に基づいていた。
したがって、「白衣の騎士」はキリスト教的文脈を想起させる強いシンボルである。この前提に立つならば、その騎士が跨る馬の毛色も看過できない。キリスト教美術において「白い馬」はキリストを象徴し、「青白い馬」は『ヨハネ黙示録』第六章第八節における「死」を意味する。
しかし、本件において馬の毛色に関する情報は一切なく、その点は依然として不明である。
鮮やかな色で太陽が昇ろうとしている図
日本に限らず、太陽は古代より世界各地で信仰の対象とされてきた。
春分・秋分、日蝕、日の出、日の入――人類はこれら天体現象を観測するため、莫大な時間と労力を費やし、巨石建造物や祭祀施設を築いてきた。特定の日に太陽光が差し込む巨大な門や神殿を造営し、太陽から死と再生の象徴を見いだし、そこから数多の物語や神話が生まれたのである。
本件印刷物に描かれた「鮮やかな色彩で昇ろうとする太陽の図」も、太陽崇拝に通じる宗教的シンボルであった可能性は否定できない。
ここで、Xが印刷所店主に語った用途を想起する必要がある。Xは、「知り合いの外国人から依頼された。宗教団体の寄付領収書として用いるものであり、怪しいものではない」と述べたという。
この発言からすれば、本印刷物の背後には、やはり宗教組織の関与があったのだろうか。
イスラエルのマーク
「イスラエルのマーク」と称された図像は、おそらくダビデの星を指すものと考えられる。前述のとおり、警察も本印刷物をイスラエル公使館に照会している。
ダビデの星(ソロモンの封印)は、正三角形と逆三角形を組み合わせた図形であり、「火と水の結合」や「人間の霊肉の結合」、すなわち「人間の魂」を象徴するとされる。この図形は日本においては籠目紋と呼ばれ、伊勢神宮にも見られる。また、徳川埋蔵金伝説や「かごめかごめ」の歌、日ユ同祖論といった都市伝説的文脈にも頻出するシンボルである。
「旗を掲げた(原文ママ)馬上の白衣の騎士」をキリスト教の象徴、「鮮やかな色彩で昇る太陽の図」を太陽信仰の象徴と仮定するならば、「イスラエルのマーク」にも宗教的意味が付与されている可能性はある。しかし、ユダヤ教は神を可視化しないという教義を持ち、ダビデの星はあくまでユダヤ民族を示す記号であり、ユダヤ教そのものの宗教的シンボルではない。さらに、キリスト教的象徴とユダヤ的象徴の併置は、原則としてあり得ない構図である。
※もっとも、ユダヤ系画家マルク・シャガールの『私と村』(1911年)のように、ユダヤ教、キリスト教、ロシア正教会のシンボルが同一画面に描かれた例外も存在する。
以上を踏まえるなら、「イスラエルのマーク」は宗教的象徴というよりも、ユダヤ民族やユダヤ文化に由来する結社、あるいは家系(例としてロスチャイルド家の家紋にはダビデの星が描かれている)を指すと解釈する方が妥当であろう。
ただし、このマークを日本の籠目紋と見なす場合、日本の神道との関連も想定できる。籠目紋は魔除けの意味を持ち、天照大御神をはじめとする大和の神々を祀る伊勢神宮の石灯籠にも刻まれている。強引な解釈ではあるが、もしそうであれば、本印刷物に描かれた「イスラエルのマーク」に、日本的宗教観が関与していた可能性も否定はできない。
100のアラビア数字と判読さえ不能な文字のようなもの
最後に残された要素は、「100」のアラビア数字と、その周囲に配された判読不能の文字様記号である。
「100」の数字が額面を示すことは明白であるが、問題はその周囲にある記号の正体である。
専門家による鑑定でも「判読不能」とされており、そもそも文字でない可能性も高い。仮に文字であったとしても、古代エジプトのヒエログリフのような象形文字には該当せず、むしろ文様的要素を持つ図形であった可能性も否定できない。
ただし、あえて「文字」と仮定するならば、日本の神代文字との関連を想定することもできる。神代文字(いわゆる神代文字と呼ばれる記号群)は、神社の石碑や札に刻まれるほか、暗号文や藩札の偽造防止記号として用いられた例がある。
したがって、この判読不能の記号が神代文字であるならば、本印刷物における役割は、偽造防止を目的とする符号であった可能性が考えられる。
まとめ:未解決のまま残された奇怪な印刷物
本記事では、戦後復興期に発生した「謎のニセ札事件」と呼ばれる未解決事案について、既知の事実と推測を整理した。
検討の結果、この「紙幣様印刷物」は、厳密な意味での贋造紙幣とは考え難い。単価50円で1,000枚が発注されていることからも、単なる悪戯ではなく、依頼者にとって何らかの価値・意図・意味を持つ物であった可能性が高い。その性質としては「証券」に近い用途も想定できるが、その発行主体は最後まで判明していない。
依頼者Xは、この印刷物が宗教団体に関係することをほのめかしていた。しかし、これまでの考察から、ユダヤ教やキリスト教とは断定できず、仮に宗教的背景があるとすれば、「太陽」「籠目紋」「神代文字」といった要素から、日本固有の宗教観と結びつく可能性も否定できない。ただし、「旗を掲げた(原文ママ)馬上の白衣の騎士」というモチーフは依然として説明がつかず、その意味は不明のままである。
結局、本件は核心部分が闇の中にあり、事件全体が多くの謎を残している。
しかし、いつの日か、この不可解な印刷物が、時を経て誰かの家の引き出しや倉庫から発見されるかもしれない。その瞬間こそ、この奇怪な「紙幣様印刷物」の真相に迫る手がかりが得られる時であろう。
――あなたの家には、見覚えのない不思議な絵柄の紙片や券類は眠っていないだろうか。
それが、歴史の謎を解く鍵になるかもしれない。
◆参考文献
外人がナゾの紙幣 印刷屋に依頼す 警視庁初提訴 国際刑事警察委へ 朝日新聞 1955(昭和30)年2月6日付
『シンボル辞典』編者,水之江有一,株式会社北星堂書店,1985.
独自視点の未解決事件と昭和の事件
◆ニセ札・偽造硬貨・贋作事件
◆奇妙な噂と事件・事故





』と功明ちゃん誘拐殺人事件-150x150.webp)