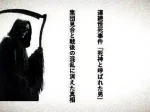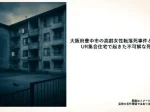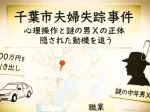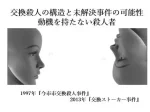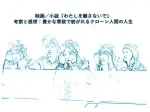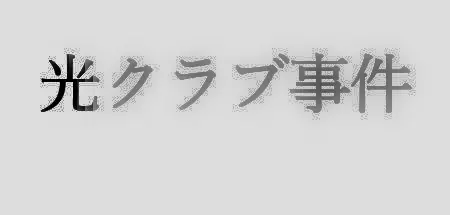
記事要約
終戦直後の混乱期、「光クラブ事件」を引き起こし27歳で自死した山崎晃嗣。
現役東大生でありながら高利貸付業を創設し、偽悪と合理を生きた彼は、「モラルと正義の実在」を否定しながらも、それを完全には捨てきれなかった。
法の形式的正義と人間の内面倫理、そして信じたがゆえに裏切られた者の論理。
山崎晃嗣の思想と行動を辿ることで、戦後から現代に通底する人間不信と制度への問いを再考する。
東京から約7,500キロメートル離れたモスクワで、世界初の社会主義国家・ソビエト社会主義共和国連邦が成立した1922年(大正11年)10月――その同じ月、千葉県木更津市の開業医の家に、四男として一人の男が生まれた。
祖父の代から医業を営む家系に生まれ、父は地元・木更津市の市長を務めた名士であった。医師として、政治家として、その名は地域に広く知られていた。
こうした裕福な名家に育った男は、両親の期待を一身に背負い、旧制第一高等学校(現・東京大学教養学部)に進学。1943年(昭和18年)、22歳で東京帝国大学法学部(現・東京大学法学政治学研究科)へと進んだ。
その名を、山崎晃嗣という。本記事では、「偽悪者」と自らを称し、終戦直後の混乱のなかで『光クラブ事件』を引き起こした山崎晃嗣という人物の思想と行動をたどることで、
法とモラルの境界線、人間の倫理、そして現代社会が抱える合理と不信の問題を再考する。
『光クラブ事件』:山崎晃嗣は人の心を信じない
山崎は、終戦後の混乱期に高利貸付業『光クラブ』を創設し、学生社長として一時代の寵児となるも、27歳にして自ら命を絶った人物である。彼は徹底したニヒリズムと合理主義を体現しつつ、意図的に「偽悪」を演出した。三島由紀夫の小説『青の時代』(新潮社、1950年)の主人公のモデルともされる人物である。
数多の人間、国家、時代に裏切られながらも、「モラルと正義の実在」を完全には否定しきれなかった、逆説的なモラリストでもあった。「女性は道具である」と公言した一方で、女性に対する畏怖と純情を内に秘めていた。
「人生は芝居である」と記し(参考:『私は偽悪者』山崎晃嗣著、牧野出版、2006年、113頁)、刹那的に生きようとした彼は、死に際して自らの写真を机上に飾り、永遠の存在となることを望んだ。
いわゆる『光クラブ事件』は、未解決事件には該当しない。
しかしながら、山崎晃嗣の自死は、彼という人間が時代と社会に対して提示した数多の問いを、未解決のまま残したといえよう。
終戦(敗戦)によりすべてが変わった1945年8月15日以降、無軌道な若者たちによるいわゆる『アプレゲール犯罪』が続出したが、『光クラブ事件』はその象徴的存在である。
本稿では、事件の実態を概説するとともに、「偽悪者」と自らを称した山崎晃嗣という一人の人物について再考を試みる。
なお、山崎晃嗣は、自身の死後、手記の公開を望んでいたものと推測される。その遺稿は、事実婚関係にあった佐藤静子氏の尽力などにより『私は偽悪者』(青年書房、1950年)として世に出された。
本記事は、山崎晃嗣を単なる事件の容疑者(実際には不起訴または起訴猶予処分)として扱うものではない。彼を、一人の実在した人間として、その名を以て記すものである。彼の名が、生きた証として後世に語り継がれることを――山崎晃嗣自身が望んでいたことと信じつつ――。
光クラブ事件の概要
1945年8月15日、日本は連合国に対し無条件降伏を受諾し、長きにわたる戦争に敗北した。これにより、それまでの国家的価値観、社会体制、秩序は崩壊し、国民は焼け野原の中で物資の極端な不足とハイパーインフレーションによる混乱に直面することとなった。
「光は新宿から」――これは、終戦直後の新宿において尾津組が設立した闇市が掲げたキャッチコピーである。この言葉に着想を得て、山崎晃嗣は自らの金融事業に『光クラブ』と名付けた。
ハイパーインフレの渦中、『光クラブ』は新聞に「遊金利殖月一割五分」と銘打った二行広告を掲載し、高配当を謳って出資者を募った。
集められた資金は、現金を必要とする生活者、零細事業者、闇市での現金商取引に従事する者らに対して、高利で貸し付けることで利鞘を得るという金融業務に用いられた。
広告画像は、『私は偽悪者』(山崎晃嗣著, 牧野出版2006.)P21から引用
端的に言えば、いわゆる高利貸金業(いわゆる「闇金」)である。しかし、現役東京大学法学部生である山崎晃嗣が運営するこの事業は、大胆かつ斬新な広告戦略――新聞広告、都電車内広告等――によって注目を集め、創立からわずか三か月で東京・銀座という一等地へ進出。あわせて、事業形態も株式会社へと改組された。
銀座進出以降、取引相手の性質も変化を見せる。従来の小口融資中心から、政府支払の遅延などに悩む大口事業者による資金需要、いわゆる「つなぎ融資」の需要が増加し、山崎のもとには『株式会社光クラブ』への相談が相次いだ。なお、当時において株式会社として正式に金融業を営む企業は他になく、光クラブは日本唯一の「株式会社金融業者」であった。
しかし、GHQ(連合国軍総司令部)および日本政府は、進行するハイパーインフレの抑制および根絶を目的として政策介入を本格化させる。1948年12月19日には「経済安定九原則」が指令され、翌1949年2月には、経済の自立・安定化・インフレ収束を目的とする金融・財政政策、いわゆる「ドッジ・ライン」の実施が始まる。このような政策転換とともに、山崎晃嗣と『光クラブ』もまたメディアの標的となる。現役東大生による派手な広告、金融業務の実態は、好奇と批判の対象となり、「出る杭は打たれる」の格言のごとく、注目の的となっていく。
「ひかり戦陣訓」の画像は、『私は偽悪者』(山崎晃嗣著, 牧野出版2006.)P62から引用し作成
画像化した「ひかり戦陣訓」にイェーリングの「権利のための闘争」があるの。所謂「ヤミ金」の山崎晃嗣らが自らの行い(業務)に19世紀ドイツ法学者ルドルフ・フォン・イェーリング(外部リンク:Wikipediaルドルフ・フォン・イェーリング)の著書『権利のための闘争』(1872年出版)を引用したことは非常に興味深い。
新聞各紙は、『株式会社光クラブ』が不特定多数の出資者から金銭を集めており、これは銀行法に違反するのではないかと報じ始める。そして1949年7月4日、山崎は物価統制令違反容疑で逮捕される。法定上限利息は月9分(年利約108%)であったが、山崎は出資者に対し月一割五分(年利180%相当)の配当を提示しており、これは利息制限法を超える「十日で一割」の高利貸付に該当する行為であった。ただし、最終的には不起訴あるいは起訴猶予処分とされた。
この逮捕を契機として、信用不安が拡大し、いわゆる「取り付け騒ぎ」が発生する。山崎は、1949年11月25日までに債権者に対し総額300万円の返済を約束するが、期日までに資金を調達することができなかった。そして、その前日である同年11月24日、山崎晃嗣は青酸カリを服毒し、自ら命を絶った。
山崎晃嗣の略歴と主な出来事
「高利貸冷たいものと聞きしかど死体にさわれば……氷カシ」
「貸借法すべて清算借り自殺。晃嗣。午後十一時四九分(23時49分)」
引用:『私は偽悪者』(牧野出版、2006年)
1922年10月、千葉県木更津市にある開業医の家に、四男として山崎晃嗣は生を受けた。祖父の代から続く医師の家系であり、父は地元・木更津市の市長を務めた名士であった。なお、出生月については1月生まれとの説もあるが、本記事では、本人の手記『私は偽悪者』(牧野出版、2006年)に記載された10月生まれを採用する。
旧制第一高等学校(現・東京大学教養学部)へと進んだ山崎は、1943年8月、東京帝国大学法学部(現・東京大学法学政治学研究科)に進学する。しかしその翌月、学徒出陣の制度により召集され、軍籍に編入された。
終戦を迎えた1945年8月15日時点、山崎は陸軍主計少尉の階級にあり、北海道旭川に駐屯する北部第178部隊にて糧秣委員を務めていた。だが戦後の混乱の中で、同年12月、陸軍の隠匿物資に関する不正が摘発され、山崎はその関係で逮捕される。翌1946年2月、札幌および旭川の拘禁所での勾留を経て、懲役1年6か月・執行猶予3年の判決を受けた。
その頃、戦後の経済は急速に混乱を極めていた。1946年2月には金融緊急措置令が施行され、預貯金封鎖と新円切替が開始される。翌3月には物価統制令が公布・即日施行され、国家による経済統制が強化されていく。
山崎は1946年4月に東京大学へ復学し、法学部の科目で極めて優秀な成績を収める。その一方で、同年8月には、N大学の元教授が理事長を務める『中野財務協会』において、「毎月2割配当・絶対保証」とうたう金融詐欺に遭い、10万円を騙し取られる経験もしている。
1947年5月3日、日本国憲法が施行される。社会の構造が根底から変化するなか、山崎は新たな時代を見据えた。1948年10月16日、東京都中野区の鍋横マーケット(現・中野区本町および中央地域)に、『光クラブ』の看板を掲げ、事業を開始する。命名の由来は、終戦直後に尾津組が新宿で開いた闇市のキャッチコピー「光は新宿から」に着想を得たものだとされている。
その後まもなく、1948年12月、GHQより「経済安定九原則」が日本政府に指令され、物価・賃金・予算など経済活動の各面にわたる厳格な統制が敷かれていく。
1949年1月26日、『光クラブ』は資本金600万円で株式会社へと改組される。東京・銀座「松屋」裏のビル一室を200万円で借り受け、本店を移転。登記上の本店は旭川とされ、中野は支店と位置づけられた。新聞広告に加え、都電の車内広告など派手な宣伝戦略により、社員・出資者は増加。だが、話題性が裏目に出たのか、日本経済新聞などが銀行法違反の疑いを報じ始め、次第に山崎と『光クラブ』への視線は厳しいものとなる。
さらに同年2月、いわゆる「ドッジ・ライン」が実施され、日本経済の自立と安定化、インフレ抑制のための金融財政改革が強行される。
同年7月4日、山崎は物価統制令違反の容疑で逮捕される。法定利息を超える高利貸付がその理由であった。8月には処分保留で釈放されたが、社会的信用はすでに崩壊していた。逮捕を契機に、出資者たちの間で取り付け騒ぎが広がり、その額は総計3,000万円に及んだ。1949年9月15日に開かれた第一回債権者総会には394名が出席。山崎は、同年11月25日までに300万円を支払うことを約束する。
しかし、約束の履行は叶わなかった。支払期日の前日である1949年11月24日夜、山崎は青酸カリを服毒し、自ら命を絶つ。享年27だった。
| 1922年10月 | 千葉県木更津市の開業医の四男として生まれる。 山﨑家は祖父の代から医者の家系であり、父は市長も務めた(1月生まれとの説もある。 10月生まれは『私は偽悪者(山崎晃嗣著, 牧野出版2006.)』からの引用) その後、第一高等学校(現、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部等)に入学。 |
| 1943年8月(22歳) | 東京帝国大学法学部(現、東京大学大学院法学政治学研究科・法学部)に入学 |
| 1943年9月 | 学徒出陣 |
| 1945年8月15日(23歳) | 終戦(敗戦)時は陸軍主計少尉 北部第178部隊(旭川)糧秣委員 |
| 1945年12月17日 ~ 1946年2月24日 | 陸軍隠匿物資横領の罪で逮捕。 札幌、旭川の拘禁所に拘留。 裁判は懲役1年6月、執行猶予3年の判決 |
| 1946年2月16日 | 1946年2月16日 ハイパーインフレ対策を目的に金融緊急措置令施行。 同月17日、預貯金封鎖、新円切替 |
| 1946年3月3日 | 物価統制令公布、即日施行 |
| 1946年4月(24歳) | 東大復学 法学部20科目のうち優17、良3の成績を収める |
| 1949年6月 | 貸金業法取締法が公布 |
| 1946年8月(24歳) | N大学の元教授が理事長を務め、毎月配当2割を謳い文句にする「中野財務協会」に10万円を騙し取られる |
| 1947年5月3日 | 日本国憲法施行 |
| 1948年10月16日(26歳) | 東京都中野区鍋横マーケット(現、東京都中野区本町4丁目、中央3、4丁目地域の商店街)に「光クラブ」の看板を掲げる |
| 1948年11月12日 | 極東国際軍事裁判の判決言い渡しの終了 |
| 1948年12月19日 | GHQから経済安定九原則(予算の均衡、徴税強化、資金貸出制限、賃金安定、物価統制、貿易改善、物資割当改善、増産、食糧集荷改善)指令 |
| 1949年1月26日(27歳) | 「株式会社光クラブ」に改組。資本金は600万円。 東京都中央区銀座「松屋」裏通りのビルの一室を200万円で契約し、事務所を移転(同所を本店、中野を支店とする。 なお、登記上の本店は北海道旭川市)。 都電に車内広告を掲載し、業績は伸びるが、日本経済新聞など一部の新聞メディアに銀行法違反「疑惑」を指摘される |
| 1949年2月 | 経済の自立、安定化、インフレ対策などを目的にドッジ・ライン実施 |
| 1949年7月4日 | 物価統制令違反容疑で逮捕 |
| 1949年8月 | 処分保留(山崎晃嗣は、著書『私は偽悪者』117頁で「不起訴」と記述している)により釈放される。 逮捕による信用失墜から経営破綻や大蔵省決定の貸出金利の指示(利子制限)などにより債権者から3000万円の取り付け騒ぎが起こる 1949年9月15日 394名の出資者(債権者)が参加した第一回債権者総会が開かれる。 同年11月25日に300万円の支払いを約束(合意)する |
| 1949年11月24日 | 300万円の用意が出来ず支払い期日の25日を前にして青酸カリの服毒自殺。 辞世の句(遺書)は、「高利貸冷たいものと聞きしかど死体にさわれば……氷カシ」 「貸借法すべて清算借り自殺。晃嗣。午後十一時四九分(23時49分)……」 参考:『戦後欲望史 混乱の四、五〇年代篇』赤塚行雄)」 |
この「午後十一時四九分」という時刻まで記された筆跡には、彼の生き方――日々を記録し、秩序の中で自らに課した倫理を貫こうとした姿――が刻まれている。最期の瞬間まで「合意は守られるべし」とするモラルを実践しようとしたその姿は、偽悪者と自称した山崎晃嗣の、誇りと意地の最終表現であったのかもしれない。
人間不信と数量刑法学:山崎晃嗣の倫理観と復讐
そもそも山崎晃嗣は、千葉県木更津市の名家に生まれ、戦前・戦中の価値観と高度な教養を兼ね備えた人物であった。その女性観は、手記『私は偽悪者』に記された「女は道具である」という過激な言葉に集約されているように見える。しかし、軍隊時代の逸話(いわゆる「登別の女」)や、事実婚関係にあった佐藤静子の証言を通じて浮かび上がるのは、むしろ女性に対して極めて奥手で、内心に畏怖を抱く一人の青年の姿である。
ある時、現役税務署職員の愛人である女性が、その素性を秘したまま山崎の秘書となる。山崎は彼女に好意を抱き、同じ想いを寄せられていると信じていたが、やがて彼女が敵対する税務署側の関係者であることを知る。山崎は彼女を「スパイ」と断じ、裏切りに対する報復として、彼女とその背後にいる税務署職員に対して復讐を試みた。
愛が深ければ深いほど、裏切られたときの憎悪は激しさを増す。自らの支配下にあると信じていた相手に、逆に精神的に支配されていたことを悟ったとき、人は激しく揺さぶられる。山崎が感じたのは、自分が「道具」として利用されたという屈辱であった。かつて自らが女性をそう見なしていたにもかかわらず、今度は自分がそう扱われた――その逆転への怒りが、普遍化された女性像への復讐へと変化したとしても、不思議ではない。
山崎晃嗣は、人間に裏切られた。社会に裏切られた。時代に裏切られた。
学徒出陣により戦地へ赴き、北海道で終戦を迎えた彼は、「陸軍隠匿物資横領」の罪で逮捕される。仲間の名を決して口にすることはなかったが、その沈黙に対して感謝や連帯の念が返ってくることはなかった。彼は自己弁護として、自らを「義賊」であると評したが、同様の行為は上官も日常的に行っていた。それでも、上官たちは処罰されることなく、無傷で戦後を生き延びた。
山崎はそこで確信する。「法は人を選ぶ」。同じ行為であっても、「誰がそれを行ったか」によって、法の運用は変化する。身分や地位、社会的属性によって、罪は軽くも重くもなる。彼は、人間のモラルを信用しなくなった。正義を信じなくなった。そして、法すらも信用しなくなった。
そうした絶望と断念の果てに、山崎が構想したのが「数量刑法学」である。これは、犯罪行為を定量的に評価し、「刑罰数量表」という対数的な公定表に基づいて、機械的に量刑を導き出すというものである。裁判官も検察官も、被告人も、その属性は一切関係がない。
A級戦犯であろうと、主計課の上官であろうと、失業者であろうと、資産家であろうと、社会的肩書は無意味である。評価されるのは、ただ「行為そのもの」だけである。
この体系は、一切の感情を排し、「公平性」の名のもとに、完全な形式的正義を実現しようとする。まさに、「人間を信じない人間」による、制度への最後の問いかけであった。
この思想は、現代においてもなお、根深い共鳴を生んでいる。「逃げ得は許さない」「上級国民は逮捕されない」「不逮捕特権があるのではないか」といった言説が、ネット空間に渦巻く。法は平等であるべきだという理念が強調される一方で、実際の法運用の不平等性が日々、告発され続けている。
そうした不満や不信を、極限まで押し進めた社会のイメージとして、映画『エリジウム』(ニール・ブロムカンプ監督、2013年)が挙げられるだろう。同作では、富裕層が宇宙ステーションに逃れ、地球上の貧困層は厳罰主義のもとで管理される。AIによる機械的な裁判システムが導入され、人間的な事情や背景、社会的文脈を一切考慮せず、瞬時に罪を量刑化して処断する。
その社会は、確かに形式的には平等である。だが同時に、それは「情」や「赦し」が一切存在しない、非人間的な法体系でもある。そこには、見せしめ的な逮捕、政治的思惑による国策捜査すら、冷徹な合理性の名のもとに肯定される危険がある。
天才・山崎晃嗣が、この帰結を理解していなかったとは考えにくい。むしろ、彼はそれを深く懸念していたはずである。だが、それ以上に、他人、社会、そして時代から受けた裏切りが、彼の内面を焼き尽くしていた。懸念よりも、怒りが勝ったのだ。
そして、他人や社会、時代からの裏切りに打ちひしがれながら生きる者たちは、山崎晃嗣の時代と同じように、現代にも確かに存在している。
裏切られることを怖れるモラリスト山崎晃嗣
人間の性は、本来傲慢、卑劣、邪悪、矛盾である故、私は人間を根本的に信用しない。
『私は偽悪者』P133
この一節に代表されるように、山崎晃嗣は、他者への根源的な不信を抱いていた。しかしその一方で、彼と事実婚関係にあった佐藤静子は、彼を「常に些細なことにも細心の注意と情熱をかけていた人」と評している(同書、P4)。この対照的な評価こそが、山崎晃嗣という人物の核心を物語っている。
つまり、彼は根源的に人間のモラルを否定する無道徳主義者ではなかった。むしろ、古典的なモラルの価値――自己犠牲、誠実、約束の履行、他者への忠実さ――を強く信じていたからこそ、それが破られたときに抱く怒りと失望もまた、深く激しかったのである。
山崎の冷笑や偽悪的振る舞いは、徹底した道徳の放棄というよりも、信じたがゆえに裏切られた者の痛切な反動である。「人間の性は邪悪である」と記したその言葉は、彼が人間性を論理的に断罪した結果というより、信頼の連続的な破綻を経験した果てに、感情的に「感じてしまった」叫びであったと解すべきだろう。
彼は完全なニヒリストではない。そして完全な無神論者でもない。むしろ、「神を信じたい」と切に願いながらも、その沈黙に裏切りを感じ、やがて否定へと至った信仰者の転落の軌跡に近い。山崎が抱いた人間や社会、そして法に対する不信は、「信じていたが故に裏切られた」という構造を内包している。
彼の合理主義――すなわち数量刑法学の構想や、人間的感情を排した法制度への志向――は、単なる冷徹な機械主義ではなく、破れた信頼への反動として生まれた理性の構築物であった。そしてその合理主義は、戦後混乱から高度経済成長へと至り、やがてバブル崩壊によって信頼や連帯が瓦解した「失われた時代」にも、ひそかに共鳴している。
人間や社会の正義、道徳、秩序といったものを信じたがゆえに裏切られ、そして理性へと逃げ込んだ者の姿は、時代を超えて、現代のどこかにも息づいている。
偽悪の理性、そして未解決の問い:山崎晃嗣が残したもの
(前略)私は社会秩序の規範として、法律は守るが、モラル、正義の実在など否定している。私は合法と非合法のスレスレの線を辿ってゆき、合法の極限、法律によって禁止されていると誤解されているものを、きわめたいうと思っているので、ほとんど強制力のない倫理綱領類似の問題ではなかったが(後略)
『私は偽悪者』P57
この一節に表れているのは、山崎晃嗣が掲げた「偽悪」の論理である。彼は、法を越えはしない。あくまで社会秩序の枠内にとどまりつつ、その縁を歩くことで、法の限界と人間の欺瞞性を暴こうとした。
だが、こうした合理主義の背後には、本来、人の心の動きや道徳に対して敏感で繊細な感受性を持った人間が、自らを守るために無道徳を演じざるを得なかった姿がある。
もしそうであるならば、山崎晃嗣は、ドストエフスキーの『罪と罰』におけるラスコーリニコフにも似た人物であったのかもしれない。彼にもまた、救いと再生の道が用意されていた可能性がある。ゆえに、その死は痛切なまでに惜しまれる。
現代社会に目を転じると、山崎とは逆の方向性が顕著になっている。人間の内面や倫理よりも、法規範のみに従うことが「善」であるかのような風潮が広がっている。
つまり、法律に触れなければ何をしても許されるという、形式主義的な道徳観が、無意識のうちに拡張されつつあるのではないか。倫理綱領のような「強制力なき道徳」よりも、罰則を伴う法律に頼る傾向が強まり、その法は次第に厳罰化され、さらにAIやアルゴリズムによって機械的に運用されようとしている。
これは、理性の絶対化が導いたフランス革命後のギロチンの祭典や、合理主義を骨格とした社会主義・共産主義国家における非人間的体制の記憶と、構造的に相似している。
「人間の性は、本来傲慢、卑劣、邪悪、矛盾である故、私は人間を根本的に信用しない」と語った山崎晃嗣は、私たちに何を問うているのか。
その言葉の裏には、ただの冷笑や虚無ではなく、人間に対する信頼の破綻と、社会制度に対する極限までの問いが潜んでいる。そして今、あらためて問わなければならない。
戦後の混乱期に生まれた『光クラブ事件』から、社会は何を学ぶべきだったのか。そして、合理主義と偽悪のあいだを生きた山崎晃嗣という存在から、我々は何を学ぶべきなのか。山崎晃嗣と『光クラブ事件』は、法とモラル、信頼と裏切り、救済と合理主義といった問題を社会に突きつけたまま、永遠に未解決のまま残された。
それは、ひとつの事件ではなく、社会に投げかけられた思考の課題であり、社会が存続する限り問われ続ける課題となるだろう。
※参考文献
『私は偽悪者』山崎晃嗣著, 牧野出版,2006.
『青の時代』三島由紀夫著,新潮社,1950.
※映像
映画『エリジウム』監督, ニール・ブロムカンプ、主演, マット・デイモン, ジョディ・フォスター,2013.
未解決事件考察と昭和の事件シリーズ
◆オススメ記事







』と功明ちゃん誘拐殺人事件-150x150.webp)