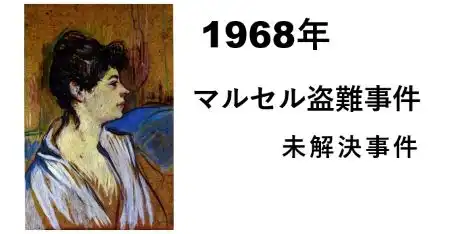
◆ご注意:本記事は、1968年(昭和43年)12月26日午後7時50分から翌27日午前9時40分にかけて発生した、ロートレック作『マルセル』盗難事件の概要ならびに経緯等を、事実に基づき解説することを目的とするものです。同事件は、1975年(昭和50年)12月27日午前0時をもって公訴時効が成立いたしましたが、そのおよそ1か月後にあたる1976年(昭和51年)1月29日、盗難された『マルセル』が発見されるという異例の展開をもって、一定の終息を迎えるに至りました。
なお、本記事において言及する『マルセル』を保管していたとされる人物(A氏夫妻)および、これを預けたとされる人物(C氏)につきましては、いずれも刑事責任を問う意味での「犯人」または「容疑者」として位置づけるものではなく、また、本記事自体も特定の人物を犯人として推定・考察することを意図するものではございません。
ロートレック『マルセル』盗難事件の概要と時代背景
1968年は、国際的にも国内的にも政治的激動の只中にあった年として位置づけられる。フランスにおいては、いわゆる「五月革命(Mai 1968)」が勃発し、既存の秩序に対する若年層の大規模な抗議運動が社会を揺るがした。日本においても同様に、東京大学構内を中心とした学園紛争が激化し、左派系学生運動が各地で頻発するなど、政治的情勢は緊張の度を増していた。
このような時代背景のもと、1968年12月には、日本犯罪史において特筆される二件の未解決事件が相次いで発生している。一つは、1968年(昭和43年)12月10日に東京都府中市において発生した、いわゆる「三億円事件」であり、もう一つは、本稿にて主として扱う、京都国立近代美術館におけるロートレック作『マルセル』の盗難事件である。
後期印象派の画家アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864年11月24日–1901年9月9日)の作品約200点を集めた「ロートレック展」は、1968年(昭和43年)11月4日から同年12月27日までを会期として、京都府京都市左京区岡崎円勝寺町26番地1所在の京都国立近代美術館において開催された。同美術館は、同年より文化庁の所属機関と位置づけられている。
本展覧会は、アルビ美術館および読売新聞社の共催によって開催され、外務省、文化庁、フランス文化省、フランス外務省、在日フランス大使館、読売テレビ放送の後援を受けていた。
京都国立近代美術館の公表資料によれば、会期中の入場者総数は74,748名に達し、1日平均では1,779名の来場者を記録したという。この数値は、当該展覧会が当時の日本社会において極めて高い関心を集めていたことを示すものであり、同時にロートレック作品への一般的な評価の高さを表す指標ともなりうるだろう。(外部リンク:京都国立近代美術館HP)
関係者が、京都国立近代美術館1階展示室中央付近に展示されていたロートレック作『マルセル』が消失していることに気づいたのは、会期最終日である1968年(昭和43年)12月27日午前9時40分頃であった。
その後、窃盗罪の公訴時効である7年を経過した1975年(昭和50年)12月27日午前0時をもって、本事件は犯人未検挙のまま時効成立に至った。『マルセル』の所在も不明なままであった。
しかしながら、時効成立から約1か月後の1976年(昭和51年)1月29日、事件は急展開を見せる。盗難された『マルセル』が、大阪府内に居住する大手音響機器メーカー勤務のT氏(当時50歳代)夫妻の自宅にて発見されたのである。
T氏夫妻の供述によれば、1972年(昭和47年)秋頃または翌1973年(昭和48年)春頃、旧知のC氏(当時28歳)より紫色の風呂敷包みを一時的に預かったという。夫妻はその内容を確認することなく、風呂敷ごと保管していたとされる。
当時50歳代のT氏夫妻にとって、20歳年下のC氏は息子のような存在であり、その人物からの依頼を疑うことはなかったものと推察される。
ところがある日、T氏の妻が風呂敷の中身を偶然確認したところ、美術作品らしき絵画が収められており、それが『マルセル』ではないかとの懸念を抱いた。妻は、信頼関係のあった朝日新聞東京本社の経済部長(T氏妻の兄の旧友)に相談したことを契機として、本件は公に発覚するに至った。
T氏夫妻とC氏は、1964年(昭和39年)頃から家族ぐるみの交際があったとされる。当時、高校生であったC氏は、関西の有名私立大学に進学し、卒業後は住宅関連企業に就職。その後、退職を経て大阪府内の公立中学校において社会科教員として勤務していた。なお、大学在学中より民族派政治活動に従事していたことも確認されている。
1960年代から70年代は、政治的関心が学生や若年層に広く共有されていた時代であり、彼らは「国家」「社会」「政治」「歴史」「国際情勢」、さらには「生活」それ自体の変革を目指して各種の運動に身を投じていた。C氏もまた、教職に就いた後も政治活動を継続し、教育関連書籍の執筆やテレビ朝日系列の討論番組への出演等、公的活動を展開していた。
また、C氏は1987年(昭和62年)に発生した未解決事件『赤報隊事件』の捜査において、参考人として兵庫県警の事情聴取を受けた経緯がある(樋田毅『記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実』岩波書店、2018年、91–103頁)。ただし、警察はC氏に対して刑事責任を問うべき人物とは認定していない。
C氏の説明によれば、1972年(昭和47年)秋頃、京都市在住の知人より「警察の捜索対象となる可能性があるもの」として箱を預かったとされるが、それが『マルセル』であるとは知らなかったという。当時のC氏は、「政治活動に関わるビラ等が入っているもの」と理解していた旨を証言している(出典:『マルセル盗んだのだれ?』読売新聞、1976年1月31日付)。
C氏が預かり品の内容を意図的に確認しなかった背景には、「確認しないことで互いを守る」という黙示的了解が存在した可能性がある。預ける側と預かる側の間にある信頼関係に依拠し、詳細を問わないという行動様式は、当時の政治活動家に共有されていた価値観の一端と考えられる。
本件において、盗難作品『マルセル』は、その所在を知らぬ複数の第三者を介してC氏に渡り、さらにT氏夫妻に移った可能性がある。C氏は、作品を預けた人物の氏名および事件の核心に関わる情報については一貫して沈黙を保っており、その理由として、「情報の開示により関係者に重大な影響を及ぼし、最悪の場合には自死者が出るおそれがある」と述べている。
冒頭においても述べたとおり、本記事は特定人物を犯人と断定したり、事件の真相を推論したりすることを目的とするものではない。本件はすでに公訴時効を迎えており、法的には終結している事件である。
事件発生から半世紀以上が経過した現在においても、C氏の「多くの者に迷惑がかかり、自殺者が出る可能性も考慮した」とする発言には、一定の重みが残る。一方で、さらなる時間の経過の中で、いずれ本件に関する真相が何らかの形で明らかとなる可能性は否定できない。
それが仮に、純粋な好奇心に基づく期待であったとしても、人は未解決の事象に対して「知りたい」という思いを抱かずにはいられない生き物なのである。
ロートレック作『マルセル』とは?作品の価値と特徴
ロートレックが1894年に制作した『マルセル』は、厚紙(縦29.5cm、横46.5cm、いわゆる8号サイズ)に油彩で描かれた作品である。画中に描かれている、特徴的にやや上を向いた鼻をもつ女性は、パリ・ダンボワーズ街の娼婦であったとされている。彼女の横顔は、時代や国境を超えて人々を惹きつける強い魅力を有している。
この『マルセル』には、当時の評価額に基づき3500万円の保険が付保されていたが、専門家による時価評価においては、1億円から2億円に相当するとする見解も存在した。
作品が盗難に遭った後、日本国内の損害保険会社は、契約に基づき保険金3500万円を作品の所蔵者であるフランス・アルビ美術館に対して支払っている。この支払いにより、『マルセル』の所有権は法的には当該保険会社に移転したと解釈されるのが通例である。
しかし、その後『マルセル』が発見された際、アルビ美術館は当該保険会社に対し、支払われた保険金および相応の利息を添えて返還したとされている。これにより、所有権は再び美術館側へと戻された可能性が高い。
結果として、『マルセル』は共催者である読売新聞社を経由し、美術館に返還された。この返還を通じて、ロートレックの作品は再び公の場に姿を現すこととなり、世界中の観衆があらためてその「魂」ともいえる筆致、そして『マルセル』の魅惑的な横顔を鑑賞する機会を得るに至った。
『マルセル』盗難事件の犯行時間・手口と捜査の経過
『マルセル』が盗難に遭った正確な日時については諸説存在するが、1968年(昭和43年)12月26日午後7時50分(閉館後)から翌27日午前9時40分(開館直前)までの間に、何者かによって持ち去られたとする見解が、現在に至るまで最も有力とされている。
もっとも、このことは逆説的に言えば、最終的に犯行の具体的な発生時刻および侵入経路が特定されるには至らなかったことをも意味している。
当時の一部報道によれば、27日午前7時30分頃までは、『マルセル』が展示室内に存在していたとの証言も散見される。ただし、1975年(昭和50年)7月5日に警察が公開した容疑者のモンタージュ写真は、同年12月26日午後11時53分頃、京都国立近代美術館南側の三条通りにおいて、不審な人物を乗せたタクシー運転手の証言に基づいて作成されたものである。
このことから、捜査当局は少なくとも公訴時効が成立する直前の時点(1975年)まで、事件は1968年12月26日夜間に発生したものと認識していたと推察される。
該当の不審人物(以下、Xとする)の特徴は、当時の記録によれば以下のとおりである。年齢は30歳から35歳程度、身長は約160cm、小太りで丸顔、髪型は五分刈り、着衣はグレー(ねずみ色)の開襟シャツと色不明のカーディガンであった。
12月末の深夜にしては軽装といえる服装であり、防寒具等の上着を所持していた可能性がある点については確認が取れていない。Xは上着を所持していたのだろうか。気になる点である。
Xは、前述の通り「京都国立近代美術館」南側約400メートル離れた三条通りからタクシーに乗車し、同所から北方向へ直線距離で約1.5キロメートル離れた京都市左京区白川小倉町「京都大学農学部グランド」の東側で降車したとされている。
以下に示すのは、『マルセル盗難事件』に関する主要な経緯の概略である。
1968(昭和43)年12月28日、「ロートレック展」の共催(主催)「読売新聞社」が『マルセル』の発見者、協力情報に1000万円の賞金贈呈を告知する。
同年12月29日、「京都国立近代美術館」の館長が辞意を表明する。
翌日30日の13時18分頃、「京都国立近代美術館」から150m~300m離れた京都市左京区岡崎円勝寺町の某食品製造会社京都工場倉庫前の通路(「空地」と表現する報道もある)で、同社従業員(機械副主任)の44歳男性が盗まれた『マルセル』の額縁らしき白っぽい額縁を発見する。
同額縁は鑑定の結果、『マルセル』の額縁と断定される。発見場所付近には、犯人(Xまたは別の人物の可能性もある)のものと思しき「ズック靴」の足跡が残っていたと報道されている。
1969(昭和44)年1月4日午前9時頃、同美術館の警備員I氏(44歳)が自宅で自殺したことが明らかになった。亡くなった警備員(守衛)は、事件当日(26日から27日)の当直担当者だった。
京都府警は27日から30日にかけ、I氏に対して計3回の事情聴取を行っていた。京都府警は、犯人が同美術館地下通路から侵入したと考えていたらしく、事件当時の地下通路の施錠の有無等に関して1月6日にI氏への再聴取を予定していたともいわれる。
1969(昭和44)年12月25日、捜査本部が解散する。「京都国立近代美術館」には、合計4回の家宅捜索が入ったとの報道が散見されるため、捜査本部は犯人の侵入経路の特定等に至らなかったと推測できる。
1972(昭和52)年7月10日、警察庁は、『マルセル』の海外流失を考慮し、ICPO(国際刑事警察機構)に国際手配を要請する。
1974(昭和49)年6月27日、翌年の公訴時効成立を控え、警察は捜査本部を再設置した。
1975(昭和50年)年7月5日、容疑者とされる人物のモンタージュ写真が公開された。これは1968年12月26日午後11時53分頃、京都国立近代美術館南側の三条通りにて、不審人物を乗せたタクシー運転手の証言に基づくものである。
同年12月27日午前0時、公訴時効が成立する。警察によると、本事件の捜査には延べ13,400人の捜査員が動員され、対象者(参考人含む)は約4,700名に及んだ。そのうち5名が容疑者として浮上したが、いずれも「シロ」と判断され、捜査は終結した。
大阪府内在住のT氏夫妻宅より、『マルセル』とみられる油彩画が発見され、鑑定の結果、盗難された作品であることが確認された。
以後、警察は任意による聴取を通じ、T氏夫妻およびC氏に対して協力を要請したが、事件の全容解明には至らなかった。なお、C氏は記者会見に応じたものの、真相に迫る具体的証言を語ることはなかった。
守衛の自死と文化的損失『マルセル』事件の見えざる被害者
前述のとおり、本事件発生当時、京都国立近代美術館において宿直を担当していた守衛(警備員)I氏は、事件後、自宅にて自死している。遺書等は残されておらず、本人の内面的な葛藤の具体的内容を知る術はないものの、報道によれば、I氏はロートレック作『マルセル』の盗難に対する責任を強く自覚していたと伝えられている。
また、事件直後の1968年12月27日から30日にかけて、I氏は京都府警による複数回の事情聴取を受けており(参考人としてか被疑者としてかは不明)、加えて翌1969年1月6日には再度の聴取が予定されていた。このような継続的な事情聴取が、I氏の精神的負担を増大させ、自死に至る一因となった可能性は否定できない。
なお、同年12月10日に発生した「府中三億円事件」においても、後に容疑者として報道された人物が、のちに自死する事態が発生しており、こうした社会的圧力が個人の尊厳や生命に影響を及ぼす構造的問題が浮かび上がる。
この点において、自死したI氏は『マルセル』盗難事件の直接的被害者の一人と見なすべきである。また、1968年12月29日に辞意を表明した京都国立近代美術館の当時の館長もまた、社会的責任の重圧を受けた点において、被害者的立場にあったと評価できよう。
しかしながら、本事件における被害者は果たしてこの二名にとどまるものであろうか。
本事件は、世界的に高い評価を受ける文化財を盗み出し、長年にわたり秘匿・死蔵するという行為である。その結果として、当該作品を鑑賞するはずであった無数の人々が、その機会を喪失させられた。すなわち、このような文化財の不正流通は、ある種の意味において、人類共通の文化的利益を毀損するものであり、広義には「世界中の人々」が被害者であるとも言い得る。
当時の文化庁長官・今日出海氏(在任期間:昭和43年6月15日〜昭和47年7月1日)は、1968年12月29日付の『読売新聞』紙上にて、犯人に向けた異例の呼びかけを行っている。氏の言葉は、単なる文化財返還の要請にとどまらず、芸術の公共性と倫理性について深い哲学的認識を含むものであった。
(前略)キミはこのマルセルを普通の窃盗犯と同じように盗みだしたのではないということだ。おそらくキミはこの絵に、異常な愛情と執着を持ったのに違いない。何度もこの絵の前にたたずみ、ながめ入り、そうして自分のそばに置きたくなったのだろう。だから、私はキミを犯人と呼びたくない。キミはおそらく犯罪者ではない。ロートレックの非常な愛好者であることにかけては、私とそっくり同じだろう。キミの気持ちもよくわかる。だからこそ、私の話を聞いてくれ。そうして、考え直してくれ。(中略)キミにわかってもらいたい。すぐれた芸術品は、世界中の人々全部の財産なのだ。それはみんなの目を楽しませるために、苦しみのなかから生み出されたものなのだ。(後略)
「名画マルセルを返して!今文化庁長官犯人に訴える世界の愛好者のため君は悪人ではないはずだ」読売新聞1968年12月29日付
この発言は、犯人を糾弾するのではなく、「異常な愛情と執着」を動機とした可能性を前提に、その感情を一定程度理解しつつも、芸術の本質が私的占有にあるのではなく、「世界中の人々全部の財産」として共有されるべきものであることを強く訴えている点において、きわめて特異であり、静かな余韻をもって、私たちの倫理と想像力に問いを投げかけてくるだろう。
今日氏のこの呼びかけは、単なる盗難事件を超えて、「芸術の公共性」および「文化財の倫理的所有権」について我々に根源的な問いを投げかけている。『マルセル』をめぐる事件は、刑事事件的な関心にとどまらず、芸術をめぐる社会的責任と共有倫理の問題へと接続されるべき性格を有しているといえるだろう。
『マルセル』盗難事件から考える芸術の公共性と人類の共有財産
古今を問わず、人類の宝とも言うべき名画が盗難の憂き目に遭う事件は後を絶たない。そこには、金銭的利益、政治的な思惑、あるいはただひとりで所有したいという欲望があるのだろう。
また、思想や信条、道徳的価値観を盾に、芸術の展示そのものを妨げようとする者たちもいる。優れた芸術を隠し、封じ込めることに「正義」を見出す声すら、いまもなお絶えることはない。
だが、芸術とは本来、すべての人に開かれてあるべきものではないか。一枚の絵が喚起する感情は、観る者それぞれの心の深みに触れ、言葉にならない記憶を呼び覚ます。
それが喜びであれ、哀しみであれ――創作物は、ただそこに在ることで、人の魂に静かに語りかける。誰もが等しく、その声に耳を澄ますことができる世界を、私たちはどこかで願っている。
ロートレックの描いた『マルセル』の横顔――その静かなまなざしが、時を超えて今もなお、私たちに問いかけている。それは、人類が永遠に守るべき、「名もなき女性」の美しい横顔であるということ――。
◆参考文献
「海外への搬出を警戒マルセル盗難で警察庁」読売新聞1968年12月28日付(夕刊)
「名画マルセルを返して!今文化庁長官犯人に訴える世界の愛好者のため君は悪人ではないはずだ」読売新聞1968年12月29日付
「額ぶちだけ発見」読売新聞1968年12月31日付
「マルセル泥こんな男」読売新聞1975年7月5日付
「マルセル盗んだのだれ?」読売新聞1976年1月31日付
「マルセルのナゾ永遠に?私は貝になる!傷つく人が多すぎると」読売新聞1976年2月5日付
「―気流―マルセル盗難事件理解できない教師の態度」読売新聞1976年2月7日付
「一千万円の懸賞金」朝日新聞1968年12月29日付
「額ぶちだけみつかる盗難のロートレックの絵」朝日新聞1968年12月31日付
「名画盗難事件美術館守衛が自殺」朝日新聞1969年1月4日付(夕刊)
「マルセル盗難の捜査本部解散」朝日新聞1969年12月25日付(夕刊)
「ICPO特別手配盗難名画マルセル」朝日新聞1972年7月11日付
「マルセル現れず盗難事件これも時効完成」朝日新聞1975年12月27日付
「盗難の名画マルセル発見時効から一ヶ月後大阪で届け出知らずに預かった専門家二氏本物と断定」朝日新聞1976年1月30日付
「どうなる法律上の責任」朝日新聞1976年1月30日付
「本物だ間違いないマルセル発見高貴な横顔も無事胸なでおろす関係者」朝日新聞1976年1月30日付
「鑑定結果に驚く夫妻押し入れに放置二年半」朝日新聞1976年1月30日付
「難解事件捜査及ばず遺留品もほとんどなく」朝日新聞1976年1月30日付
「つかめぬルートマルセル発見解明全力」朝日新聞1976年1月30日付(夕刊)
「えっ本当よかった仏関係者念押し喜びにわく」朝日新聞1976年1月30日付(夕刊)
「預けた人の名はいえぬマルセル発見気にとめなかったカギ握るCさんは語る」朝日新聞1976年1月30日付(夕刊)
「事実の解明は困難か所有者転々した疑いも」朝日新聞1976年1月30日付(夕刊)
「マルセル事件は終わったか美泥棒…潜む甘え直視したい文化的責任」朝日新聞1976年1月31日付
「入手経路語らずマルセル発見中学教諭が会見京都府警も事情を聴く」朝日新聞1976年1月31日付
「Cさんは元右翼団体員」朝日新聞1976年2月1日付
「ままならぬ真相究明マルセル事件任意【調査】に手を焼く」朝日新聞1976年2月5日付
「マルセルを返還読売新聞社に」朝日新聞1976年2月14日付(夕刊)
「定住外国人の参政権巡り討論 賛成派と反対派が一堂に」朝日新聞1994年5月16日付
「支局長からの手紙:マルセルあれこれ」毎日新聞2011年10月3日付
「テロのうごめき脈々(「時効」 朝日新聞襲撃事件3)」東京新聞2003年3月6日付
樋田毅『記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実』岩波文庫,2018.
井出守『迷宮入り事件の謎―ミステリーより面白い-時効直後に帰ってきた名画』雄鶏社 ,1994.
事件・犯罪編集委員会『最新版 事件・犯罪日本と世界の主要全事件総覧―国際・政治事件から刑事・民事事件』,教育社,1991.
アイキャッチ画像に使用した『マルセル』の出典:『ロートレック展カタログ1982-83』アートライフ1982.
未解決事件・昭和の事件 考察・解説シリーズ
◆絵画盗難事件



と降車場所(京大農学部グランド付近)出典:Googlemap.webp)




























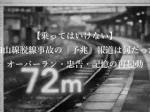
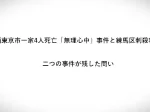
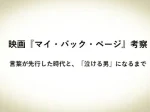
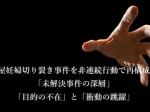

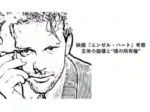
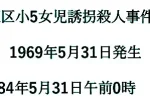



』アイキャッチ画像-150x112.webp)





