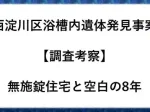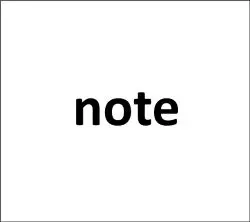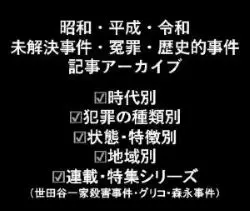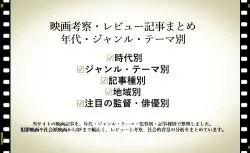『グラン・トリノ』映画 概要
★ご注意:この記事には、映画『グラン・トリノ』のネタバレが含まれています。
「ラストベルト(錆びた地帯)」とも呼ばれる米国の中西部(五大湖周辺の州など)を舞台とする映画『グラン・トリノ(Gran Torino)』は、21世紀のジェンダー平等社会のなかで毛嫌いされつつある父性、父親と息子の関係性、大人の男とその共同体(ホモソーシャルと呼ぶ者もいる)、男らしさの追求、生と死、罪と贖罪そして移民の国アメリカの移り変わり――それらの問題を描いたクリント・イーストウッド監督、主演、プロデュースの傑作映画だ。
2008年に公開(日本での公開は2009年)された『グラン・トリノ』は、名監督クリント・イーストウッド、名俳優クリント・イーストウッド、名プロデューサー・クリント・イーストウッド、そして米国共和党支持者でありつつ、アメリカ建国の精神を受け継いだリバタリアン的価値観を持ちつつ「人間の持つ正義の感情」を大切にするクリント・イーストウッド監督の数多い名作のなかでもひときわ感動的な作品だともいえる。
主人公ウォルト・コワルスキーの遺言は以下のとおりだ。ポリティカル・コレクトネス(political correctness)からはほど遠い言葉が並んでいる。さらにいえば、反ポリティカル・コレクトネスともいえるかもしれない。
わが友人、タオ・ヴァン・ローに譲渡する
豆食いメキシコ人のように車のルーフを切らず
クズ白人のようにペンキで車体に炎など描かぬこと
また後部にカマっぽいスポイラーなど付けぬこと
あれはクソだ
それさえ守れるのならあの車はお前のものだAnd I’d like to leave my 1972 Gran Torino to…my friend… Thao Vang Lor. On the condition that you don’t chop-top the roof like one of those beaners, don’t paint any idiotic flames on it like some white trash hillbilly, and don’t put a big, gay spoiler on the rear end like you see on all the other zipperheads’ cars. It just looks like hell. If you can refrain from doing any of that… it’s yours.
日本語字幕 戸田奈津子
――ややもすれば――この名作『グラン・トリノ』は――21世紀的ではないとの声も聞こえてきそうだが――だからこそ――大切な映画でもある。なぜなら、『グラン・トリノ』は移民の国アメリカの「多様性」をクリント・イーストウッドの視点で肯定的に表現していると思えるからだ。
なお、地図は『グラン・トリノ』のロケ地はアメリカのミシガン州のデトロイト市内ハイランド・パーク周辺である。主人公ウォルトの家は、同市のハイランド・パーク(Highland Park)にある。(参考:『グラン・トリノ』プロダクションノート)
地図を使って主人公ウォルトや愛犬ディジー、そして、タオを想いながらハイランド・パークを散歩するのもいいかもしれない。
『グラン・トリノ』映画 あらすじ
映画『グラン・トリノ』は、主人公ウォルトの妻との別れの儀式――教会での葬儀のシーンから始まる。その教会での葬儀の後、主人公ウォルトの家(アメリカのミシガン州のデトロイト市内ハイランド・パーク)には、妻の死、母親の死、祖母の死のため主人公ウォルトの2人の息子や孫たちが集まるが――「1950年代だと思っている」「人のすることは全て気に入らない」と息子に影口をいわれるほどの頑固者の主人公ウォルトは不機嫌だ。そして、隣に住むモン族の一家では新たな命の誕生を祝うために多くの人が集まっている。自国内の混乱や迫害から逃げ、遠いアジアの地から教会の助力などで移民してきたモン族の一家に生まれた新たな命と100年以上前にポーランドから移民してきたと思われる主人公ウォルトの家族の死――この2つの家族の死と生の場面は映画『グラン・トリノ』と近年の米国を象徴しているようにも思える。
主人公ウォルトはポーランド系移民だ。彼の一族が「いつ」祖国ポーランドから米国に移民したのかはわからないが、主人公ウォルトは朝鮮戦争(1950年6月25日 – 1953年7月27日)に米国軍E中隊第一騎兵師団第三小隊の一員として参加し、1952年の戦闘の功績により「銀星章」を授与されている。その後、帰還したウォルトは50年フォード自動車の組立工として働いた。
主人公ウォルトの朝鮮戦争従軍の経緯も定かではないが、朝鮮戦争時代の米国は徴兵制があったことから彼は徴兵され見知らぬ北東アジアの地で戦ったのかもしれない。なお、朝鮮戦争の米国軍の戦士者は32万人以上、兵士の平均年齢10代後半ともいわれている。
映画『グラン・トリノ』は、頑固者で不機嫌で妻を亡くした孤独な高齢者だが「タフガイ」のウォルトとその隣家に住む「男らしくない」モン族の少年タオ、タオの姉で頭の良いスーとの関係を軸に展開される。

画像はモン族の子供。彼(女)らは、ベトナム戦争(1955年11月-1975年4月30日)の戦禍や政府、他の民族の迫害から逃れるため米国など多くの国に移住(移民)した。クリックで画像が大きくなります。
この3人の関係を軸に展開される映画『グラン・トリノ』は、80年代から90年代の米国の中西部の人種構成の変化、(疑似)父と息子の関係、父性の重要性、家族の外にある階層や職業的繋がりからなる「共同体」、そして、「生と死」、変化しながらも受け継がれる米国の建国精神などを――
父と息子の物語
映画『グラン・トリノ』は父と息子の物語だ。女性一族のなかで暮らす内向的な男児タオは、ヒスパニック系ギャングや同族のモン族系ギャング(タオの従兄弟も構成員)から「男」扱いされていない。彼らは、他人から「殴られないように虚勢を張り」、悪ぶることが「男らしさ」の現わし方だと考えている。「女の仕事」と揶揄される庭仕事(草木の手入)を好み、静かな時を好むようにも見受けられるタオは、そのような彼らの価値観に馴染めないように見えるが――「腰抜けは誰かの後ろ盾が必要」だ。タオは従兄弟が所属するモン族系のギャング仲間の「入会の儀礼」を与えられるがその儀式に失敗してしまう。
タオの姉スーがウォルトに語る言葉が印象的だ。――「男は女より順応性がないから、女の子は大学、男の子は刑務所」――タオもこの言葉のように警察に逮捕され刑務所送りになり最悪は誰かに撃たれ死ぬ可能性もあった。だが、彼は父親となり最良の友人となり互いの孤独を少しだけ癒し合える疑似父親のウォルトに出会えた。
ウォルトは前述のとおり、ポーランドからの移民の一族だ。ポーランド系移民の彼は多感な10代後半から20歳前後の頃、見知らぬ北東アジアで戦い、子供を含む13人以上の人間を殺し、帰還後は自動車製造メーカーの組立工として勤勉に働いたブルーカラーの白人男性だ。ブルーカラーの白人ウォルトはタオに勤勉さを教える。勤勉に働き、自ら金を稼ぎ、車を買い交際相手を見つけ、壊れた家具などを修理し、ビールを飲み、犬の世話と芝の手入をし、同じような階層のブルーカラーの友人たちの共同体のなかで軽口を叩きながら毎日を過ごす――ウォルトはタオに仕事を紹介し、「50年かけて集めた工具」を貸し、同族の女性をデートに誘ったタオに自慢の72年型グラン・トリノファストバック・コブラエンジン搭載を貸す約束をする。
内向的な無職の少年に自立と自律を教え、移民の国にある家族以外の共同体――職業、階層の共同体――に参加させ、その共同体のなかで上手に生きるための言葉遣いや態度などコミュケーションの取り方を教える。これは父性だ。ウォルトの父性がタオを刺激する。それは――疑似的だが――父親から息子へ教えだ。父親から息子への知恵の継承だ。
一方、ウォルトは疑似的息子タオから何を得たのだろうか。ウォルトの実の息子2人やその妻と孫たちは、ウォルトを頑固で不機嫌な時代錯誤の家父長制的な「父」だと思い距離を置いている。日本車のセールスをする実の息子。口先だけで金を稼ぐ息子。人生の大半をフォードの組立工として過ごし、引退後は修理屋を名乗るウォルトも彼ら彼女らと距離を置く。それがウォルトの孤独の原因でもある。孤独な高齢者のウォルトに出来た新しい息子タオ。タオは軟弱だが頭の良い優しい素直な少年だ。ウォルトはタオに無償で人生を教える。ウォルトは実の息子や実の家族以上に疑似息子タオに無償の愛を与えた。それは、タオがウォルトの――疑似的だが――「息子」となり、ウォルトはタオから必要とされたからだろう。
誰かから必要とされる――それは――人間にはとても大切なことなのだ。
移民の国の共同体
1776年7月4日に独立宣言を発表したアメリカ合衆国( United States of America)は移民の国だ。英国からの移民から始まり、世界中の多くの国から自由の国アメリカに移住した(ただし、アフリカ系アメリカ人は奴隷として強制的に連れて来られた)。
移民たちは自身の出自の「民族」や信仰の対象(宗教)を中心に家族をつくり共同体をつくる。だが、共同体はそれら以外にもつくられる。その一つが職業的な共同体であり、所属階層の共同体だろう。
映画『グラン・トリノ』の主人公ウォルトはポーランド系の移民だが、作品のなかに登場する友人はイタリア系の床屋の自営業の男性、アイルランド系の建築会社社長だ。
彼らブルーカラー(労働者階級)の友人関係、ホモソーシャルの共同体の中で使われる言葉は、ポリティカル・コレクトネス(political correctness)からは程遠い。
「ポーランドじじい」「アホなイタ公」「イエロー」「クロ」「米食い虫」「アイルランドの酔っ払い」
(参考字幕:戸田奈津子)
頭の良いタオはウォルト達からブルーカラーの共同体で使われる言葉や態度を学ぶ。繰り返しになるが、ウォルトからその共同体のなかで上手に生きるための言葉遣いや態度などコミュケーションの取り方を教え――一人前の男として――共同体のなかで認められ、自由の国アメリカ、多様な人種、民族、階層、階級が存在する移民の国アメリカでの生き方を教える。
アジアから来たモン族の少年(彼は英語を話す米国生まれだろう)は、移民の国の一員となる。そして、移民の国はこれからも多様な人種、民族を自国の国民にするだろう。冒頭のシーンの「モン族の一家では新たな命の誕生を祝うために多くの人が集まっている」シーンが、それを象徴しているのかもしれない。
一人前の大人と男らしさ
映画『クラン・トリノ』のテーマには「一人前の大人」「男らしさ」があると思われる。この二つの言葉もジェンダー平等やホモソーシャルや父権社会を否定的に捉える00年代以降(米国では90年代以降)の現代社会から見れば時代錯誤で野蛮な価値観だと指摘されるだろう。だが、「1950年代だと思っている」主人公のウォルトやその友人たちは、それらを肯定的に考えていると思われる。なお、ギャング達は「男らしさ」を前述のとおり、他人から「殴られないように虚勢を張り」、悪ぶることが「男らしさ」の現わし方だと考えているようだ。
主人公のウォルトは、「仕事、車、恋人」のないタオを一人前と認めていない。「仕事」は自立のための最低条件であり、車は「自由の象徴」であり、恋人は「他人に認めて貰える存在」になった証だと考えているのかもしれない。車を磨くように「男を磨け」とウォルトは言う。
男同士の話し方を学び、勤勉に働き、車を手に入れ、恋人をつくり機会があればその二人は家族となり子をつくるだろう。それが、ウォルト流の「一人前の大人」の定義かもしれない。そして、それは、1950年代にあった働く米国人――豊かで厚みがあった中間層――の価値観だったのかもしれない。
良質なモノを手に入れ、大切に扱い、壊れたら修理する――使い捨ての現代にない価値――使い捨ての人間関係ではできない共同体があった時代――その時代に生きたウォルトの価値観かもしれない。
ウォルトは「男らしさ」にもこだわりがある。朝鮮戦争に参加したタフガイのウォルトは、銃を持ち、ピックアップトラックに乗り、ジッポを使いタバコを吸い、ビールを飲み、ポーチに星条旗を飾り、72年型グラン・トリノファストバック・コブラエンジン搭載を新車のように磨き上げる。
米国の戦争に参加した(させられた)ウォルト。ポーチの星条旗はなにを意味するのか?愛国心か?コブラエンジン搭載の72年型グラン・トリノファストバックをウォルトは新車のように磨きあげる。だが、彼がグラン・トリノを運転するシーンは一度もない(タオは運転するが)。コブラエンジン搭載の72年型グラン・トリノファストバックは――ある意味――ポーチの星条旗のように――庭先に敷地内に展示されているようにも思える。
飾られた星条旗とコブラエンジン搭載の72年型グラン・トリノファストバック。そのコブラエンジン搭載の72年型グラン・トリノファストバックは、「一人前の男」となったタオに――
受け継がれる米国の建国者の精神
ここからは少しだけ、名画『グラン・トリノ』をつくった名監督クリント・イーストウッド、名俳優クリント・イーストウッド、名プロデューサー・クリント・イーストウッドの他の作品から考察してみたいと思う。
80年代頃までのクリント・イーストウッドが関わる映画は、1965年の『夕陽のガンマン』に代表される西部劇や1971年から始まる『ダーティハリー』シリーズ、1982年の『ファイヤーフォックス』などの娯楽性の強い作品が多く、90年代中頃の恋愛映画『マディソン郡の橋(1995年)』を経て、1997年の『目撃』、2003年の『ミスティック・リバー』などシリアスな作品が増えていく。なお、クリント・イーストウッドは、1930年5月31日生まれのため、第76回アカデミー賞で作品賞など6部門にノミネートされた『ミスティック・リバー』は73歳当時の作品だ。そして、その後も彼の活躍は続く。作品賞などアカデミー賞4部門の栄冠に輝いた『ミリオンダラー・ベイビー(2004年)』、2006年の『父親たちの星条旗』『硫黄島からの手紙』の二部作。『グラン・トリノ』の2006年には、警察の不正と子供を探す母親の実話を元にした『チェンジリング』、2014年、2018年、2019年にはいずれも実話を元にする『アメリカン・スナイパー』、『運び屋』、『リチャード・ジュエル』などの名作を次々と発表している。
これらの名作を次々と発表するクリント・イーストウッドは、共和党支持者として有名だが、一方で国家や国家権力を盲信しない米国建国の精神を受け継いでいるともいえる。
共同体のために戦うが「国家のため」を言い出す者を警戒し、その国家の持つ権力の怖さを常に警戒しながら、自己とその周辺の(例えば家族など)のため、幸福追求のためには命懸けの奮闘をする。
そこからは、米国独立宣言(リンク先はアメリカンセンタージャパンのHP)にある以下の文章が思いだされる。
われわれは、以下の事実を自明のことと信じる。すなわち、すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ。こうした権利を確保するために、人々の間に政府が樹立され、政府は統治される者の合意に基づいて正当な権力を得る。そして、いかなる形態の政府であれ、政府がこれらの目的に反するようになったときには、人民には政府を改造または廃止し、新たな政府を樹立し、人民の安全と幸福をもたらす可能性が 最も高いと思われる原理をその基盤とし、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる形の 権力を組織する権利を有するということ、である。もちろん、長年にわたり樹立されている政府を軽々し い一時的な理由で改造すべきではないことは思慮分別が示す通りである。従って、あらゆる経験が示すよ うに、人類は、慣れ親しんでいる形態を廃止することによって自らの状況を正すよりも、弊害が耐えられ るものである限りは、耐えようとする傾向がある。しかし、権力の乱用と権利の侵害が、常に同じ目標に 向けて長期にわたって続き、人民を絶対的な専制の下に置こうとする意図が明らかであるときには、その ような政府を捨て去り、自らの将来の安全のために新たな保障の組織を作ることが、人民の権利であり義 務である。
独立宣言(1776 年)
このアメリカの建国の精神はクリント・イーストウッドから新しい国民へ。
ウォルトからタオへ。
これからも――受け継がれていくのかもしれない。
それは、タオがウォルトから譲り受けたコブラエンジン搭載の72年型グラン・トリノファストバックと銀星章と愛犬デイジーに象徴されている。
戦争を知る者の最後の闘い
ここでは、映画『グラン・トリノ』の最後のテーマと思われる「生と死」を考察してみよう。主人公ウォルトは朝鮮戦争で13人かそれ以上を殺した。そして、部隊でたった一人だけ生き残り銀星章を授与された。戦場で人を殺した時の気持ちをタオに聞かれ、「知らんでいい」と答えるウォルト。
彼は地下室にひっそりと隠すように保管していたその銀星章をタオに渡す。
そして、銀星章を胸に付け救急車にかけよるタオ。
ウォルトが銀星章に託した意味はなんだろうか?
若い牧師に向い「“死はほろ苦い、悲しみはつらいが魂の救いは癒し”それが“生と死”ならお笑いだ。」と言い放ったウォルト。
タオに向い「お前は大人になった。自慢できる友達だ。お前の人生は今から――」と言うウォルト。
タオに託した銀星章の意味は――「生きろ」だったのかもしれない。そんな気が――する。
※アイキャッチ画像は「朝鮮戦争退役軍人記念碑ワシントン DC」
※モン族の子供(作者アーロン・ブラッドフォード,2011年3月3日)
お時間のある時に以下の記事もご覧ください。家族や親子を考える おすすめの記事
独自視点の海外映画考察シリーズ