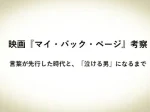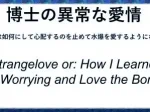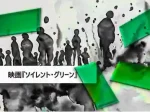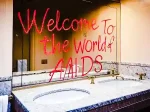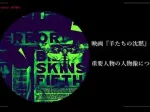映画『星の子』は、今村夏子の同名小説を原作とし、2020年に公開された作品である。監督は『MOTHER マザー』や『さよなら渓谷』で知られる大森立嗣。主演の芦田愛菜が、思春期の少女・ちひろの繊細な心の揺れを見事に表現している。
この物語は、両親が信仰する新興宗教の影響を受けながらも、なお「普通」であろうとする少女の葛藤を描く。信仰とは何か、家族とは何か、人は何を拠り所にして生きるのか。
本作は、静かな光の中にそうした問いを浮かび上がらせる。 原作が持つ淡々とした筆致と、一人称の語りが生み出す孤独感は、映画では光と影、無言の時間、役者たちの微細な表情で繊細に再現されている。宗教と家族、思春期の揺らぎ——それらの普遍的なテーマを描きながらも、現代社会の中で揺れる「信じること」の意味を問いかける作品である。
映画『星の子』の概要|今村夏子の小説を映画化
★ご注意:この記事には、小説・映画『星の子』のネタバレが含まれています。
動画は流れ星。見つかりましたか?
映画『星の子』は、第39回野間文芸新人賞を受賞し、第157回芥川賞候補となった今村夏子の小説を原作に、大森立嗣監督が映画化した作品である。主演は芦田愛菜。2020年10月に公開され、家族と信仰をテーマにした静謐なドラマとして高い評価を得た。
大森立嗣監督は、親と子の関係を独自の視点で描く作品を多く手がけてきた。実際の事件をモチーフにした『MOTHER マザー』(2020年7月公開)(参考:映画『MOTHER マザー』と2014年の埼玉県川口市祖父母殺害事件)秋田児童連続殺害事件から着想を得たとされる『さよなら渓谷』(2008年公開)など、社会の歪みや人間の本質を見つめる作品で知られる。本作でも、信仰に縛られた家族の姿を通して、親子の愛と絆を問い直している。
主演の芦田愛菜は、カルトと家族、そして思春期というテーマを背負う少女「ちひろ」を繊細かつ多面的に演じた。原作の飾り気のない一人称の文体を体現しつつ、成長の痛みと親を愛する心の間で揺れる少女の姿を見事に表現している。
共演者には、父親役の永瀬正敏、母親役の原田知世、母の弟・雄三おじさん役の大友康平が名を連ねる。また、ちひろが憧れる教師・南役には岡田将生、教団の幹部信者である海路さん・昇子さん役には高良健吾と黒木華が起用され、実力派俳優たちが作品に深みを与えている。
『星の子』のあらすじ|家族と信仰に揺れる少女の物語
ちひろは、損保会社に勤める父と専業主婦の母、5歳年上の姉を持つ林家の次女として生まれた。出生時の体重は標準を下回り、「三カ月近くを保育器のなかで過ごした」(今村夏子『星の子』朝日文庫、p.6)。
幼少期のちひろは体が弱く、湿疹や中耳炎、発熱、胃腸炎など、さまざまな病気に悩まされていた。その度に両親と姉も心を痛め、病院での治療や民間療法を試すものの、症状は改善しなかった。
そんな折、父親の会社の同僚・落合が、「ちひろの苦しみの原因は水にあるのではないか」と指摘する。水を変えたほうがいいと勧められ、両親は『金星のめぐみ』という特殊な力を持つ水を取り入れる。
この『金星のめぐみ』との出会いが、林家の世界を一変させる。やがて、その中心には、この水を販売するカルト教団が鎮座するようになる。林家の両親は、他の信者家族と同様に教団の重力に引き寄せられ、深くのめり込んでいく。
その後、姉と母の弟(雄三おじさん)による「水入れ替え事件」などが起こるが、両親の価値観はすでに教団の影響下にあり、家族を愛し、愛されたいと願うちひろと姉も、その力に抗うことはなかった。
小説・映画『星の子』は、信仰と家族のはざまで揺れる少女の成長を描いた作品である。近年、「カルト2世」として注目を集める問題とも重なり、親子の愛と絆を深く問いかける名作といえる。
『星の子』の世界観|家族・学校・教団の三つの世界
映画『星の子』では、主人公・ちひろ(ちーちゃん)の世界が三つの層で構成されている。一つは、父母と姉がいる「家族の世界」。もう一つは、小学校・中学校での「学校の世界」。そして最後に、両親が信仰する教団が作り出した「信仰の世界」である。
この三つの世界の中心にあるのは「家族の世界」だ。家族とは、生まれた瞬間から所属し、自らの意思では変更できない存在である。反抗期を迎えた姉・まーちゃんは、リストカットや家出を繰り返し、やがて音信不通となる。しかし、後に両親へ手紙を送り、自身に子が生まれたことを伝える。家族の縁を断ち切ったはずの姉ですら、完全に家族の世界から離れることはできない。
この三つの世界のうち、「家族の世界」と「学校の世界」の住人たちは基本的に善良な人々である。両親や姉、母の弟である雄三おじさん、その妻や子どもも、それぞれの立場で家族の幸福を願っている。
しかし、両親の「愛と奉仕」の精神は、次第に家族から離れ、教団とその信徒へと向かう。他者への奉仕こそが両親にとっての存在理由となり、家族への愛情すらも教団を通じたものへと変質していく。
一方、「学校の世界」の住人たち――例えば、ちひろの友人・なべちゃんなど――は、時折、「誰かが誰かに騙されている」といった率直な疑問を投げかける。しかし、そこに悪意はなく、彼らは純粋な子どもとしてちひろと関わり続ける。教団の教えとは無関係に、学校の世界には「子ども同士の自然な関係」が広がっている。彼らはちひろが悲しめば一緒に悲しみ、ちひろが笑えば共に笑い、思春期の悩みを共有する。それは、ちひろにとって大切な「もう一つの世界」だ。
対して、「信仰の世界」はより複雑である。この世界に生きる信者たちにとって、それは楽園のように映るかもしれない。しかし、ちひろが尊敬する教団幹部・海路さんや昇子さんには、「詐欺的な手法」「監禁」「リンチ」などの噂が絶えない。また、この世界には完全な平等は存在しない。海路さんや昇子さん、そして父親を教団に勧誘した落合の家は大きく、引っ越しのたびに家が小さくなる末端信者である林家とは明らかに異なっている。
ちひろには、この三つの世界をまたぐ友人が二人いる。それが、同級生の春ちゃんと、落合の息子・ひろゆきくんだ。何事にも消極的で、教団の世界にも学校の世界にもなじめない春ちゃんの変化。そして、両親を安心させるために詐病し、それに気づかないふりをするひろゆきくんの家族。この二人の存在は、ちひろの家族だけでなく、あらゆる家庭に共通する「親子関係の普遍的なテーマ」を象徴しているといえる。
| 映画『星の子』の家族・親族の世界の主な人物 | 映画『星の子』の学校の世界の主な人物 | 映画『星の子』の教団の世界の主な人物 |
| ちひろの父 | なべちゃん(親友) | 海路さん(父は教団執行部長) |
| ちひろの母 | 新村くん(なべちゃんの彼) | 昇子さん(祖母が教団祈祷師) |
| ちひろの姉 | はるちゃん(信者かつ同学年) | 落合さん夫婦 |
| 母の弟(雄三おじさん) | 南先生(憧れの先生) | ひろゆきくん(落合夫婦の子) |
『星の子』の結末とラストシーン|流れ星が象徴するもの
年に一度、12月の週末に行われる教団の全国集会。その舞台は、「星々の里」と名付けられた大規模施設である。参加者は教団が用意したバスに分乗し、泊まり込みで集会に参加する。
中学3年生になったちひろは、初めて両親とは別のバスに乗り、10代から20代の若者たちと行動を共にする。宿泊部屋も両親とは別となり、「家族の世界」から初めて切り離された。その瞬間、ちひろの心に大きな不安が広がる。それは、「もう二度と両親と会えなくなるかもしれない」という恐怖だった(同書、p.163)。
しかし、その不安が頂点に達したとき、母親が現れ、ちひろを散歩に誘う。「流れ星を見に行こう」という提案だった。
親子3人は、満天の星空を仰ぎ、流れ星を探す。同じ時間、同じ場所で、同じ星空を見上げる。
ほぼ毎年、12月初め頃から中頃の間には、ふたご座流星群を見ることができる。「多くの流星が見られるという点では、年間最大の流星群と言えるでしょう。条件の良いときに熟練した観測者が観測すると、1時間に100個程度の流星を数えることは珍しくありません。(引用:国立天文台HP)」これからの人生のなかで「ちひろ」や我々は流れ星をいつく見つけることができるのだろうか?
写真はふたご座流星群の明るい流星(約マイナス3等)と月明かりに照らされた富士山。2021年12月15日2時25分、山梨県富士河口湖町にて撮影。(クレジット:佐藤 幹哉(国立天文台))国立天文台広報ブログから
そして、家を出た姉も、どこかでこの夜空を見ているかもしれない。彼女は、生まれた子どもと共に、流れ星を探しているのかもしれない。
だが、それぞれが見つける流れ星は、同じものではない。両親が見た流れ星を、ちひろは見ていない。ちひろが見た流れ星を、両親は見つけられない。
人それぞれに見える流れ星は違う。だが、それでいい。
物語の途中、教団幹部の海路さんと昇子さんはこう語っていた。「自分の意思で見ようとしても見えないものは見えない」「すべては宇宙の意のままに」(同書、p.41)。流れ星は、誰が見たかではなく、誰がそれを心に留めたかが大切なのかもしれない。
それでも、ちひろの家族はその夜、「いつまでも星空を眺めつづけた」(同書、p.173)。家族という星座の中で、ちひろは自分の光を探し続ける。
映画『星の子』のラストシーンは、この星空を静かに映し続ける。
★参考文献
『星の子』今村夏子著,(朝日文庫)2019,
お時間があれば以下の記事もご覧ください 家族や親子を考える おすすめの記事
おすすめの記事 カルト問題
独自視点の日本名作映画 考察