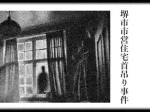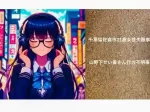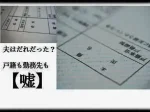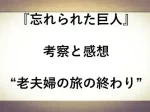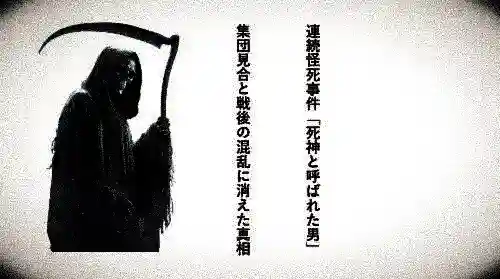
【要約】
敗戦直後の混乱期、複数の資産家女性と結婚し、その妻や家族に不審死が相次いだK氏は、「死神」と呼ばれた。結婚相談所を介して婚姻を繰り返し、財産取得の疑いで警視庁捜査一課が捜査を開始。だが、財産横領・結婚詐欺・殺人のいずれにおいても決定的証拠は得られず、事件は起訴に至らないまま未解決事案として処理された。制度の隙間と戦後の社会的混乱が、真相解明の障壁となった。
1948年(昭和23年)11月15日、全国紙の朝刊に「新妻3名の怪死」「死神のような男」「妻と舅の連続不審死」「4人目の妻から失踪」といった異様な見出しが並んだ。
報じられたのは、戦後の婚姻制度の変化と結婚相談所の台頭を背景に、複数の女性と婚姻関係を結び、不可解な死や財産トラブルを残して姿を消した一人の男――K氏の存在である。
警視庁捜査一課が本件に乗り出したことからも、それが単なる結婚詐欺や財産目的の犯行ではなく、重大事件の可能性をはらんでいたことが明らかとなった。
本記事では、K氏をめぐる連続怪死事件の全容と、その背後にある戦後社会の制度的隙間に光を当てる。
社会的文脈:戦後復興期と婚姻制度の変容
本件の特異性を理解するうえでは、戦前・戦中から戦後にかけての婚姻制度と、その媒介装置の変容を考察する必要がある。
戦前・戦中における婚姻は、旧民法(1898年施行)に基づく家父長制のもとで行われており、婚姻には戸主(家長)の同意が必須であった。
一般的に婚姻は「家」と「家」の結合として捉えられ、個人の意思はしばしば二次的なものとされていた。こうした制度下では、媒酌人(仲人)が極めて重要な役割を果たし、両家の信用と家格を裏書きする存在として機能していた。
戦後、1947年(昭和22年)の民法改正により家制度は廃止され、「婚姻は両性の合意」のみに基づく制度へと大きく転換された。これに伴い、媒介装置としての仲人制度も相対的に弱まり、代わって「集団見合」や民間の結婚相談所が登場する。
これらの変化は、婚姻の自由度を高めた反面、制度的信頼の空洞化を生み、身元や資産状況の確認が不十分なまま婚姻が成立する事例が増加した。
こうした時代背景のなかで、K氏のように複数の媒介機関を利用し、資産家の家に婿入りすることを繰り返す人物が登場したことは、制度的・文化的変容に伴う隙間を象徴する現象であった。
K氏は複数の結婚相談所に登録し、50人近くの女性と文通および見合いを繰り返していた。とりわけ、彼が一貫して婿養子としての婚姻形態を志向していた点は、資産家の家系に入り込むことで経済的利益を得ようとする意図を有していたことを示すものとして、多くの者が捉えていた。
ここでK氏の基礎的背景を確認しておく。K氏の個人史には、戦後社会の構造的変容と制度の隙間が色濃く反映されている。
彼は群馬県内の工業高校機械科に進学するも中途退学し、その後、病弱を理由に安定した職業生活を維持できなかった。父親は鉄道会社から神職を経た経歴を有するが、両親はいずれも死去しており、扶養・支援関係を担う近親者は存在せず、社会的に孤立した状態に置かれていたと考えられる。
このような経済的・社会的資源への接触が限定された状況下において、K氏が繰り返し選択したのは、「婿養子として資産家の家系に入る」という婚姻形態であったのだろう。
それは単なる結婚ではなく、婚姻という制度を通じて経済的安定と社会的包摂を獲得しようとする、戦略的行動であったと解釈することができる。
戦後の家制度解体と婚姻制度の自由化は、従来の血縁・地縁に依拠した信用構造を弱体化させる一方で、媒介機関(結婚相談所等)を介した婚姻において、当事者の身元確認や社会的背景の検証を困難にした。
K氏の行動は、まさに制度的空白を突いた「新たな時代」の事案であり、制度が過渡期にあった戦後社会のひずみを象徴する事件であった。
彼にとって婚姻は、情緒的な結合ではなく、資産と居場所を獲得するための制度的戦略として機能していたと考えられる。この点にこそ、本件の構造的特異性が認められるだろう。
【戦後連続怪死事件の分析】三名の妻および一名の舅の死:婚姻関係と不審死の構造
以下に検討するのは、K氏と婚姻関係を結んだ三名の女性およびその一族の死についてである。
いずれも公式には病死とされているが、その時期的連続性、婚姻と資産の移動との重なり、さらには警察による捜査対象となった経緯から、不審死として再検討されるべき事案である。
本章では、死亡した妻たちおよび舅の具体的状況と死の経緯、それに関連する婚姻の意図や条件といった構造的側面を精査し、K氏の行動に内在する企図を明らかにする。
第一および第二の婚姻:姉妹の短期連続死
K氏は1944年(昭和19年)、栃木県の蒟蒻農家に生まれた次女Aと婚姻した。1946年(昭和21年)には第一子を出産したが、出産から間もなく健康を崩し、同年8月に肺炎により死亡した(享年22〜24歳)。
Aの死は当時、体力の消耗と過労が重なったものと見なされていたが、婚姻から約2年という短い期間での急死であったことも事実である。
その翌年、K氏はAの妹であるBと婚姻関係を結んだ。Bも同じ家でK氏と暮らし始めたが、再婚から1年も経たない1947年(昭和22年)10月、病死(享年20〜22歳)している。
AとBはいずれも20代前半という若さで、かつ短期間で相次いで死亡しており、死因はともに病死とされたものの、その連続性と婚姻関係の経緯には不自然さが残る。
特に、姉妹が同一人物と結婚し、いずれも早逝したという事実は、単なる偶然として処理するには疑念を抱かせるものであり、婚姻と死のあいだに何らかの因果関係があった可能性は否定できないと、当時の警察も認識していたようである。
第三の婚姻と舅の急死:資産移転と親族の死の連鎖
Bの死から間もない1947年(昭和22年)秋、K氏は東京都中野区に居住する不動産所有者一族の令嬢Cと接触し、文通や訪問を通じて急速に関係を深めた。
当初から親族はK氏の素性や過去を疑い、婚姻には強い警戒感を示していたが、Cが妊娠したことにより家族間の力関係は崩れ、最終的に1948年(昭和23年)3月、K氏は婿養子として正式に婚姻関係を結ぶに至った。
婚姻成立後まもなく、Cは重度の悪阻を訴えて入院した。体調は一時的に回復するも、その後再び容体が急変し、手術の末、同年5月29日に死亡した。享年は20代半ばとされる。
さらに奇妙なことに、Cの父親も同年5月3日、心臓麻痺により急死しており、家族内で短期間に二人が相次いで死亡するという異常な事態となった。
この連続死を受け、C家の親族はK氏がC家の家財を無断で売却したとして「財産横領」の疑いで警視庁に訴え出た。
警視庁捜査一課は、栃木県警と連携しつつ、K氏の過去の婚姻歴および複数の女性の死亡事例に着目した。
そして本件を、単なる財産犯罪ではなく、婚姻に付随して繰り返された不審死との関連性を含む広範な事件として捉え、捜査対象に位置づけた。
こうして本件は「位置づけ捜査」として正式に開始された。
第四の婚姻と失踪:婚姻関係の操作と隠蔽工作
1948年(昭和23年)7月、K氏は千葉県市川市に居住していた20代の女性Dと結婚する。
Dは都内の高等学校に勤める教員であり、学歴・職業ともに安定した生活基盤を有していた人物である。加えて、彼女の出自は資産家の家庭に属しており、一定の経済的余裕があったとされる。
しかし、婚姻からわずか数ヶ月後の1948年(昭和23年)11月13日、K氏は突如としてDのもとから姿を消した。失踪は事件報道の直前であり、事前の予兆もなかった。
困惑したDはK氏の住民票を取得したが、そこには東京都武蔵野市内の実在しない架空住所が記載されていた。これは、行政手続を悪用した偽装であり、制度の隙間を突いた意図的な工作とみられる。
Dが現地を訪れたものの、K氏の居住実態は確認されず、住居としての形跡もなかった。K氏は「吉祥寺で商売を始める予定」と語っていたが、その言明を裏付ける職業活動や開業準備の痕跡も一切認められなかった。
K氏の所在が不明のまま数日が経過した1948年(昭和23年)11月17日、事態は突如として動いた。この日、K氏は吉祥寺駅近くの銀行を訪れ、弁護士費用の名目で現金の引き出しを試みた。
しかし、行員の一人が新聞報道によりK氏の顔と名前を把握しており、不審を抱いて直ちに通報。K氏はその場で財産横領容疑により現行犯逮捕された。
また、この日、K氏には別の女性との見合いの予定が入っていたとされる。この事実は、彼がDとの婚姻を維持しながらも、同時に次なる資産家への接近を企図していたことを示すだろう。
警視庁捜査一課の介入と釈放:何が立件を阻んだのか
K氏の逮捕は、当時の社会に衝撃を与え、各方面から注目を集めた。しかし、結果的に刑事責任を問うには至らなかった。
警視庁は捜査一課に捜査本部を設置し、栃木県警と連携して本格的な捜査に着手した。捜査一課は殺人や傷害致死といった重大事件を専門とする部署であり、同課が本件を担当したこと自体、警察が当初から連続不審死との関連を重視していたことを物語っている。
警察が特に注目したのは、K氏の異常な婚姻歴と、それに伴って発生した複数の配偶者の死、さらには舅の不可解な急死であった。これらの死亡事例において、犯罪性を直接示す証拠は得られなかったが、いずれも不審な状況を伴っていた。死亡時期が短期間に集中し、病状の急変や死因特定の困難さといった要素が共通しており、警察はそれらの事例に構造的な連関の可能性を見出していた。
Dに対する財産横領の容疑は、捜査着手の形式的契機に過ぎず、警察は当初から殺人を含む重大犯罪の可能性を念頭に捜査を進めていた。とりわけ、K氏の一連の行動が、婚姻制度の隙間を利用した連続的かつ計画的な犯行である可能性を重視していた点は見逃せない。
ただし、本件が発生した1948年(昭和23年)は、同年5月に施行された新刑事訴訟法の下、戦後憲法の理念に基づく「疑わしきは罰せず」の原則、および厳格な証拠主義が刑事手続の根幹に据えられていた。すなわち、捜査と立件には、戦後司法制度の構造的制約が強く作用していた。
捜査当局は周辺証拠の収集と経緯の精査を重ねたものの、K氏の行動を殺人に直結させる証拠は、最後まで得られなかった。死亡した配偶者および舅の遺体からは、外傷や毒物の痕跡は検出されず、医学的所見も自然死あるいは病死との判断にとどまった。検察も慎重な姿勢を崩さず、捜査は最終的に行き詰まりを見せた。
その結果、K氏は財産横領容疑についても釈放され、起訴には至らず、事件は刑事手続上、終了扱いとされた。
複数の死が一人の人物と関連しながらも、起訴に足る決定的な証拠を欠いた本件は、「疑わしきは罰せず」という刑事司法の基本原則、そして、制度としての証拠主義と当時の技術水準との乖離がもたらした限界を示す、象徴的な未解決事案となった。
まとめ:戦後社会の混乱に消えた「死神」の足跡
K氏の足取りはその後、途絶えた。釈放以降の所在について、公式に確認された記録は存在していない。あれほど世間を騒がせた事件の中心人物が、時代の混乱に呑まれるように記録と記憶の彼方へと消えていったという事実は、戦後の不安定さを象徴するとともに、本件に一層の不可解さを与えている。
1940年代後半、日本は敗戦直後の混乱期にあり、戸籍制度や警察の情報管理体制も現在のように厳格ではなかった。住所や氏名の変更は比較的容易であり、全国的な情報の共有体制も未整備のままであった。
戸籍や住民票は紙媒体で管理されており、空襲による役場の焼失や、疎開・転居の頻発により、その正確性は大きく損なわれていた。人々が自らの身分を証明する手段すら、当時は不安定であったといえる。
このような時代背景に照らせば、K氏が身分を偽り、別人として生き直すことは十分に可能であった。当時は、他人名義の戸籍が売買される事例も存在しており、そのような手段を用いれば、過去の身元を追跡されることなく、新たな土地で生活を始めることも現実的に可能だっただろう。
とりわけ、戦災により死亡または行方不明となった者の戸籍が、ブローカーを介して第三者の手に渡る事例も複数確認されている。K氏がそのような手段を用いていたとすれば、戦後社会の混乱が、いかに個人の追跡を困難にしていたかが浮き彫りとなる。
事件の報道は一時的に世間の関心を集めたものの、次々と発生する社会問題や新たな事件に埋もれ、やがて忘却の彼方へと押し流された。「死神」とも呼ばれたK氏の名も、次第に人々の語りから消えていった。
しかし、その軌跡が完全に消えたわけではない。本件が提起した諸問題――婚姻制度の悪用、戦後社会における法と倫理の空白、そして未成熟な科学捜査による証拠収集の限界――は、今日においてもなお検討されるべき課題である。
現代では、インターネットやSNSの普及により、他者と出会い、関係を築くことがかつてよりも容易になった。
一方で、身元を偽り、利害を前提とした婚姻関係等の人的関係性を構築するリスクも高まっている。そうした環境において、過去の事例が異なるかたちで再現される可能性は否定できない。
本件は、事実の全貌が明らかにならなかったという点で未解決事件である。だが同時に、それは現代社会に対する警鐘としての意味を、今なお失ってはいない。
◆参考資料
読売新聞1948年11月15日付
読売新聞1948年11月16日付
読売新聞1948年11月17日付
読売新聞1948年11月18日付
読売新聞1948年11月19日付
読売新聞1948年11月20日付
読売新聞1948年11月22日付
朝日新聞1948年11月19日付
◆戦後の事件


























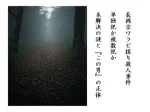
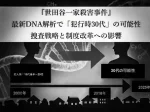




のアイキャッチ画像_edited-150x112.webp)