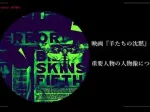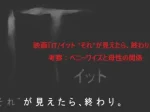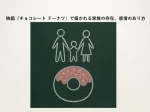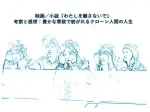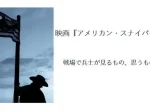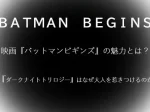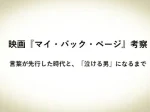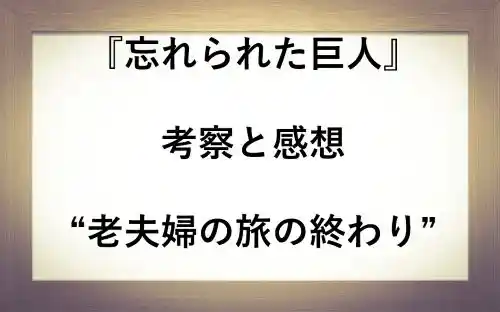
要約
カズオ・イシグロの長編小説『忘れられた巨人』(2015)は、アーサー王亡き後のブリテン島を舞台に、老夫婦アクセルとベアトリスの旅を描いた作品である。物語は、記憶を奪う「霧」の存在や、人々の忘却と再生、夫婦の愛情と裏切りをめぐるテーマが静謐に語られる。
作中に登場する「島」は、死後の世界やアヴァロンを想起させる象徴的な場として描かれ、ベアトリスの旅の結末と深く結びついている。読者自身も霧に包まれるような不思議な感覚を体験し、再読ごとに異なる印象を与える点が大きな特徴である。
小説や映画、ゲームといった媒体を問わず、創作物に用いられることが多い「アーサー王伝説」。子供の頃、「エクスカリバー」という言葉の響きに惹きつけられた記憶がある人も多いことだろう。
ノーベル文学賞の受賞作家であるカズオ・イシグロにも、そんな「アーサー王伝説」を題材にした作品がある。それが『忘れられた巨人』という長編小説だ。
本作は不思議な読後感を持つ作品で、一読しただけでは意味が読み取りづらい部分も少なくない。今回は、筆者が本作を幾度か繰り返し読んだ上での感想や、考察を書いていきたいと思う。
『忘れられた巨人』の作品概要
『忘れられた巨人』は2015年に出版された、カズオ・イシグロの長編小説である。アーサー王が亡くなった後のブリテン島を舞台として、息子を訪ねる老夫婦の旅路が描かれて
本作のジャンルは、「アーサー王伝説」を下敷きにしたファンタジー小説だ。しかし、本作には動的な、いわゆるファンタジーにありがちな激しい要素はあまりない。老夫婦が互いを気遣い合いながら進んでいく描写や会話が多く、冒険活劇のようなファンタジーを期待して読むと肩透かしを食らうかもしれない。淡々と進む物語の中に潜む、不思議さや不気味さが本作の持ち味である。
本作では、老夫婦の愛情や記憶、戦い、そして、人々に忘却をもたらす「霧」とその原因が、カズオ・イシグロ特有の静謐な筆致で描かれている。
あらすじ
アーサー王が亡くなり、争っていたブリトン人とサクソン人が一見平和に暮らしている時代。ブリトン人であるアクセルとベアトリスは、息子と一緒に暮らすために、村から旅立つことになった。
道中、老夫婦は様々な人と出会う。「霧」の影響でありとあらゆるものをすぐに忘れてしまう人々。不思議な船頭にサクソン人の戦士・ウィスタン、アーサー王ゆかりのガウェイン(後に解説)、同胞たちに憎まれ村にいられなくなった少年・エドウィン。
旅の途中、様々なものを見聞きしたアクセルは、過去を少しずつ思い出していく。自分がかつて何者だったのか、ベアトリスとの間に起こったこと。そして、息子の現在。
そして二人は、忘却を起こす霧の正体に近付いていくことになる。
考察:ベアトリスが渡った「島」とは?
本作には、印象的な島が登場する。名前も何もなく、ただ「島」と表現される存在だ。行くためには船頭が漕ぐ小さな船に乗る必要があり、その船頭からして「普通の島ではない」という場所だ。
どの様に普通ではないのか。作中の表現を簡単にまとめると、次のようになる。
- 島には何人もの人が住んでいるが、お互いの存在を感じ取れることは無い。しかし、特別な状況下において、他の人の気配が感じられることがある
- 並外れた愛情で結ばれた2人であれば、島で一緒に暮らすことができる
- 一度島に渡ってしまうと、帰ってこられなくなる(明言はされていないが、1人取り残された老婆たちの言葉から筆者が判断)
では、この島とは一体何なのだろうか。筆者なりに考えていると、「アーサー王伝説」に登場するアヴァロンという島に思い立った。
アヴァロンはブリテン島のどこかにあるとされる伝説の島で、りんごの名に由来する楽園である。アーサー王が戦争で受けた致命傷を癒すために訪れたとされており、彼の最期の地となった。一説によると、アーサー王はいつかくる復活の時のために、この島で眠りについているという。
アヴァロンはどんな場所なのか。その詳細は分からない。しかし、アーサー王の死と生(復活)に関する場所であることから考えて、常世(あの世)に近い存在であることは理解できる。
アクセルとベアトリスのうち、島に渡ったことが明確に描かれているのはベアトリスだけだ。ベアトリスはアクセルと異なり、「何らかの病にかかっていること」・「島を認識できていること」・「息子が島にいることが分かる」ことが描かれている。
ベアトリスとアクセルは、本作の世界に立ち込める「霧」の影響で様々な事実を忘れてしまっていた。しかし、島に渡ろうとしたときに、その「霧」はすでにない。2人の間に起こった諍い。息子をすでに失っていること。こうした事実が、アクセルとベアトリスの前に立ちはだかることになる。
死んだはずの人が住まう「普通ではない」島。そして、それを認識できる病を抱えた老婆。何より、一度行くと帰っては来られない場所。そう考えると、本作の「島」は黄泉の国なのだろう。船頭はいわば、三途の川の渡し守だ。アヴァロンはギリシャ神話にも関係しているから、カロン(ギリシャ神話の冥界の川の渡し守)と似た存在とも考えられる。
アーサー王はブリトン人の君主である。そして、ベアトリス(とアクセル)もまた、ブリトン人である。ブリトン人はブリトン人の君主が眠る土地で、心静かに死後の世界を生きるのかもしれない。 アクセルもまた、近い将来、島を訪れるのだろう。しかし、ベアトリスと一緒にいられるとは限らない。「霧」がなくなったことで、アクセルはベアトリスの裏切りを思い出してしまったからだ。ベアトリスもまた、アクセルに受けた仕打ちを忘れることはないだろう。
『忘れられた巨人』を読んだ感想
本作は不思議な作品だ。霧に包まれて「忘れて」いるのは作中の登場人物であるはずなのに、読んでいるこちら側も霧の中に入ったような感覚に陥ってしまう。これは筆者にとって、非常に不思議な感覚だった。
その不思議な感覚がどこからくるものなのかと考えると、タイトルにもなっている「忘却」と、その原因である「霧」に行き当たる。
本作の世界は、全てのものが靄(モヤ)に包まれた様にどこかぼやけて感じられる。それはおそらく、登場人物たちが霧による忘却のせいで「確固とした自己」を失ってしまっているからだろう。「過去の記憶をはっきりと語れない」という事象により、登場人物の人となりがつかみにくくなっているのだ。
それはアクセルやベアトリスに対しても同じである。会話によって、2人とも善人であることやアクセルの人間的な深さなどは伝わるが、彼らを形成してきた物事は分からない。断片的に提示される事実を、つなぎ合わせていくしか理解する方法がないのである。
この傾向は、物語の外縁に位置する人々に顕著だ。記憶がない人は、あらゆる経験がなく、いわばまっさらな状態だ。物語の冒頭でパニックに呑まれるサクソン人が描かれているが、これが本作の本質を突いている。パニックは誰でも陥るものだが、経験がない人ほど混乱しやすい。目の前で起こる状況に対処できないからこそ、防衛反応としてパニックを起こしてしまうのだ。そしてパニックに陥っているにも関わらず、その原因を忘れてしまう。
人々の狂乱状態。さらには、すべての外殻がぼやけた世界。これが読者にもたらす影響は非常に大きい。読む側も登場人物たちと同じく、忘却の波に飲まれてしまうのだ。少なくとも筆者は霧の影響を受けて忘れてしまい(もしくは理解できずに)、幾度か読み返すことになった。
本作は特に難しい言葉を使っているわけではない。ただ、頭の中に霧がかかったように、物語の上辺部分をなぞって読み進めてしまう。
物語の構造を完全に理解するためには、もう少しの再読が必要だろう。しかし読書中の感覚、さらには読後感も、他の小説ではなかなか味わえない感覚が得られる作品だと感じて、よりワクワクしてしまっている自分がいる。
まとめ
カズオ・イシグロの『忘れられた巨人』は、読む人や読むタイミングによって、大きく印象が変化する作品だろう。アーサー王やガウェイン卿へのイメージ、アクセルやベアトリスに対する感覚。「霧」のせいかもしれないが、再読の度に少しずつ心象が変わっていく。
他の人は本作を読んで、どのように感じるのだろう。ありとあらゆる人の話を聞いてみたい。自分とは違う感覚を持つ人の話を聞いて、新しい視点を発見したいと思う。
もしくは、数年たった後、別の見方で物語を考察しているかもしれない。その時がちょっと楽しみである。
◆カズオ・イシグロ作品紹介
◆独自視点の映画紹介