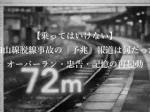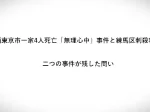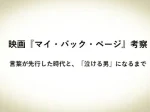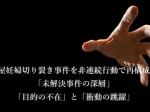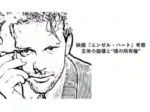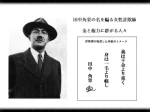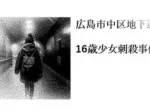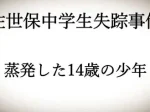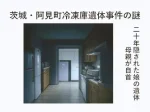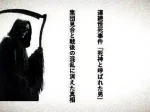かつて、貴き血筋に育まれた少女がいた。九條家――平安の面影をいまに伝える名門に生まれながら、彼女は静かに殻を破る。焼け落ちた邸、失われた母、凍える家族の沈黙。
胸に宿る小さな祈りを頼りに、彼女はカトリックへと身を投じた。名もなき人々に寄り添い、そしてある朝、老いた男と家を出る。
その「家出」は破滅ではなく、ひとりの目覚めであり、旧い制度が静かに崩れ始めた時代の覚醒でもあった。 令嬢の足取りは、制度に縛られた日本の過去をそっと踏み越え、新しい時代へ向かう微かな光となった。
平安時代から続く五摂家筆頭の元公爵家
九條家は、藤原北家の嫡流として平安期より摂関を独占した「五摂家」の筆頭である。朝廷において最も高い家格を誇り、時の天皇に仕え、代々の政務を担ってきた由緒正しき家柄であった。
明治維新後も、その由緒に基づいて旧公家の中でも最高位に列せられ、華族令により侯爵、のちに公爵に叙される。京都に本邸を構えながらも、政治と社交の中心である東京・赤坂にも邸宅を構え、両都にわたって華族文化の象徴的存在であった。
加えて、東西本願寺や真宗佛光寺派の本山『佛光寺』とは深い姻戚関係を持ち、信仰と血縁のネットワークを築いてきた。さらに、皇室や薩摩藩主・島津家をはじめとする他の旧華族とも婚姻や縁戚関係を結び、名門としての地位を揺るぎないものとしていた。
こうした宗派と血統を超えた広範な結びつきは、公家としての宗教的権威と、近代華族としての社会的・財政的基盤を支える装置として機能し、日本近代史において特異な重層的ネットワークを構築していたのである。
旧華族の娘:愛を求めカトリックへの改宗
M子は、1927(昭和2)年、九條公爵家の父と島津家出身の母の長女として、東京・赤坂の邸宅で誕生した。彼女は、三人姉弟の長女であり、生まれながらにして将来を嘱望された存在だった。だが、11歳の時に母を病で喪い、その喪失は彼女の内面に深い影を落とした。
幼少期からすでに乳母に育てられていたが、母の死後はその存在にいっそう依存し、実の母の不在は埋めがたかった。父との距離も終始、縮まることはなかった。
幼少期から学習院初等科に通い、格式ある教育を受けたが、1945(昭和20)年、戦火は九條家の赤坂邸宅をも焼き尽くし、学習院高等科を中退することとなる。その後、京都へ移住し、家祖の墓所維持を目的に設立された九條家内山財団の管理下にある寺院に身を寄せた。
伝統ある家柄の娘でありながら、戦後の混乱と生活の逼迫は、彼女にとって避けがたい現実であった。
1947(昭和22)年、彼女を長年育ててきた乳母が郷里の長崎に帰ると、M子は深い孤独感に包まれる。精神的な寄る辺を求めて、同年より京都・河原町にあるカトリック教会に通い始め、4月22日には正式に洗礼を受け『小さきテレジア』の名を授かる。
その選択は、仏教との深い結びつきを持つ九條家にとって衝撃的であり、家族からの反対の声もあったと言われる。しかし、M子は信仰の世界に安らぎを見出し、やがて教会の貧困者救済活動に積極的に関わるようになった。
その活動の中で、彼女は一人の男性――54歳のN氏と出会う。人生経験豊かで、教会に尽力するN氏に、M子は父性と信頼を見出し、次第に心を寄せていくようになった。
駆け落ちと呼ばれた家出の真相:彼女家を出た理由
貧困者救済活動を共にしたM子は、次第に疲労が蓄積し、ついには過労により体調を崩してしまった。彼女はN氏の献身的な付き添いを受けながら、N氏と共に九條家に戻り、静養することとなる。
看病の合間にも、N氏はM子の心の支えとなり、その絆はさらに深まっていった。しかし、九條家の中でその関係は穏やかには受け入れられず、特に父は、二人がこのまま同居を継続することに強く反対した。父は気弱な性格であったとも伝えられており、父としての責務や家名の重圧が、寛容な判断をさらに困難なものにしていたのかもしれない。
一方で、教会内でも二人の親密さを巡って様々な憶測が飛び交い、不穏な空気が漂い始めていた。信仰と奉仕の場であるはずの教会において、噂という名の疑念はM子の心を徐々に追い詰めていった。
1947年4月25日の早朝、M子とN氏はついに決断を下す。このときM子は、もしものときのためとして、青酸化合物を所持していると周囲に語ったとも伝えられている。その言葉が真実だったかどうかは不明だが、彼女の決意の深さを示す逸話として残っている。
まずは京都市内の教会関係者であった新聞記者の自宅に2、3日身を寄せ、その後、戦後の混乱期に設置されていた『北高野引揚者用寮』へと移る。その場でも長居はできず、次第に人目を避けるようにして洛南の寒村へとたどり着いた。
そこには田畑が広がり、世間から隔絶された静けさがあった。二人はそこで、わずかな衣服と信仰心を抱え、心身を癒すための仮の生活を始めるのだった。
メディアが描いたスキャンダル:令嬢と年上男性の関係
新聞各紙は、元公爵令嬢と年の離れた男性との家出を一斉に報道し、その関係性に対する社会的関心を煽った。
報道では、N氏が前年に妻を亡くし、子どももいないことが取り上げられ、孤独な中年男性が若い令嬢に接近したという構図が描かれた。さらに、九條家との交渉の際に、N氏が強引な物言いをしたとされる証言なども紹介され、読者の感情を刺激する記事が紙面を占めた。
一方で、賢子の妹が教会を訪ねて話し合いを求めた際、N氏が高圧的な態度を取り、「何しに来たのか」と言い放ったという証言も取り上げられた。この場面は、姉妹の断絶を象徴する出来事として報じられ、N氏の人柄への疑念を深める一因となった。
また、N氏がM子を「甘言に乗せて連れ出した」のではないかという憶測も飛び交い、二人の関係性をセンセーショナルに描く記事が紙面を賑わせた。
こうした一連の報道により、N氏に対する否定的な印象が社会に広まり、旧華族への同情と、「育ちの良いがゆえに世間知らずな令嬢が騙された」というステレオタイプが一層強調される結果となった。
華族という封建的象徴と「恋愛という自由意思――この対照的な二つを結びつけ、大衆の驚きと興味を煽ったのはメディア自身である。
報道はこの出来事を「元公爵令嬢の駆け落ち」という物語に仕立て、センセーショナルな演出を加えた。それは当時の読者にとって絶好の娯楽となり、週刊誌や新聞の紙面を賑わせる格好のスキャンダルとなった。
報道は事実以上に物語性を求め、読者の関心を掴むための演出を過剰に施していた。
語られた心の叫び:元令嬢の手記から読む孤独と赦し
父こひし 母やこひしき わが運命(さだめ) 淋しむこころ たれに告げむや
出典:元侯爵令嬢M子氏の手記『読売時事』昭和24年2月号
『読物時事』に掲載されたM子の告白は、家制度の崩壊と個の孤独を赤裸々に綴るものであった。幼少期に母を失った彼女にとって、家族との絆は希薄で、乳母だけが心の寄る辺だった。
父との関係も疎遠であり、顔を合わせるのは一日にせいぜい数回、食卓を囲む機会は年に一度の正月に限られていたという。そのような環境のなかで、彼女は常に「家族」というものへの渇望を抱えていた。
戦後の九條家は、外見の格式とは裏腹に生活苦にあえぎ、家計は月に三百円まで落ち込み、名門の末裔であることと現実との乖離が、彼女の心に深い矛盾と痛みを刻んでいた。
そうした中で出会ったN氏は、父の面影をもつ年長の存在として、彼女の心を包み込んだ。N氏の言葉や振る舞いは、M子にとって慰めであり、信頼であり、彼女は自然と「お父ちゃん」と呼ぶようになったという。
血縁では埋まらなかった心の空洞を、他人との情愛で埋めようとするその姿は、孤独と求愛の入り混じった切実な姿であった。また、教会での奉仕活動を通じて彼女は「必要とされること」の喜びを知り、そこで初めて自分自身の価値を感じたと語っている。
その感覚こそが、冷たい家の壁よりも、祈りと労働のある教会を自らの居場所とする決意へとつながっていったのである。告白文は、「封建的家族観への告発」であると同時に、「父を赦す娘の祈り」、そして「居場所」を模索するひとりの若い女性の切なる記録でもあった。
信仰と奉仕の人生:保育園創設と晩年の活動
家出から数年を経た1955(昭和30)年8月1日、M子は大阪・此花区に社会福祉法人「人類相愛事業M保育園」を創設した。その理念は彼女がカトリックの奉仕活動で培った価値観に根ざしていた。
保育園の設立には、松下電器産業の創業者・松下幸之助や、経済人として知られる北沢敬二郎ら関西財界の支援があったとされ、彼らとの信頼関係は、M子の真摯な姿勢と高い理想に裏打ちされていた。
当初は数十名の子どもを対象とする小規模な園であったが、地域住民や信徒らの支援を受けながら徐々に拡大する。同保育園は、保育だけでなく、児童の教育や情操にも力を入れ、時代の変化に対応する柔軟な体制を築き上げていった。
M子は、1995(平成7)年に園長職を後進に譲った後も、施設に併設された少年部で引き続き指導にあたり、子どもたちに寄り添い続けた。園には皇族関係者も公式に訪れ、その慈善事業の誠実さと継続性は社会的にも評価されるに至った。
元公爵令嬢として生まれ、家を捨て、信仰と奉仕に人生を捧げたM子の歩みは「実践的信仰」の結晶として施設の隅々に刻み込まれている。
一方で晩年の記録は乏しく、生死に関する公式発表も確認されていない。ただし、彼女の功績は、「世を捨てた令嬢」ではなく「社会に尽くした一人の女性」として静かに歴史に刻まれている。
“身分の終焉”と“個の再生”:彼女が選んだ道とは
九條の令嬢の家出劇は、旧華族制度が瓦解する混乱期に、血統・宗教・ジェンダーが複雑に絡み合うなかで生まれた、ひとりの女性による「個」の解放劇であった。
旧華族という格式は、戦後の急激な社会変化のなかで生活の貧窮と精神的な空洞を覆い隠すことができず、名家の看板はもはや安定を保証するものではなくなっていた。
そうした状況下で、M子はカトリックへの改宗と、教会を通じた慈善活動に身を投じることで、自らの新たな「居場所」を模索し、構築していった。その姿は、制度と伝統に揺らぐ戦後日本における新たな女性像の構築にも重なっていた。
世間の報道は二人の関係をスキャンダラスに取り上げたが、そこに描かれたのは「父を求める娘」と「庇護者を演じた老善人」との、現実的で切実な相互依存に過ぎなかったとも言える。
さらに、家出後にM子が築いた福祉事業は、単なる逃避ではなく、血縁や格式から解放された彼女が社会との新たな接点を生み出し、地域との持続的な紐帯を形づくることに成功した証左であった。
敗戦と家制度の崩壊によって生まれた空白を、信仰と奉仕という手段で埋めた元公爵令嬢――。その軌跡は、戦後日本において「身分の終焉」がいかにして「個の再生」へとつながったのかを示す象徴的な物語であり、制度に縛られながらも、そこから飛び出す勇気を選んだひとりの女性の記憶として、今も静かに語り継がれている。
◆参考資料
聲社『声』1957年10月
時事通信社『読売時事』1949年2月号
『実話新聞』1949年1月10日付
『読売新聞』1995年1月7日付
◆戦後の事件