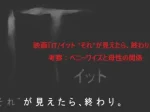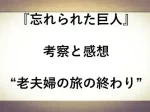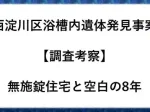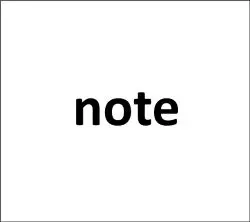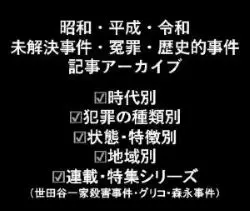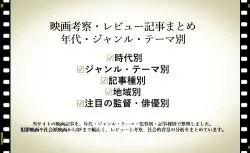要約
映画『チョコレート ドーナツ』(2012年公開)は、1970年代アメリカを舞台に、ゲイカップルとダウン症の少年が共に暮らす姿を描いた実話ベースの作品である。本記事では、作品の概要やあらすじを紹介しながら、血の繋がりにとらわれない家族の絆や、社会から向けられる差別のまなざしについて触れている。観た人それぞれが「家族とは何か」を考えさせられる、温かくも切ない物語である。
家族愛とは、どのようにして生まれるのだろう。血の繋がりが全てという訳ではないし、「自分の子供だから」と語れるほど、単純なものではないはずだ。家族の間に流れる愛情は、時としてドラマチックなものになりうる。
いわゆる「普通」からは少し外れた、一風変わっているけれども確かな愛情で結ばれた家族を描いた映画に『チョコレート ドーナツ』という作品がある。
今回は本作を通して、家族の存在や感情のあり方を見ていきたいと思う。
『チョコレート ドーナツ』の作品概要
『チョコレート ドーナツ』は2012年に公開されたアメリカの映画である。実話をベースとした作品で、ダウン症の少年と、彼を育てようとするゲイカップルを主人公としている。
主役を務めるのは、自身もバイセクシュアルだと公表しているアラン・カミング。ダウン症の少年・マルコを演じたアイザック・レイヴァも、本作がデビュー作ながら、心に残る演技を見せている。
本国のアメリカだけでなく日本でも高い評価を受け、2020年には東山紀之主演で舞台化もされた。
あらすじ
舞台は1970年代のアメリカ――ルディは歌手になる夢と、それに伴う実力を持ちながらも芽が出ず、ゲイバーのショーでダンサーをしていた。そんな日々の中、ルディは店を訪れたポールと惹かれあい、交際することになる。
ある日の朝、隣室から響く大音量の音楽に耐え兼ねたルディは、1人でうずくまるダウン症の少年・マルコと出会う。
母親はまだ帰ってきていない。ルディは検事局で働くポールに助言を求めるが、その返事は芳しくない。母親が麻薬所持で逮捕されたこともあり、マルコは施設に入ることになった。
施設になじめず、家に帰るため脱走するマルコ。ルディとポールは夜道を一人で歩くマルコを保護し、3人で暮らすために奮闘することになる。
家族とはどんな形/存在であるべきなのか
私(筆者)はできる限り、「○○(する)べき」という言葉は使いたくない。強い言葉だし、聞いたり見たりすると焦燥感にかられているような気持ちになるからだ。しかし今回は、あえて苦手なこの言葉を使っていきたい。
家族とは、どんな存在なのだろう。この問いを向けたとき、その答えは大きく分かれることだろう。家族に向ける感情は人それぞれ異なり、「これが正解!」といった答えもないからだ。
本作に登場する、ルディ・ポール・マルコの状況を整理し、3人の関係性を見ていこう。
ルディとポールは同性同士で愛し合うゲイカップルだ。確実に愛し合ってはいるものの、結婚はもちろん、2人の関係性は大っぴらにすることも難しい状態である。1970年代のアメリカは同性愛者に対する差別が酷く、職場や周囲に隠して生きていくことを余儀なくされていたからだ。(検察官であるポールもまた、同性愛者であることがバレて仕事をクビになっている)。
マルコもまた、難しい境遇に置かれている。
彼には一緒に暮らす母がいたものの、その母は親としての役割を果たせてはいない。恋人との時間を優先してマルコを家から追い出し、挙句の果てに麻薬所持で逮捕されてしまう。彼が持つ障害を考えなくても、なかなか厳しい環境だ。唯一の養育者である母がいなくなったマルコは、施設で暮らすことになる。
ルディとポール、それにマルコが家族のような関係を築くきっかけとなったのは、2人が夜道をさまようマルコを保護したことがきっかけだった。2人が正式にマルコの監護者となり、一緒に暮らし始めたのである。
どの段階で、2人がマルコに対し愛情を抱き始めたのかは定かではない。ルディはおそらく、最初は同情心からマルコを引き取ろうと考えたのだろう。しかし、ルディやポールがマルコを見る目は愛情深い家族のそれだ。ホームビデオ風に撮られた3人の生活シーンは、見ているだけで癒されるような素敵なシーンである。
父親と母親と子供。時と場合によってはこれに祖父母も加わるかもしれないが、一般的に「家族」と表現すると、この形が思い浮かぶ。しかし、ルディたちの場合は当てはまらない。ルディがマルコを「息子」と表現するシーンがあるものの、基本的には役割を固定せず、純粋な愛情で繋がった関係である。
この関係を家族と呼ぶかどうか。それは人によって意見が分かれる部分だろう。しかし私は、ルディとポール、そしてマルコの3人は確実に「家族」だったと声を大にして言いたい。マルコの実の母親でさえ近づけない程の、確固たる家族だった。 家族とは、法律や外側からの視線で決められるものではないはずだ。愛情で繋がり、何かあったときに帰ることができる場所が家族なのだと思うからだ。
マイノリティに向けられる感情
明らかな敵意を持った差別の目を向けられたことはあるだろうか。因みに、私はある。「普通」から逸脱することの恐ろしさは、なかなか忘れることができない。
本作は家族の物語であると同時に、差別の物語でもある。そして、ゲイというマイノリティが受け続ける感情を描いた物語でもある。
ルディとポールはゲイであり、1970年代のアメリカ人にとって普通ではない、受け入れがたい存在だった。ゲイであるというだけで公然と侮蔑され、社会的な地位や立場を失いかねない状態だ。
ポールにとって検察官は憧れの職業だった。だからこそ、仕事を失わないために性的指向を隠そうとする。そして、「普通」の人々の差別意識を代表する存在として描かれるのが、ポールの上司である。
ポールの上司は一見ニコニコとした、人の良さそうな男性に見える。しかし、ルディとポールを「異常」と言い放ち、そう言葉にすることにためらいも、疑いも持っていない。彼にとってゲイは悪であり、批判されてしかるべきだと考えているのだろう。つまり、同じ「人間」としてルディとポールを見ていないのだ。
人は無意識的に自分とは異なるものや理解ができないものを恐れ、排斥しようとしてしまう。こうなると、理解し合うための対話は難しい。
ポールの上司の描写はあからさまで非常に分かりやすいが、ルディやポールは常日頃からこうした感情を浴び続けている。マルコの母親がルディを見る目、ポールに好意を寄せていたはずの女性の目。差別意識を隠そうともしない、感情的な表情だ。
本作の舞台となった時代から、そして、本作が制作された時から、それなりの時間が経った。マイノリティの中でもLGBTQに対する意識は大きく様変わりした。しかし、差別意識という感情の本質そのものは同じままだ。おそらく、感情を向ける方向や方法が変化したのだろう。
人間は様々な感情を抱く。差別意識もそうした感情の一つだ。差別意識を抱くことそのものは仕方ないことであるし、なくそうとして完全になくせるものではない。だからこそ、お互いがお互いを尊重して、対等な人間同士として付き合うことが重要になる。性別は関係ない。皆等しく1人の人間なのだ。 マルコの担任の教師は、ルディやポールをマルコの両親として、人間として接していた。彼女のような人が増えて欲しいと思う。
まとめ
名作であるにも関わらず、表に出にくい作品がある。映画『チョコレート ドーナツ』は正にそんな作品だ。見るまでのハードルは高いかもしれないが、一度鑑賞すると、その魅力が体の中に染みわたっていくような、そんな映画作品である。
本作は決してハッピーエンドではない。けれど、人間的な優しさに包まれた作品でもある。「ハッピーじゃないなら」と目を背けるのはたやすいが、それでは本作の優しさや美しさを感じられない。
私はこの記事で差別意識について語ったが、そんな小難しいことは脇に置いてもいい。とりあえず、未見の人に一度鑑賞してみて欲しい作品である。
公式映像資料(YouTube)
文章だけでは伝わらない空気を、映像として確認するための資料として掲載する。
🎥参考映像(出典:シネマトゥデイ公式チャンネル)映画『チョコレートドーナツ』予告編
◆家族・絆について考える映画
◆オススメの記事