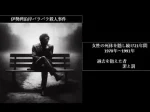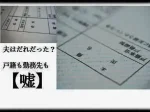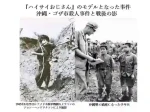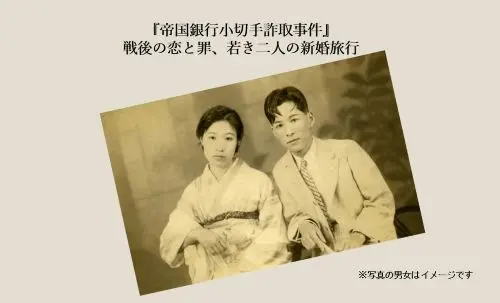
偽造小切手は、まるで恋文のようだった。その一枚が、ふたりの未来を変えてしまった。
終戦からわずか2年――昭和22年。東京はまだ巨大な焼け跡だった。空襲の傷跡が生々しく残り、バラックが肩を寄せ合う街には、人々の逞しい生命力と、しかし同時に、出口の見えない焦燥感が渦巻いていた。
そんな灰色の風景の中で、一枚の「小切手」が、若き男女の運命を、そして「戦後」という時代のひとつの断面を静かに切り取る。これは、罪の物語であると同時に、焼け跡に咲いた束の間の青春譜でもある。
罪を犯したのは、銀行に勤める真面目な若い女性と、薬学を学ぶ19歳の学生。ふたりは小切手を偽造し、逃げるように長野・諏訪へと旅立つ。それは『新婚旅行』と呼ばれた。
これは、実在した詐欺事件にわずかな想像を添えた、戦後という時代の空気を纏う青春の記録である。重たい記録ではない。むしろ、読後にふと微笑みがこぼれるような、そして少し胸が締めつけられるような、そんな小さな物語である。
第1章:帝国銀行、秋の朝に差し出された一枚の小切手
昭和22年9月22日、東京都中央区の『帝国銀行東京支店』。秋の気配の陽光が、煤けた窓を通してわずかに差し込む。そこに、一枚の小切手が提出された。額面40万円、『駿河銀行横須賀支店名義』。当時の大卒初任給が数千円(東京都職員の平均給与は約3500円)だった時代、それは都心に小さな家が買えたかもしれないほどの、天文学的な金額だった。しかし、それは精巧に、だがどこか稚拙さも残して偽造されたものだったという。大胆さと危うさが同居する、若さの証のように。
外では、焼け残ったビルが骸骨のように立ち尽くし、復員兵たちは軍靴を脱ぎ捨てて日常を探していた。闇市では法外な値段で食料が取引され、人々は配給の列に黙々と並ぶ。そんな喧騒の中を、GHQのジープが埃を巻き上げて走り去り、進駐軍兵士の嬌声が銀座裏に響いていた。古い秩序が崩壊し、新しい価値観が混沌の中で生まれようとしていた、そんな時代だった。
第2章:彼女の名前はS、真面目な事務員だった
偽造小切手を窓口に滑り込ませたのは、同支店に勤めるS(23歳)だった。戦中も戦後も、変わらず事務の仕事を続けてきた。勤続8年、誰からも真面目だと評される女性だった。
上司の信頼も厚く、その実直さは誰もが認めるところだったという。だがその日、彼女の表情には、普段の従順さとは違う、微かな決意と、未来へのひそやかな希望の色が浮かんでいたのかもしれない。
彼女はこれまで、何かを「自分のために」選んだことがあっただろうか。戦中は国家のために、戦後は職場と家族のために――。ふと目を閉じたその朝、初めて「自分の人生に賭けてみたい」と思ったのかもしれない。
乏しい配給食糧で作った弁当を風呂敷に包み、彼女は毎朝、瓦礫の残る道を歩いて銀行へ通った。道端で空腹を訴える子供たち、生活に疲れた人々の顔。それらは、彼女の目に焼き付いて離れなかっただろう。この日常から抜け出したいという願いが、彼女を突き動かしたのだろうか――。
第3章:彼の名前はH、薬学生にして「自由」の夢想家
共犯とされたのは、『東京薬学専門学校(現在の東京薬科大学)』に通うH(19歳)だった。
知的な風貌をしており、まだ少年と呼んでもよい年齢だった。
教科書も満足に手に入らない戦後の混乱期にあっても、彼は学問への意欲を失わず、ノートには分子構造の図が几帳面に書き込まれていた。けれども同時に、彼の心は実験室のフラスコよりも、まだ見ぬ「自由」の輝きに強く惹かれていた。
彼が夢見た「自由」とは、単なる金銭的な豊かさだけではなかったはずだ。軍国主義の重苦しい空気から解放され、思想も、生き方も、そして恋愛も、自分の意志で選び取れるという感覚。ラジオから流れる進駐軍のジャズ、街角のカフェで英語混じりの会話に興じる男女。
それらは、旧体制の価値観に縛られてきた若者たちにとって、目映いほどの解放の象徴に映ったことだろう。
彼は、その新しい時代の風を、愛するSとともに吸い込みたかったのだ。
「君と、国境のない世界へ行きたい」──。そんな言葉が、Sへの手紙に綴られていたのかもしれない。彼の胸に描かれた計画は、この「自由」への渇望と、銀行に勤める恋人の存在とによって、少しずつ形を成していった。彼の胸にあった夢想は、ノートに描いた構想から、やがて現実的な「方法」へと姿を変えていった。
Sが扱う帳簿、支店長が席を外す時間、帳場に生まれる一瞬の死角――。それらすべてが、彼の夢と現実とを、静かに接続していった。
この時代、旧来の価値観からの逸脱を、新たな創造や希望と捉える若者は少なくなかった。アプレゲール犯罪といわれた『光クラブ事件』に代表されるように、彼らは既存の秩序に異議を唱え、自分たちの手で新しい世界を築こうとした。本事件もまた、そうした戦後初期の若者たちの精神性を映し出しているのかもしれない。
第4章:ふたりで描いた四十万円の幻想
事件の構図は、ある意味では単純だった。K支店長の不在を狙い、SはHの指示どおりに小切手を偽造したとされる。そして9月22日、その偽造小切手が、ついに行使された。
現金15万円と銀行小切手25万円分を手にした二人は、その日のうちに東京を離れた。目指したのは信州・諏訪だった。それは、彼らにとってのささやかな「新婚旅行」だった。
中央線を乗り継いでの旅だっただろうか。東京から大阪まで15時間を要した時代だ。石炭の煙が立ち込める汽車は、まだ戦争の傷跡が残る風景の中を、ゆっくりと走っていた。
車窓からは、復興の槌音と、すすきの原を渡る秋風。車内でふたりは、何を語り合ったのだろうか。
宿帳に偽名を記すSの手は、震えてはいなかったか。Hは、その様子をどんな笑顔で見守っていたのだろう。記録は残っていない。だが、諏訪湖の静かな水面だけが、彼らの束の間の解放を知っていたはずだ。
宿泊先の夜のなかでHが囁いたという言葉は、若く未熟な、しかし切実な愛の誓いだったのかもしれない。
戦火をくぐり抜け、日々の労働と生活苦に追われてきた二人にとって、自分たちのためだけに時間とお金を使うという経験は、奇跡のようだっただろう。それは、罪によって手に入れた、歪んだ形ではあったが、彼らが夢見た「未来」の予行演習だったのかもしれない。
第5章:一万円のカメラ、旅行、五万円、そして上板橋の終幕
諏訪での短い滞在を終え、ふたりは再び東京へ戻った。Hは現金の一部で、1万円を超えるカメラを購入し、さらに5万円を知人に預けた。それは新しい生活への準備だったのかもしれないし、ただの若者らしい衝動買いだったのかもしれない。
けれど、ふたりの夢は長くは続かなかった。帝国銀行からの通報を受けた警視庁の捜査網は、迅速に動き出した。そして9月23日、警視庁日本橋署の手によって、Hは上板橋の下宿先で逮捕された。
部屋には、買ったばかりのカメラと、まだ一度も使われることのなかったフィルムが残されていただろう。そのレンズが捉えようとしていたのは、どんな未来だったのだろうか。現像されることのなかった未来のネガフィルムのように、彼らの「自由」への逃避行は唐突に終わりを告げた。
40万円の使い道――旅行に出かけ、カメラを購入し、現金の一部を知人に託した。預けた金には、やがて訪れる発覚を見越した、隠匿の意図があったのかもしれない。けれども彼らの行動は、罪の重さとは裏腹に、どこか無邪気で、「戦後的な消費」とも呼べる性質を帯びていた。
たとえ刹那的であっても、それは自分たちの「現在」を精いっぱい生きようとする姿のあらわれだった。そして、それは戦前・戦中の抑圧からようやく解き放たれた若者たちが、自分自身を取り戻そうとして選び取った、ささやかだが確かな自由のかたちだったのではないだろうか。
カメラは、ふたりが手にした唯一の「資産」だった。それは過去を記録するためのものではなく、これからの未来を写し出すための、さながら魔法の箱だった。だが結局、そのシャッターが切られることはなく、未来は現像されなかった。旅の切符は燃え尽き、小切手は紙屑に還った。そして残されたのは、ただ一枚の夢のネガフィルムだけだった。
第6章:罪と呼ばれた青春、記録に残らぬその後
SとHが法的にどのように裁かれたのか、詳細な記録は見つかっていない。起訴されたのか、どのような判決が下ったのかも不明である。ただ、「結婚を約束していた」「新婚旅行と称して逃避行した」という断片的な情報だけが、まるで昭和の片隅に置かれた未完成の恋愛小説のように、記憶されている。
これは、まぎれもない「罪」だった。銀行を欺き、社会の秩序を破った行為に違いない。だが、その罪を生んだのは、彼らの胸のうちだけではなかった。焼け跡に満ちた空気の重さ、若さゆえの未熟さ、そして何より、たったふたりで未来を築こうとした切実な願い――。それらすべてが、この小さな過ちの背後に静かに横たわっていた。
「ふたりで生きる」――その願いは、国家やイデオロギーといった大きな物語が音を立てて崩れ落ちたあの時代において、彼らがたどり着いた唯一の希望だったのかもしれない。それは高らかに語る理想ではなく、瓦礫の上にぽつんと灯る、小さな火のような希望だった。
罪と呼ばれたその行為の奥には、飢えがあり、焦燥があり、そして若者なりの想いがあったのだろう。
時代が崩れ、善悪の輪郭すらあいまいになるなかで、彼らが信じようとしたものは、紙幣でも名誉でもなかった。
ただ、「ふたりで生きてゆきたい」という、言葉にすればあまりに儚く、しかし胸の奥では誰よりも真剣だった、ささやかな未来だったのだ。
19歳と23歳の犯罪――誰が、この時代の空気も知らずに、彼らに正義の石を投げられるだろう。生きること自体にどこか罪の匂いがつきまとい、しかし同時に、生きていくこと自体が肯定されていたような、そんな時代の若者たちだった。彼らの罪を断じることは、その時代の空気を忘れることであり、戦後という地平を知らぬ者の冷たさに似ている。
そして何より、彼らは逃げなかった。逮捕され、社会の眼差しに晒され、それでも逃げずに受け止めた。そこにこそ、青春の名を与える理由があるのかもしれない。 彼らはまだ若かった。そして、戦後の日本もまた、まだ若かったのだ。もしもあなたがこの時代を生きていたなら、彼らと同じ小さな過ちを、同じような愛を、選ばなかったと本当に言い切れるだろうか。
7章:罪を越えて、人生を歩くふたりの影
罪を犯した若者たちを責めるのは容易い。だが、あの時代を生きた誰もが、少しの過ちと、少しの愛に救いを求めていた。ふたりは罪を償い、新しい名前で、どこか郊外の小さな家に暮らし、子どもを育て、笑い、老いていったかもしれない。
やがて時代は、高度経済成長の光の中を駆け抜けていった。焼け跡はビルに変わり、闇市は商店街となり、人々は豊かさのなかで、“戦後”という言葉さえ忘れはじめていた。
ふたりが暮らしたかもしれない郊外の家や団地もまた、復興の象徴でありながら、かつての過ちや自由への渇望を、静かに包み隠していったのかもしれない。
そして、夕暮れのベランダや茶の間の棚には、古びたカメラがひっそりと飾られていたかもしれない。そのカメラで撮られた家族写真のアルバムには、戦後を生きた彼らだけが知る「真実」が、微笑みの影にそっと忍んでいたのではないか。
若い頃の罪を抱えながら、それでも愛し合い続けること。その背中を、子供たちは知らずに見つめて育っていったのかもしれない。自由とは、過去を赦し、誰かと明日を築く力のことだった。
人生とは、ときに小さな過ちを抱いたまま、それでも愛し合うことを許された、やわらかな物語なのである。
彼らがその後、どのような人生を歩んだのか、私たちは知る由もない。罪を償い、社会の片隅で過去を秘めて静かに生きたのだろうか。あるいは、若き日の過ちは彼らを分かち、それぞれ別の道を歩んだのだろうか。確かなのは、彼らの物語が、焼け跡から立ち上がろうとしていた日本の、無数の名もなき青春のひとつであったということだ。
私たちは、この小さな事件の中に、何を読み取るべきだろうか。単なる犯罪記録か、時代の犠牲者の物語か、それとも、どんな状況下でも「自由」と「愛」を求めてしまう人間の、普遍的な姿だろうか――。
あとがき
本記事は、1947年に実際に発生した事件に、わずかな想像を交え、物語として再構成した記録です。この事件は、かつて『カストリ新聞』と呼ばれた紙面の、ほんの片隅に載った小さな記事でした。これは罪の記録ではなく、ひとつの『時代』が残した呼吸を伝える、小さな記憶にすぎません。
たった一枚の「偽造小切手」に纏わる事件が、ふたりの青春を静かに語り出しました。ここに綴られた物語が、唯一の正解だとは思いません。
けれど、読者ひとりひとりが、この若きふたりの「戦後」に思いを馳せ、私たちが生きてきた時代の原風景に、ほんの少しでも触れていただけたなら、それこそが、この記録の願いであり、目的なのです。
忘れられた事件をひとつの「記憶」として綴り、「物語」として再構築することが、現在を生きる私たちの想像力の「火種」となるなら、これに勝る喜びはありません。また、この時代の若者たちが追い求めた『自由』については、『光クラブ事件』の記事でも詳しく描いています。
◆参考資料
『探偵新聞』昭和22年9月号
◆戦後の事件



























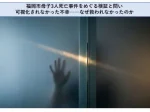


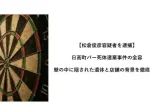
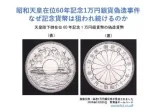
のアイキャッチ画像_edited-150x112.webp)