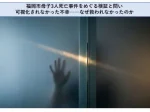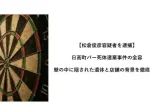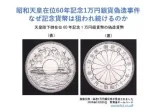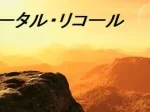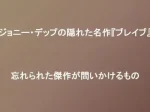1998年に公開された映画『セイヴィア(Savior)』は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争(1992年-1995年)を舞台にした戦争映画であり、民族浄化という現代史における痛ましい出来事を描いた作品である。本作は、戦争、民族浄化の残酷さと個人の倫理的葛藤を描くことで、観客に『戦争の本質』と『人間』を問いかける。
本記事では、映画の概要、あらすじ、背景となるボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の歴史的文脈を詳細に説明するとともに、主人公ジョシュアの変遷を分析する。特に、彼が憎しみと復讐の連鎖から抜け出す過程、そしてラストシーンから考察できる彼の『三度目の人生』について掘り下げる。また、映画の持つ哲学的テーマや戦争映画としての意義についても考察し、作品が観客に与える影響について論じていこう。
映画概要
映画『セイヴィア』は、ユーゴスラビア出身の監督、ピーター・アントニエヴィッチ(Predrag Antonijević)が監督を務め、ハリウッドの実力派俳優デニス・クエイドが主人公ジョシュア・ローズ(後にギイ)を演じた。脚本はロバート・オアが手掛け、戦争の現実を生々しく描くストーリーが評価された。また、オリバー・ストーンが製作総指揮として関わっており、彼のリアリズムと政治的視点が本作にも影響を与えている。
映画は国際的な映画祭で高く評価され、特に戦争映画としてのリアリズムが称賛され、ヨーロッパでは戦争の悲劇を描いた作品として一定の評価を受けている。特にボスニアや旧ユーゴスラビア出身の観客からは、そのリアリズムと歴史的正確性が高く評価された。
あらすじ
映画は、元アメリカ兵であり、現在は外交官としてフランスに駐在していたジョシュア・ローズが、イスラム過激派による爆弾テロで妻子を失う場面から始まる。復讐に燃えた彼は、仲間とともにイスラム教徒のモスクを襲撃し、無関係の人々を殺害してしまう。この事件により、彼は逮捕を逃れるためにアメリカを離れ、『ギイ・ヴァンデンバーグ』と名乗り、フランス外人部隊に入隊する。
やがて、彼はボスニア・ヘルツェゴビナの紛争地帯で傭兵として活動することとなる。彼の任務は、セルビア人勢力の一員として、イスラム教徒やクロアチア人との戦闘に従事することであった。
ある日、セルビア人女性ヴェラは、停戦中の捕虜交換によって解放された。紛争中、双方の勢力は交渉によって捕虜交換を行うことがあり、彼女もその一環として解放されたのだった。
しかし、解放直後に彼女は新たな危機に直面する。ジョシュア(以下、ギイと記す)が共に行動していたセルビア兵のゴーランが、ヴェラを暴行する。彼女は敵兵との間にできた子を身ごもっており、それを知ったゴーランは彼女を嘲笑し、侮辱しながら腹部に暴行を加え、殺害を試みる。その行動の背景には、捕虜として屈辱を受けた敵方の女性に対する憎悪や、戦争がもたらす非人道的な心理状態があったと考えられる。
ギイは、その場でゴーランを殺害することでヴェラを救う。しかし、この行為はセルビア人部隊に対する裏切りと見なされ、彼自身も命を狙われる立場となる。ギイはヴェラと共に逃亡するが、戦場の現実は過酷であり、安全な逃亡路はなかった。
ギイはヴェラと彼女の子供を守るために奔走するが、戦争の過酷な現実の中で逃亡は容易ではない。ヴェラは当初、生まれたばかりの子を拒絶し、母乳を与えず、オムツの交換もしなかった。
彼女にとって、この子は敵兵による暴行の結果生まれた存在であり、『望まない子』の証とも言える存在だった。また、ヴェラの家族も彼女とその子を受け入れず、関係を断つ。ヴェラは一家の恥と見なされ、家族は彼女が民族としての誇りを奪われたと考えているのだろう。
この出来事は、『民族浄化』が単なる身体的な暴力ではなく、被害者を共同体から切り離し、帰属意識そのものを奪うことで、社会的・心理的にも排除する手段として機能することを示している。
しかし、逃亡の旅を続ける中で、ヴェラの中に母親としての感情が徐々に芽生え始める。彼女は子供を拒絶し続けるのではなく、少しずつ受け入れるようになり、最終的には母親としての愛情を抱くようになる。この変化は、戦争の憎しみの中でも、動物的な本能としての母性が自然と芽生えることを象徴している。ヴェラが命を落とす前に歌う子守歌が印象的だ。
ギイは孤児となった赤ん坊を抱え、生まれたばかりの子のため安全な場所(赤十字“ICRC”が関与すると思われる『人道支援施設』)に向かう。彼の行動は単なる自己満足や贖罪ではなく、戦争に巻き込まれた無実の人々への誠実な対応であり、思想・信条、立場を越え、他者と関わる中で善を求める人間の本能であり、それが彼自身の精神的な変化を促す契機となる。
そう、『本能』と『理性』は、時に『復讐』を生むが、『復讐の連鎖』を終わらせることもできるのだ。
映画の背景:ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争と民族浄化
映画『セイヴィア』の背景には、1990年代に旧ユーゴスラビアで起こったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争がある。この戦争は、セルビア人、クロアチア人、ボスニア・ヘルツェゴビナのイスラム教徒(ボシュニャク人)という三つの民族が入り乱れた紛争であり、特にセルビア人勢力による『民族浄化』が問題となった。
ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、特定の民族を排除するための大量殺戮や強制収容が行われ、国際社会から非難を浴びた。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(ICTY)において、『民族浄化』の一環として敵性民族の女性に対する組織的な性的暴行が戦争犯罪として認定された。
民族浄化(Ethnic Cleansing)とジェノサイド(Genocide)は異なるが、どちらも歴史上繰り返されてきた。『民族浄化』は特定の民族を地域から排除することを目的とし、強制移住や追放を主な手段とする。一方、ジェノサイドは、その民族自体の根絶を目指し、殺害や文化的抹消を含むより徹底的な破壊行為を伴う。
これらの行為は、歴史的に様々な地域で繰り返されてきた。それは、ナチス・ドイツによるホロコースト(ユダヤ人やロマへの迫害・大量虐殺)、ウスタシャ政権によるセルビア人、ユダヤ人、ロマに対する大量虐殺、ルーマニアの鉄衛団によるユダヤ人迫害とポグロム、そして16世紀以降の新大陸における先住民虐殺と強制移住 である。
また、女性に対する性暴力は、女性を精神的・肉体的に破壊するだけでなく、民族の継続性を断つことを目的とした戦術であり、多くの犠牲者が長期にわたる心理的・社会的苦痛を強いられる結果となった。
ヴェラもその犠牲者の一人であり、収容所で暴行され、敵兵の子を身ごもることを強いられた。このようにして生まれた子供は、両民族から疎外され、戦後社会においても困難な立場に置かれることが多かった。
それだけでなく、母親であるヴェラ自身もまた、民族の敵として見なされ、味方であるはずの自民族から憎悪の対象となることがあった。戦争における性的暴行は単なる身体的暴力ではなく、女性の精神的な崩壊をも狙ったものであり、多くの被害者が命を懸けて抵抗できなかった自分を責め、深い罪悪感に苦しんでいた。ヴェラのように、暴行を拒絶できなかったことで自身を責め続ける女性も少なくなかったのである。 映画は、戦争に巻き込まれた個々の人間の視点から、この非人道的な現実を描き出している。また、映画が描くボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の側面は、現代の戦争犯罪やジェノサイドに対する警鐘として鳴り響いている。
戦争と人間性の回復
戦争は人間を変え、時に極限の状況下で本来の倫理観を失わせる。しかし、映画『セイヴィア』は、戦争のただ中にありながらも、個人が良心を取り戻し、人間性を回復する可能性があることを暗示している。
ジョシュア(ギイ)は、戦地において子どもを射殺するという極限の選択を経験する。その行為は彼の心に深い傷を残した。かつて家族を失った悲しみと怒りから、復讐と戦闘に身を投じた彼は、戦場での行為が自身の人間性を蝕んでいくことに気づいていく。その苦しみの中で彼はヴェラと出会い、彼女の境遇を通じて自身の行為と向き合うことを余儀なくされる。
特に印象的なのは、ヴェラとの会話の中で、ジョシュア(ギイ)が自身の偽名を告白する場面である。ヴェラに「なぜ名前を変えたのか」と問われた彼は、「ジョシュアは色々なことをした」と答える。この言葉には、彼が過去の行為に対して抱く深い悔恨が込められている。
彼は、自らが犯した暴力の連鎖に苦しんでいた。しかし、ヴェラとの出会いは、彼が単に過去を忘れるのではなく、それと向き合いながら贖罪の道を歩む契機となった。
ヴェラを助けた瞬間、それは単なる同情や一時的な感情ではなく、彼自身がかつて持っていた正義感や人間性を再発見する契機となった。彼の行動は、戦争という極限状態にあっても、人は選択によって自らを変えることができることを我々に教えてくれるだろう。
主人公の二度目の人生と三度目の人生
ジョシュアは、妻子を失い、復讐のためにモスクを襲撃した後、アメリカでの居場所を失い、フランス外人部隊に入ることで『二度目の人生』を生きた。これは、新たなアイデンティティを獲得するための選択であり、自らの罪を覆い隠す手段でもあった。しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の最前線で彼が直面した現実は、単なる逃避では済まされないものだった。ヴェラを救ったことで、彼は新たな決断を迫られることになる。
キリスト教には『セカンドチャンス(Second Chance)』という概念があり、これは人が罪を悔い改め、新たな道を歩む機会を与えられるという考え方である。この概念は、新約聖書の『ルカの福音書』15章に登場する『放蕩息子の物語』に象徴される。父親が過去に罪を犯した息子を無条件で受け入れるように、神の慈悲のもとで人は新たな人生を生きることができるとされる。これは、罪を犯した者が悔い改め、新たな人生を歩む機会を与えられるという考え方である。
ジョシュア(ギイ)の『二度目の人生』は、彼が過去の罪から逃れるために選んだ道であり、受動的な選択だった。しかし、『三度目の人生』は異なる。これは彼自身が主体的に選んだ新たな生き方であり、贖罪ではなく、未来へ向けた意志の表れである。放蕩息子は、神に『失われていたが見いだされた』たが、ジョシュア(ギイ)の『三度目の人生』は、自ら見出すであろう。。
映画のラストシーンでは、彼はヴェラの子供を抱えながら、戦場から立ち去る姿が描かれる。これは、彼が『三度目の人生』へと踏み出したことを象徴している。この新たな人生において、彼は一人ではなかった。戦争で息子と孫を失い、もはや「失うものは何もない」と語る老夫婦は、ジョシュアとヴェラを匿い、協力した。彼らにとって、助けることは自己犠牲ではなく、人としての尊厳を守る行為だった。また、終盤で登場する女性も、彼の逃亡を助けるなど、彼の選択を支える『善意』と『協力』があった。
『失うものは何もない』者が恐れを抱かずに『善』を行う一方で、ジョシュア(ギイ)は『守るべきもの(子ども)』を手にしたことで、生きることに執着するようになる。彼は新たに手にした命の重みを理解し、それを失うことを恐れるようになった。過去の彼であれば、死は解放だったかもしれない。しかし、子どもを抱いた彼は、もはや自殺を選ばない。彼は生き抜くことを決意し、それが彼にとっての『第三の人生』となったのである。
彼は最後まで生き抜く道を選んだ。それは、彼の目にうっすら浮かぶ涙が象徴している。その涙は、『三度目の人生』を歩む決意を固めた証であり、戦場の暴力に染まった自分を捨て、人間性を取り戻したことを示している。
まとめ
映画『セイヴィア』は、戦争映画としての迫真性だけでなく、個人の倫理的葛藤と変化を描いた作品である。本作は、戦争の悲惨さを超えた『贖罪』と『人間性の回復』というテーマを提示し、観る者に深い問いを投げかける。
本作が描くのは、戦場という極限状態の中での人間の選択である。主人公ジョシュア(ギイ)は、復讐の連鎖に取り込まれながらも、ヴェラや彼女の子供との関わりを通じて、自らの人間性を取り戻していく。民族浄化という狂気の中で、彼は復讐ではなく『守ること』を選び、戦争によって奪われたものを再び取り戻そうとする。
また、映画は『民族浄化』という歴史的悲劇を背景に、戦争における女性への暴力や、戦後社会における被害者の孤立と苦しみをリアルに描き出している。ヴェラが子供を拒絶しながらも、次第に母性を取り戻していく姿は、人間の本能としての愛情の力を象徴する。
さらに、作品は『本能』と『理性』の正の側面と負の側面という対立軸を通じて、戦争と人間性の関係を問う。復讐を生むのも『本能』なら、復讐の連鎖を断ち切るのもまた『本能』である。そして、『理性』は暴力を正当化することもできるが、最後には善を選択する道を照らす光となる。
映画『セイヴィア』は、単なる戦争映画ではなく、戦争の本質と人間の選択を問う哲学的な作品である。暴力と贖罪、復讐と和解、人間性と非人間性というテーマの中で、観る者は『人間とは何か』という根源的な問いと向き合うことになるだろう。
◆戦争・軍隊・軍人に関係する映画考察・解説シリーズ