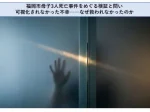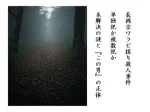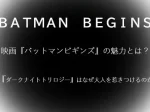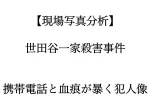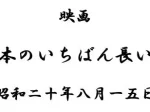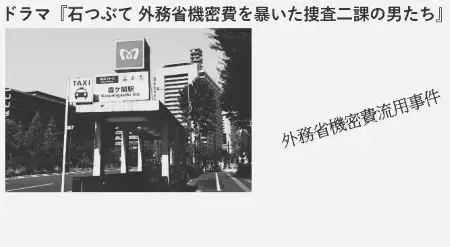
国家の中枢・外務省――。その裏金の存在を暴いた刑事たちの執念と葛藤を描いたのが、2017年に放送されたドラマ『石つぶて~外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち~』である。
本作は、実際に発生した『外務省機密費流用事件』を基に、地方警察である警視庁捜査二課が、国家中枢の政治家や外務省のエリート官僚に戦いを挑む姿を描いた異色の刑事ドラマである。
この事件は、単なる汚職や個人の不正ではない。領収書不要で監査も免除される「外交機密費」という国家の特権的な資金が、組織ぐるみで私的に流用されていた実態が明らかになった。事件の背後には、官僚機構の腐敗、政治との癒着、そして司法・警察組織の構造的な問題が複雑に絡み合っていた。
一方で、本事件が起きた1999年から2002年にかけて、日本の警察組織もまた変革期にあった。取調べの可視化、女性刑事の登用が進むなかで、従来の捜査手法や刑事像が変わりつつあった。昭和の刑事たちが貫いてきた「無骨で寡黙、生活を捨てて捜査に没頭する刑事像」は、過去のものになりつつあった。
本記事では、『外務省機密費流用事件』の実態を整理するとともに、『石つぶて』が描いた捜査二課の戦いを振り返る。そして、本事件が日本の警察、司法、政治にどのような影響を与えたのかを考察する。
「国益」の名の下で隠蔽されてきた裏金の真相とは何だったのか。警察組織の変革期において、刑事たちはいかに戦ったのか。そして、国家権力に挑んだ捜査の行方は——事件の核心に迫る。
ドラマ『石つぶて』と外務省機密費流用事件の真相—実録刑事ドラマの核心に迫る
この記事には、ドラマ『石つぶて〜外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち〜』の内容に関する記述が含まれています。
2017年11月より放送された全8話のドラマ『石つぶて〜外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち〜』は、実際の『外務省機密費流用事件』を基にした刑事ドラマである。本作は、国家機関の不正に挑んだ捜査二課の刑事たちの執念を描き、従来の刑事ドラマとは一線を画す異色の作品となっている。
原作は、元読売新聞の警視庁担当記者・清武英利氏(1950年生)のノンフィクション『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』(講談社、2017年)。キャストには佐藤浩市、江口洋介、北村一輝、萩原聖人、佐野史郎などが名を連ねる。
刑事ドラマでは一般的に、殺人事件を扱う「捜査一課」が主役となることが多いが、本作は知能犯罪や汚職事件を専門とする「捜査第二課」に焦点を当てている。知能犯捜査に特化した警視庁捜査二課の刑事たちが、外務省という国家の中枢に潜む不正を追及する姿を描き、従来の刑事ドラマの枠組みを覆す内容となっている。
本記事では、ドラマ『石つぶて〜外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち〜』の魅力を分析するとともに、実際に発生した『外務省機密費流用事件』の概要を解説する。
なお、原作では登場人物は実名で描かれているが、ドラマ版では架空の名称が用いられている。本記事においても、『私とキャリアが外務省を腐らせました 汚れ仕事ザンゲ録』(著:小林祐武氏)に基づく場合を除き、ドラマ版の名称を使用する。
※『外務省機密費事件』関係者の詳細は、原作のノンフィクション『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』をお読みください。
ドラマ『石つぶて』のあらすじと外務省機密費流用事件—警視庁捜査二課の闘い
物語は、1997年3月に発覚した「外務省エリート高官2億円着服疑惑」の隠蔽から始まる。外務省が年間50億円を計上する機密費の一部を、複数の高官が私的に流用していた疑惑が浮上したが、「国益」を名目とする箝口令により、事件は不問とされた。
それから2年後の1999年7月、警視庁捜査第二課は、贈収賄や詐欺、業務上横領を担当する「ナンバー」(第四・第五・第六知能犯)において、大手証券会社の強制捜査を実施し、支店幹部数名を逮捕した。しかし、その裏で、担当刑事の収賄(加重収賄)疑惑が発覚した。この一件を機に、組織内部の出世競争、嫉妬、不信が顕在化し、捜査二課特有の閉鎖的な体質が露わになった。
一方、警視庁捜査第二課 第一知能犯情報係(通称「情報」)の主任・木崎睦人は、汚職や談合の情報を収集していた。彼は「保秘」(情報の秘匿)を徹底し、慎重な情報収集を行うが、その手法は同僚から「偏屈」と評されていた。
その頃、刑事部捜査第四課(後の組織犯罪対策部第四課)出身の斎見晃明警部補(後に警部)が、捜査第二課「情報」の係長に任命された。彼は警察内部の改革派であり、強引な取り調べや暴力的手法に問題意識を持っていたが、旧来の捜査手法を重んじる木崎や、強硬な姿勢を示すナンバーの刑事たちと対立した。
木崎は、情報源の一人である元民主自由党総務会長・溝口恭輔を介し、元総理秘書の菱岡博文と接触した。菱岡の証言から、外務省のノンキャリア官僚の中にキャリア官僚以上の贅沢な生活を送る者がいるとの情報を得た。そして、外務省の「三悪人」の一人である西欧局第一課課長補佐・秋村篤郎(モデル:小林祐武氏)を捜査対象とした。
木崎は『捜査関係事項照会書』を活用し、秋村の生活口座を詳細に調べ、さらに、真瀬和則(要人海外訪問支援室長)の資金の流れを追うため、銀行口座、宅配履歴、住民票、戸籍情報、元愛人の証言を基にした裏付け捜査を進めた。
最終的に、木崎は1億7,000万円の隠し口座を突き止めた。これは単なる役人と業者の贈収賄事件ではなく、国家の機密資金「官房機密費」にまで及ぶ大規模な汚職事件であると判断された。木崎と斎見は、互いに衝突しながらも次第に認め合い、捜査第二課長・東田将之の指揮のもと特別捜査班を結成した。警視庁捜査第二課は、霞が関のエリート官僚たちに対する捜査に本格的に乗り出した。
木崎たちの捜査は、外務省のプール金(裏金)、国家の極秘予算『官房機密費』の捻出方法、キャリア官僚とノンキャリアの権力構造、官僚と政治家の癒着、そして中央省庁と警視庁の関係性を明らかにすることを目的としていた。1997年3月に隠蔽された「外務省エリート高官2億円着服疑惑」と同様の結末を迎えるのか、それとも捜査の手が外務省キャリア官僚や政治家にまで及ぶのかが問われることとなった。
本作は、実話に基づいた刑事ドラマとして、国家権力の不正とそれを暴こうとする刑事たちの戦いを描いている。
捜査第二課の刑事・木崎睦人—外務省機密費事件の核心に迫る
木崎睦人は1945年生まれである。警察官となった理由について、「食べるためだった」と真瀬和則に語っている。要人海外訪問支援室長である真瀬が外務省に入省したのは1968年。同年、派出所勤務だった木崎は、12月10日に発生した三億円事件の犯人を自らの手で逮捕したいと考えていた。
しかし、長年にわたり捜査第二課に身を置いた彼が直面したのは、それをはるかに上回る「10億円規模の事件」であった。木崎は「10億円だ」と軽口を叩きながらも、真瀬の内面を探ろうとする。
これは、昭和という激動と苦難の時代を生きた者同士の対峙である。「故郷に錦を飾りたい」「親の自慢になりたい」といった価値観が共有されていた時代、二人はそれぞれの立場で組織に尽くしてきた。真瀬はキャリアと外務省組織を守るために沈黙し、木崎は「公とは国民のものである」という信念のもと、役人の不正を追及する。対立しながらも、根底にある精神は共通していた。
木崎睦人にとって、刑事とは単なる職業ではなく、実存そのものである。酒も博打もやらず、朝から夜遅くまで捜査に明け暮れる。昼は捜査先の公園でパンをかじり、夜は立ち食い蕎麦を啜る。家族はおそらくおらず、趣味もない。彼の人生は刑事という役割に完全に捧げられていた。「仕事と生活の調和」といった概念が語られる以前の時代に育ち、職場を居場所とすることを選んだ。それが、木崎睦人である。
外務省機密費流用事件の概要—警視庁捜査二課の追及と国家の不正
2001年1月1日、21世紀の幕開けとともに、読売新聞は特大の元日スクープを報じた。記事の内容は、警視庁捜査第二課が外務省幹部職員を「外交機密費」流用の疑いで捜査しているというものだった。
外務省幹部、「外交機密費」流用か 自己口座に1億5000万円 警視庁が捜査 首相の外国訪問の際に支出される「外交機密費」を扱う外務省大臣官房の幹部(55)が、自分の銀行口座に一億五千万円もの資金をプールしていることが三十一日、読売新聞社の調べでわかった。問題の口座には、約五年にわたり、一回当たり百数十万-数百万円の入金が月数回のペースで繰り返されており、最も多い時には二億円の残高があった。警視庁捜査二課は、外交機密費の一部が流用された疑いがあるとみて、口座開設の事情を知る関係者の聴取に踏み切るなど捜査を始めた。 この幹部は一九九三年から九九年まで、首相が外国を訪問する際の日程調整などを担当する「要人外国訪問支援室」の室長を務めていた。 複数の同省関係者によると、室長は、首相の外国滞在時のホテル代や専用電話敷設代など必要経費のほか、相手国首脳への贈答品代や接待費など、外交機密費全般を一人で扱っており、年数回-十数回の外国訪問や事前の下見出張の度に、「臨時の出費に対応する」などの名目で一回数百万円の現金を管理する立場にあった。 問題の口座は定期預金口座で、この幹部が室長に就任した後の九四年に都内の銀行の支店に開設された。捜査二課が調べたところ、その直後から、同じ支店の本人名義の普通預金口座に、一か月に数回のペースで一回当たり百数十万-数百万円の入金が現金であり、ほぼ同額が定期預金口座に振り替えられていた。 一回に一千万円を超える入金も数回確認されており、九九年末時点の残高は約二億円にも上っていた。現金は幹部が自分で銀行の窓口に持ち込んでおり、九九年秋に別のポストに異動した直後から入金は途絶えている。 幹部には給与以外に収入はほとんどないことから、捜査二課は、幹部が外交機密費の一部を流用し、自分名義の口座に入金していた疑いがあるとみて関係者から事情聴取を続けている。 一方、幹部は、読売新聞社の取材に、「機密費を流用した事実はない」と疑惑を否定している。
読売新聞 2001年1月1日付
以下の図表は、外務省機密費流用事件の経緯—発覚から捜査、裁判までの時系列
| 2001年1月1日 | ノンキャリアM元要人外国訪問室長の機密費流用疑惑を読売新聞が報道。 |
| 2001年3月10日 | 警視庁は首相外遊の際の宿泊費を水増しし、官房機密費約4,200万円を詐取した容疑でM元室長を逮捕。 その後、「詐欺罪」で起訴された。立件された総額は5億円以上。 |
| 2001年4月26日 | 第一次小泉純一郎内閣発足。田中真紀子氏が外務大臣就任。 |
| 2001年7月16日 | 前年の九州・沖縄サミットに係る約2,200万円詐取容疑で小林祐武氏元経済産業局総務参事官室課長補佐らが逮捕される。 |
| 2001年7月26日 | 外務省はデンバー総領事を不正経理により約1,000万円(約8万1,000米ドル)流用したとし、懲戒免職にする。 |
| 2001年9月6日 | 警視庁はA欧州局西欧第一課課長補佐を逮捕。 逮捕の容疑は95年のAPEC大阪会議の会場費約4億2,300円の水増し請求による詐取の容疑で逮捕。 |
| 2001年11月30日 | 田中真紀子外相がプール金問題の最終報告を発表。 |
| 2002年3月 | 東京地裁はM 元要人外国訪問室長に懲役懲役7年6月の判決を言い渡す。(東京地裁の判決が確定判決) |
| 2002年5月 | 小林祐武氏に懲役2年6月、執行猶予5年の有罪判決。 |
外務省機密費流用事件と内閣官房機密費—隠された国家の資金構造
霞が関のエリート集団である外務省は、独自の採用試験制度を持つ特殊な官庁である。2001年まで、外務省への入省は「外務公務員採用1種試験」により選抜され、合格者がキャリア官僚として採用されていた。
外交機密に守られた外務省官僚や官邸、政治家たちは、それぞれが個人の保身、省益の維持、外交上の秘密の保持、国益の擁護を理由に、『外務省機密費流用事件』の捜査拡大を抑え込もうとした。
事件の核心には、政府の最重要機密の一つである「裏の内閣官房機密費」の存在があった。その捻出方法として、国庫から外務省を含む各省庁へ支出された外交機密費が、外務省からの上納金として総理官邸に戻り、裏金としてプールされていた可能性が指摘されている。その使途や、関与した官僚・政治家の詳細、特に外務省内で「ドン」と呼ばれる高官と真瀬和則との関係は明らかにされなかった。結果として、真瀬の罪名は「業務上横領」ではなく「詐欺罪」となり、ノンキャリア官僚・真瀬の個人的犯罪として処理された。
実際に『外務省機密費流用事件』で立件されたのは、詐欺罪に問われたM元室長と小林祐武氏である。M元室長の捜査により、多くのキャリア官僚が懲戒処分を受けたが、M元室長からキャリア官僚や政治家への金品の流れ(贈収賄の疑い)は解明されず、全容は不透明なままとなった。ドラマ『石つぶて~外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち~』では、この事件が多くの疑惑を残したまま終結した様子が描かれている。
なお、外務省から官邸への外交機密費の上納問題は、2010年の政権交代(自民党→民主党)を機に、政府が初めてその「存在」を認めた。しかし、その使途については現在も公開されていない(参考:外交機密費上納の「闇」民主が使途公表NGの理由 JCASTニュース2010年2月9日配信)。
以下は、岡田克也元外務大臣の「外交機密費(答弁では「外務省の報償費」と表現されている)」国会答弁の一部である。
今までの経緯等を改めて確認したところ、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことが判明したということで、質問主意書の答弁になりました。
第174回国会 衆議院 予算委員会 第10号 平成22年2月12日 外務大臣 岡田克也
昭和刑事の魂と捜査二課—変わる警察組織の在り方
ドラマ『石つぶて』の副題は『外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち』である。その名のとおり、木崎を筆頭とする警視庁捜査二課の組織は、典型的な男性社会であった。「情報」に所属する刑事たちもまた、その例外ではない。
そんななか、「情報」で唯一の女性刑事である矢倉かすみの言葉が印象的である。「これまで女性刑事が立件した『サンズイ』(汚職事件)はない。女性が独自で掴んだ犯罪情報もない」という発言は、当時の警察組織における女性刑事の立場を端的に表している。
事件後、外務省キャリアと昵懇の関係にあった警察キャリア(刑事部長、警備部長など)の意向を反映したとされる「報復人事」が行われた。木崎と矢倉かすみはナンバー(第四・第五・第六知能犯)へ異動となり、東田将之捜査二課課長は警察庁の指示により他府県へ転任した。
一方、司法制度改革・警察改革を支持していた斎見晃明は昇進を果たしたものの、取り調べの録音・可視化については次第に慎重な立場を取るようになった。酒席では「サンズイの捜査には、濁った水に住む少しはみ出したメダカのような刑事と、その無茶を敢えて見逃す良い上司が必要だ」と語るようになった。木崎たち「情報」の刑事たちと共に仕事をするなかで、斎見自身の捜査観にも変化が生じていた。
木崎は渋谷署への異動を経て、警視庁を退官した。定年を迎えた木崎のもとを訪れた斎見は、一つの報告をする。それは、矢倉かすみが「サンズイ」を立件したという事実だった。
女性刑事が単独で「サンズイ」を摘発したのは、警察史上初の出来事であった。
しかし、司法制度改革・警察改革の進展により、昭和の刑事たちが用いた強引な取り調べ、被疑者の琴線に触れる取り調べは困難となり、「サンズイ」の立件は激減していた。
汚職は本当に消えたのか。収賄は減少したのか。それとも、木崎のように刑事という職務に全てを捧げる「実存としての刑事」が減少しただけなのか。
矢倉かすみは、昭和の刑事たちの最後の「愛弟子」として、その魂を受け継いだ。昭和の刑事たちは静かに去りゆくが、その精神は次の世代へと引き継がれ、時代とともに形を変えながらも存続していくのである。
まとめ:外務省機密費流用事件と『石つぶて』が映し出す変革期—国家の闇と警察の転換点
外務省機密費流用事件は、日本の官僚制度に深く根ざした「裏金」の実態を暴いたが、その捜査を担った警視庁捜査第二課の在り方もまた、変革の過渡期にあった。
本事件の捜査を指揮した捜査二課は、汚職や収賄といった知能犯捜査を専門とする部門であり、地道な捜査手法によって外務省高官の巨額流用を突き止めた。しかし、捜査の過程で浮かび上がったのは、単なる個人の犯罪ではなく、国家レベルの「裏金システム」であった。
ドラマ『石つぶて』は、この事件を基に捜査二課の刑事たちの奮闘を描き、官僚機構の不透明な資金の流れと、国家権力の壁に挑んだ捜査の真実を浮き彫りにした。作品では、捜査官たちの執念と葛藤、そして捜査を封じ込めようとする圧力がリアルに描かれている。
一方で、この時代は警察組織そのものが大きな変革を迎えていた。
本事件の捜査が行われた1999年から2002年にかけて、日本の警察は取調べの可視化や女性刑事の登用といった改革の波 に直面していた。これまでの警察は、強引な取り調べや密室での尋問が常態化 していたが、人権意識の向上に加え、適正手続きの厳格化が求められる時代へと移行しつつあった。その結果、取調べの録音・録画(可視化)が議論され、従来の捜査手法に制約がかかるようになった。自白偏重の捜査に対する批判も強まり、刑事訴訟法の改正を含む司法制度改革が進められるなかで、警察は従来の「密室型捜査」からの転換を迫られていた。
また、女性刑事の登用が進む中で、従来の「刑事像」も変化を迫られた。これまで刑事とは、「無骨で寡黙、生活を顧みずに捜査に没頭する男性像」が典型とされていた。しかし、本事件の捜査を経て、捜査二課の矢倉かすみ刑事が「サンズイ(汚職事件)」を女性として初めて立件 したことは、警察史においても象徴的な出来事である。
『石つぶて』は、単なる汚職事件のドラマではなく、「警察組織と刑事の在り方が変わりゆく時代の物語」でもあった。事件後、捜査二課の刑事たちはそれぞれ異動し、組織の力学に翻弄されながらも、自らの信念を貫いた。一方で、捜査手法や刑事像は次第に変容し、「刑事とは何か」「警察はどうあるべきか」という問いが浮かび上がる。
外務省機密費流用事件が暴いたのは「国家の闇」だけではない。警察組織と刑事の在り方が変革期にあったという事実 でもある。事件が終結しても、その影響は続いている。
本事件では、一部の官僚が立件されたものの、官房機密費の流れや外務省内の不正構造の全貌は解明されないままとなった。2010年、政権交代により外務省の「官邸への機密費上納」の存在が明らかになったものの、その使途はいまだに公表されていない。
国家の裏金問題は、未解決のまま残されている。そして、警察組織と刑事の在り方の変革も、現在進行形で続いている。
★参考文献
『私とキャリアが外務省を腐らせました 汚れ仕事ザンゲ録』小林祐武著,講談社,2004年
『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』清武英利著,講談社,2019年
あなたにオススメ 実際の事件をモチーフにしたドラマ・映画考察と未解決事件考察
◆関連記事







』と功明ちゃん誘拐殺人事件-150x150.webp)