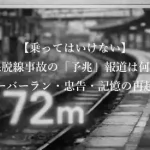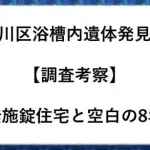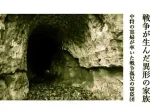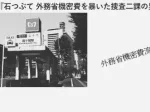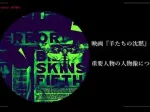交換とは、人間の社会性を象徴する、最も古く根源的な行為である。人類は太古の昔から、物と物を、物と労働を、物と貨幣を交換してきた。そこには信頼と対価、そして相互性という倫理が存在していた。
だが、もし交換されるものが「感情」、とりわけ怒りや復讐心であったならどうだろうか。それが匿名の空間で他者に受け渡され、実行に移されたとき、「交換殺人」という構造が生まれる。
動機と実行が断絶し、責任が拡散する――この特異な構造は、捜査を著しく困難にし、いくつもの未解決事件の背後に密かに潜んでいる可能性がある。
本記事では、『今市市交換殺人事件』(1997年)と『交換ストーカー事件』(2013年)を手がかりに、「交換」という構造の輪郭を辿る。加害と動機が切り離され、共犯関係が不可視化されるその仕組みが、いかに現実に入り込み、捜査と倫理の前提を揺るがしているのか――静かに、だが確かに見つめ直す試みである。
未解決事件を読む「物語の構造」
未解決事件の捉え方には、一つの仮説がある。それは、事件を『物語の構造』として分類する視点である。すなわち、事件には『大きな物語』『小さな物語』、そしてその中間に位置する「中間の物語」が存在するのではないか、というものである。
『大きな物語』は、暴力団や極左団体など、首謀者と実行犯の間に明確な関係性を持つ組織犯罪である。この種の事件では、被害者と組織との間に、金銭や思想、利権などの摩擦が背景にあることが多く、動機の根源が構造化されている。
一方、『小さな物語』は、被害者と加害者の間に私的な関係性が存在し、殺意に至る経緯に感情的な蓄積がある。恋愛、嫉妬、金銭トラブル、あるいは加害者側の一方的な逆恨み――そのいずれもが、加害の動機を形成する。こうした事件が未解決に終わるのは、加害者が被害者と密接な関係にありながら、周囲の誰にも気づかれていない場合である。
そして、『中間の物語』がある。ここでは、加害者と被害者の間に事前の関係性が存在しない。被害者の居住地、行動パターン、立ち寄り先などが偶然的に加害者の射程に入ることによって事件が起きる。だがもう一つ、この「中間領域」に属する構造がある。それが、『交換殺人』である。
交換殺人は、加害者同士が互いに無関係の相手を標的にし、「自分が殺す代わりに、あなたも殺してくれ」と合意する。動機と実行が交差することで、個別の事件において動機が「消える」のだ。この特異な構造は、事件を不可解なものに見せる力を持つ。
『交換殺人』とは何か
交換殺人とは、犯罪の動機と実行を分離し、かつ可視化されない共犯関係によって成立する特異な構造である。一般的な殺人事件では、加害者と被害者の間に何らかの関係性が存在し、それが捜査の手がかりとなる。だが交換殺人においては、犯人自身に直接的な動機が存在しない。殺人は他人のために実行され、その対価として自身の望む殺人もまた他人の手で行われる。
この構造は、倫理的にも法的にも「誰が責任を負うのか」という問題を複雑化させ、加害者(犯人)の特定を極端に困難にするだろう。
フィクションに描かれた完全犯罪の構図
『交換殺人』という語が社会に広まったきっかけの一つは、アルフレッド・ヒッチコック監督による映画『見知らぬ乗客』(Strangers on a Train, 1951)である。小説家パトリシア・ハイスミスの原作に基づく本作では、列車の中で出会った男2人が「お互いの殺人」を持ちかける。動機と実行が交差することで、犯行の合理性と証拠の欠如が巧みに仕組まれている。
この物語構造は、「殺意はあるが手段がない者」と「手段はあるが殺意が希薄な者」が交換関係を結ぶことで成立する。交換相手を「使い捨て可能な道具」と見なす視点がありながら、どちらかが一方的に暴走する危うさも含まれている。
また、日本のテレビドラマにおいても、交換殺人というテーマは繰り返し描かれてきた。たとえば、森村誠一原作のサスペンス・ドラマ『灯』(2001年)、野沢尚脚本による『その男の恐怖』(1998年)など、交換殺人を題材にした作品が複数存在する。これらの作品は、動機が不可視化されることで犯行が“完全犯罪”的に展開されるという構造を通じて、視聴者に「動機の不在こそが恐怖を増幅させる」という印象を強く与えている。
交換殺人というアイデアは、関係性のない人間同士が「目的」によってのみ結びつくことの不気味さを描くものであり、フィクションではそれがサスペンスや倒叙劇の形式で機能してきた。だが、それはあくまで安全な想像の中での「狂気」であり、現実には成立しがたい構造と見なされてきた。
しかし、次章で示すように、その構造は1997年、現実の裁判所の中に姿を現した。
現実に起きた交換殺人(未遂)事件:1997年・栃木今市市の事例
1997年9月、栃木県今市市で発生した殺人事件は、当初「家庭内暴力に苦しむ妻とその友人による共感の結果」として報道された。だが、捜査と裁判の過程で明らかになったのは、極めて計画的で構造的な犯行であった。
被告Aは、暴力的な夫に対する恐怖と不満を口実にしていたが、実際には多額の借金の発覚を恐れ、夫を殺害する計画を立てていた。そして、同様に家庭内暴力に悩んでいた近隣の主婦Bに対し、「お互いの夫を殺そう」と持ちかけた。
これは、フィクションの中で描かれる『交換殺人』の構造に酷似している。
実際の犯行では、交換のうちAの夫のみが殺害された。犯行には、Aの13歳の長男も加わり、母親への共感を動機として凶行に及んでいる。殺害は、包丁による刺突と首を絞めるという複合的手段によって行われ、偶発的な怒りによるものではなく、明らかに準備された犯行だった。
この事件の特異性は、「共感」や「救済」といった表向きの動機の背後に、Aの利己的な事情――借金の隠蔽、自己保身――があった点である。さらに、薬物による事故死偽装など、完全犯罪を意識した試みもなされていた。
事件は結果として未遂に終わった「交換」であり、構造的には不完全であったものの、他者の動機を利用して共犯関係を演出したという点で、交換殺人の原型に位置づけられる。
裁判ではAおよびBの両被告が殺人罪に問われ、それぞれ懲役10年(求刑12年)、懲役7年(求刑10年)の実刑判決が言い渡された。長男については児童自立支援施設への送致となっている。
判決文では「準備周到で残忍」「自己中心的な動機」といった表現が用いられ、家庭内暴力を口実とした情状酌量は限定的にしか考慮されなかった。
『今市市交換殺人(未遂)事件』の限界
仮に本件が完全な『交換殺人』であったとしても、その構造には限界が存在し、未解決事件とはならなかっただろう。AとBは互いに近隣に住み、子ども同士が同級生であるなど、地域的にも人的にも強い接点が存在していた。このような「関係性の濃さ」は、捜査機関にとって犯行動機や共犯関係の端緒を見出す要素となり得る。
つまり、「交換殺人」が真に「発覚しにくい構造」として機能するためには、加害者同士が物理的にも社会的にも無関係であることが望ましい。関係性もなく、地理的にも遠く、日常生活において接触のない他者と匿名空間でつながることで、共犯関係は完全に可視化されず、動機の断絶を保てる。
この意味で、今市事件は「交換的構造」の端緒にある事件ではあっても、交換殺人が未解決のまま成立し得る犯罪モデルとして機能するには、むしろ不完全だったと言えるだろう。
インターネット空間での「交換」:2013年『交換ストーカー事件』
『今市市交換殺人事件』のように、加害者間に人間関係や地域的接点が存在する場合、それは捜査上の重要な手がかりとなりうるだろう。だが、2010年代以降、インターネットの匿名掲示板やSNSの登場によって、加害者同士が互いに顔も本名も知らぬまま「加害の契約」を交わす構造が出現した。
そこには関係性も接触もなく、ただ「復讐したい」「嫌がらせをしてほしい」という欲望だけが結びつく鍵となる。
交換殺人が成立し得る構造的条件――加害者間の無関係性・可視化されない動機・分担された加害行為――が、ネット空間によって現実化されたのである。
復讐サイトの実態と心理的構造
2013年に発覚した『交換ストーカー事件』は、いわゆる『復讐サイト』と呼ばれるインターネット掲示板を介して成立した、共犯的嫌がらせ行為である。そこでは、利用者同士が匿名で恨みの対象を共有し、「あなたの敵に私が干渉する代わりに、あなたは私の敵に干渉してほしい」という“対価付きの加害”が成立していた。
加害者たちは互いの実生活において何ら接点を持たず、共通していたのは「誰かに復讐したい」という欲望だけである。この点において、人間関係を基盤とした「今市市交換殺人事件」とは構造が異なる。ここでは、関係性を媒介せず、欲望と言語だけで成り立つ“純粋な交換構造”が展開されていた。
復讐を目的とする掲示板に、ある者がこう書き込む。
――私は今、確実に復讐しなければならない人間が1人います。
その書き込みを見た誰かが応じる。
――わかりました。協力します。お金はいりません。ひとつだけ、私の復讐に協力いただけることだけが条件です。
この簡単なやり取りによって、「契約」が成立する。
この構造の背後には、「復讐は自分の手で行うべきではない」という自己保身と倫理観のねじれがある。他人に実行させれば、自分は怪しまれずに済むという根拠の乏しい安心感と免罪感が、ネットの匿名性と接続することで、行動の抑制を容易に解除してしまう。
匿名性がもたらす加害の共有と拡張
『交換ストーカー事件』では、加害者は「代行人」という名目で他人の敵に干渉した。たとえば、ある歯科医師の女性が、共犯者の依頼を受けて、元交際相手の妹とその子供にゴキブリの死骸を送りつけた――といった行為が明らかになっている。
復讐の内容は、明確な暴力よりも「不快な介入」や「象徴的嫌がらせ」に留まっていたが、その構造は殺人となんら変わらない。「あなたの敵を私が貶める」ことに「感情的報酬」が伴うため、共犯関係は短時間で成立し、行動にも結びつきやすくなる。
また、金銭の授受もなく、実行は個人の自由意志に基づいて行われる。そこには、従来の「依頼/受託」関係とは異なる「共犯の自発性」があり、それが捜査や責任追及を困難にしている。
「見知らぬ他人」が結託する時:法の限界と課題
この事件を司法の枠組みで捉えると、形式的には教唆罪の構成要件を満たす可能性がある。だが、ネット空間における匿名性ゆえに、「教唆者が誰か」を実行犯が知らないまま犯行に及ぶケースが多く、実体的な因果関係や指示の存在が証明できない。結果として、実行者以外の責任を問うことが著しく困難になる可能性がある。
ネット空間は「会わない共犯」「顔のない依頼者」「法の届かない合意」の温床となっている。そしてこの構造は、殺人へと容易にスライドし得る。現に、2007年の『闇サイト殺人事件』では、面識のない男女が匿名掲示板を通じて知り合い、共謀のうえで金銭目的の殺人を実行した。
この事件は交換殺人ではない。だが、関係性のない者同士がネット空間を介して加害を分担し、実行に至ったという点で、交換殺人の構造――すなわち「匿名的な共犯と目的の交差」にきわめて近い。
交換ストーカー事件は、加害の「分業化」と「匿名的分散」が、いかに現実に浸透しているかを如実に示している。今や、見知らぬ誰かが、別の誰かの恨みを自発的に引き受け、実行に移す時代なのだ。
「闇サイト殺人」と「トクリュウ」に見る交換型犯罪の進化
交換型犯罪が可視化されにくいのは、その構造が「明確な関係性」と「対価の明示」を巧妙に避けるからである。2000年代以降、インターネット上での共犯関係は、互いの素性を知らないまま、加害行為のみで接続される匿名的な連鎖へと変質していった。
こうした現象の延長線上には、『闇サイト殺人事件』と2020年代の『トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)』が存在する。そこにはもはや人間関係も、背景の共有も存在しない。あるのは、「誰かの敵を攻撃する役割を担う」匿名の加害者たちと、その役割を黙認あるいは誘導するネット空間の構造である。
2007年、名古屋市で発生した『闇サイト殺人事件』は、従来の犯罪構造を大きく変容させた象徴的事件である。『闇の職業安定所』と名乗る匿名掲示板で集まった面識のない男女が、金銭目的で女性を襲撃・殺害したこの事件では、依頼者と実行犯、あるいは共犯者同士の物理的接点は一切存在しなかった。
加害者たちは「仕事」としての殺人を認識しており、その共犯関係は匿名性と短期的利害の一致によって成り立っていた。殺人という重大犯罪が、匿名の掲示板上で「業務委託」のように成立する。ここでは交換というより、「他人の目的を請け負う」ことが主体化されている。
交換殺人という構造的犯罪の問題点と未解決事件への応用可能性
交換殺人が現実に成立した場合、その構造には捜査上・司法上の重大な課題が潜んでいる。最大の問題は、加害者と被害者に「動機をつなぐ接点」が存在しないことである。一般的な殺人事件では、動機は捜査の出発点であり、被害者との関係性が重要な手がかりとなる。だが交換殺人においては、加害者は自身の動機によってではなく、他者の復讐を「代行」するかたちで殺人を実行する。
この構造においては、実行犯は一種の「請負人」であり、裏側に「真の動機の保持者」が隠れている。しかも、その人物が実行犯と一度も接触していなければ、動機も関係性も浮かび上がらず、事件は通り魔的な犯行と認識されて終わる危険がある。
また、匿名掲示板やSNS、秘匿通信アプリなどを通じて行われる「交換」は、共犯関係を完全に不可視化する。動機の一方がネット空間にしか存在しないため、仮に実行犯が逮捕されても、「なぜその人物が狙われたのか」は闇のままである。
このような構造的特性は、未解決事件のなかにも潜んでいる可能性がある。たとえば、加害者が特定されず、被害者が特に恨みを買う要素を持たなかった事件――通り魔、無差別殺人、理由不明の襲撃――それらのなかには、「誰かの復讐の代行者」によって実行された「交換殺人」や「片側の交換」が隠れているのかもしれない。
動機と実行を断絶させ、責任を分散し、さらに匿名空間で成立する交換構造は、捜査の網を巧妙にすり抜ける。そしてそれは、社会が前提としてきた「動機と犯行の結びつき」という倫理的枠組みさえも攪乱する。こうして、交換殺人は「動機が見えない犯罪」として現代に潜行するだろう。
SNS型「共犯募集」の現在:トクリュウと犯罪の分散化
2020年代に入り、特殊詐欺の実行役や誘拐などの「実働犯」をSNSで募るケースが増加した。通称「トクリュウ」と呼ばれるこの手口では、Telegram、Signalなどの秘匿性の高い通信アプリが利用され、犯罪者同士の接触は極限まで匿名化・暗号化されている。
この構造の恐ろしさは、参加者が「誰の指示かを知らないまま」犯行に加担することにある。主犯格は完全に後方に隠れ、現場に現れるのは「実行される役割」だけである。加害行為が「分業」され、「責任」が消失していく構造は「交換殺人」に共通している。
さらに、仮想通貨の存在はこの構造に新たな非可視性を加える。金銭の移動がブロックチェーン上で行われ、受け取り手も依頼主も容易には追跡できない。ここでは金銭は「目的の共有」の裏づけではなく、「匿名の信頼」を成立させるための保証機能として作用する。
ただし注意すべきは、金銭との引き換えで明確な殺人を依頼する構造は、刑法上の「殺人教唆」あるいは「依頼殺人」に該当し得る点である。本記事が扱う「交換型構造」は、あくまで金銭を介さず、欲望・復讐・正義感といった「動機の応酬」によって成り立つ共感的な加害構造である。
それでも、仮想通貨や秘匿通信アプリが犯罪の責任をより曖昧にし、「誰のために」「なぜ行われたか」を不明瞭にする傾向は、交換型構造の隠蔽性を一層強化するだろう。現代においては、「誰かの加害」に見えて、その背後には「他人の動機」が潜んでいるという二重の構造を想定しなければ、捜査も裁きも成立しない段階に入っている。
結語:動機なき殺人の時代を生きる
交換殺人という構造は、もはやフィクションの中に閉じ込めておける概念ではない。動機と実行が分断され、匿名の加害者同士がネット空間で交差する現代において、殺意は「他者を介して実行される欲望」として、共有・流通し始めている。
この構造が恐ろしいのは、実行者が誰かの代弁者でありながら、その「誰か」がどこにも実在しないかのように姿を消していることにある。復讐、嫌悪、怒りといった負の感情が他者に「委託」されるとき、そこに責任の所在はなく、動機すらも検出不可能になる。
未解決事件の一部には、「殺した者が動機を持つ犯人ではない」という構造が、静かに横たわっているのかもしれない。見知らぬ誰かが、見知らぬ誰かの怒りを請け負い、さらに別の誰かを殺す。そこにあるのは、復讐ではなく、欲望の代行だろう。加害の動機は移植され、責任は拡散し、倫理は誰にも届かなくなる。
かつて、殺人とは、動機と主体が一つの線で結ばれた物語だった。しかし今、交換という機構がその線を断ち切る。誰が望み、誰が実行したのか――その境界は、匿名という霧の中に沈み、殺意だけが、名前を持たずに流通していく。
私たちは今、殺人という行為が、誰のものでもないまま遂行される時代を生きている。
◆参考資料
『読売新聞』1997年9月27日付
『中日新聞』1997年9月29日付
『中日新聞』1997年12月9日付
『日刊スポーツ』1997年12月10日付
『毎日新聞』1998年9月1日付
『産経新聞』2014年3月19日付
『産経新聞』2014年3月22日付
◆オススメの記事