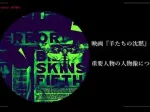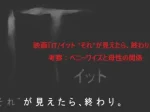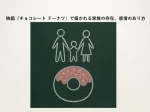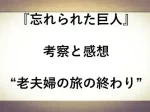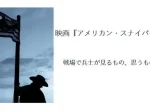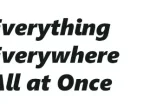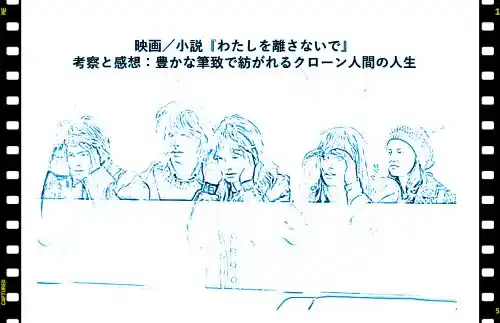
記事要約『わたしを離さないで』は、臓器提供を使命として生まれたクローン人間たちの静かな人生を描いた物語である。本記事では、主人公キャシーの視点を通じて「生きること」「死ぬこと」「人間らしさ」について考察する。過剰な感情描写を排した淡々とした語りの中に、深い郷愁と哀しみが織り込まれた本作は、読むたびに新たな気づきを与えてくれる。
漫画で、アニメで、小説で。特にSFというジャンルを冠する作品には、「クローン」という存在がしばしば登場する。それぞれに思い入れのある作品がある人も少なくないだろう。
筆者にとって、クローンを題材とした作品の中でも思い入れが強いのが『わたしを離さないで』という作品だ。カズオ・イシグロの著作である本作は、映画化のほかに、日本でドラマ化もされている。
今回は、原作小説と映画版をからめながら、本作の考察と、筆者の感想を書いていきたいと思う。
『わたしを離さないで』作品概要:映画/小説
『わたしを離さないで』は、2005年に発表されたカズオ・イシグロの小説である。2010年にはキャリー・マリガンなどが主演を務めた映画版も公開。さらに日本でも、舞台化及びドラマ化された(舞台版とドラマ版については、この記事では触れないでおく)。
本作は、臓器提供のために生み出されたクローン人間を主人公とした作品である。いわゆる「クローンの反乱」であるとか、「お涙頂戴の展開」などはなく、クローンとして生まれた人々の感情などを静かに、それでいて心揺さぶる筆致で描いている。
多少の違いや省略した部分はあれど、本作の映画版は原作に非常に忠実だ。原作の中で起こった重要であろう事柄をきれいに拾い集め、わかりやすく表現している。それぞれ独自の魅力があるが、どちらも目を通しておくことで、より物語の世界が理解しやすくなるはずだ。
あらすじ
主人公のキャシーは31歳(映画では28歳)。優秀な「介護人」として、「提供者」の世話を長年続けてきた。自分の仕事に自負はあるが、”潮時“だとも感じている。
彼女が思い出すのは、幼いころに育ったヘールシャムのこと。ルースとトミー、そしてその他の友人たちと暮らしたときのこと。そして、ヘールシャムを卒業してから暮らした”コテージ“でのこと。
特定の目的のために生まれたキャシーたち。彼女たちは何を考え、どのように成長し、生きていったのだろうか。キャシーの記憶を辿ることで、その真実が明らかになっていく。
生きること、死ぬこと、嫌悪感:『わたしを離さないで』考察
クローン人間と聞いて、どんな存在を思い浮かべるだろうか。
映画『アイランド』(2005年)のように、生き残りをかけて戦う存在?もしくは、映画『us』(2019年)やルパン三世映画版のマモーのように、いわゆる「オリジナル」からは離れた異質な存在?人間ではないが、実在のクローン羊・ドリーを想像した人もいるかもしれない。
クローン人間をテーマに据えた作品の中には、彼らが持つ悲劇性を物語のキーワードとして据えることが少なくない。本作でいえば、「ドナーとなるために生まれた」という部分だ。望む仕事をしたり長生きしたりといった未来は、彼らには存在しない。
もちろん本作も、ドナー要員として生まれた彼女らの悲劇は描写されている。それでもなお、他の作品よりもよほど静かだ。キャシーたちクローンは死を恐れるし、できる限り遅らせようとはする。それでも、「提供」という使命から目を背けることはない(背けさせてくれないという側面もある)。
映画『アイランド』では、ユアン・マクレガー演じる主人公が生きるため、自由になるために戦うことになる。これは、もともと自分が置かれた環境を知らず、その上で恐ろしい事実を知ってしまった故の行動だ。
しかし、本作でキャシーたちはこうした行動を起こすことはない。唯一といえるのは「提供猶予」を受けるための行動だが、あくまでも「猶予」であって「免除」ではない。キャシーの前にも提供猶予に挑んだ人たちがいたらしいが、彼ら(彼女ら)も、寿命まで生き延びるための行動ではなかったはずだ。
キャシーたちが「免除」ではなく「猶予」を求める理由。それは、彼女らが育ってきた環境にあるのだろう。キャシー達はヘールシャムの”保護官“によって、彼女たちの人生について、それとなく、幼いころから教えられてきた。「自分は”提供”という使命のために生まれた」と物心つく前から知っておくことで、人間の本質である恐怖感を薄めてきたのである。
人間は誰でも死ぬのが怖い。「死」とはいつどこで、どんな形で来るか分からないからだ。しかし、キャシーたちは違う。自分の未来について、ある程度の予測がつくのである。また、ヘールシャムはクローンを育てる機関の中でもかなり人道的な施設だったようで、より穏やかに、自分の未来を受け入れられたとも考えられる。
そんなヘールシャムの中にも、「ゆっくりと、かつ、それとなく」未来を教えることに対し反発していた保護官がいた。それがルーシー先生である。
映画版でこそ扱いが少ないものの、原作小説でのルーシー先生の役割は重要だ。ルーシー先生は短い期間でヘールシャムを去った保護官だが、主人公3人の、特にトミーに強い印象を残した人物である。
ヘールシャム、そして、ヘールシャムを代表する保護官であるエミリ先生は、キャシーたちを守るために「隠し事」をすることを是としていた。使命を知ったことによるショックを減らし、少なくとも幸せな子供時代を過ごすためだろう。
しかし、ルーシー先生は違った。「隠し事」をすることなく、しっかりと子供たちに自分の未来を教える方がよいと思っていたようだ。
これは、ルーシー先生がキャシーたちを「人間」として見ていたことを意味するのだろう。将来の「提供者」ではなく、ただ目の前にいる「子供」として。普通の人間と変わらず得意不得意があり、悩み苦しむ存在として。
物語の終盤、キャシーたちを守り導いてきたエミリ先生は、彼女たちヘールシャムの子供たちが「怖かった」と吐露する。キャシーたちが描いた絵を集め、クローンに「心がある」ことを証明しようと奮闘していたマダムも同様だ。この恐怖感は、自分とは全く異なる存在に対する恐怖感を指すのだろう。
キャシーたちクローンは、私たちとは全く異なる理由やプロセスで生まれた存在だ。望まれて、愛されて生まれたわけではない。それでも、クローンたちには「心」があった。私たちと同じく、悩み、愛し、恐れ、そして疲れ、あきらめてしまう。
本作は、クローン人間が生き、考え、そして死んでいく物語だ。そして、彼らに対し恐怖感を抱きながらも手放せない、いわゆる「普通の」人間の物語だ。
本作を読んだり見たりして、「普通」の人間のエゴを嗤う人もいるだろう。しかし、もし自分自身に臓器移植が必要になったとき、彼らを頼らずにいられるのだろうか。私は自信がない。
キャシーたちとともに育つ心:『わたしを離さないで』感想
淡々とした文章。これは、感情が込められていないと見られる場合が少なくない。浮き沈みの激しさが一見でわかる感情的な文章に比べ、冷静に見渡している感覚になるからだろう。読みやすい反面、平坦な印象を与えることも多い。
本作は、淡々としたキャシーの独白で語られる物語である。キャシーはあくまでも冷静に、自分の感情や周囲の状況を冷静に描写している。にも関わらず、本作は非常に情緒的だ。
本作で語られるキャシーの言葉は、過去を懐かしんでいる言葉が多い。よい思い出と悪い思い出の双方を含めたルースとの記憶。トミーと交わした会話。待ち受ける未来に対する恐怖感よりも、幸せな過去の時代に向ける郷愁の方が大きい。そしてそれは、ルースやトミーが「終了(使命を終えること)」してからも変わらない。
キャシーの物語を追いかけていると、自分自身の子供時代の思い出だとか、友人と過ごした日々だとかが頭の中を駆け巡ることになる。背景となる国や状況は違っても、共通項は少なくないらしい(カズオ・イシグロは子供のころに日本からイギリスに渡った)。
だからこそ、本作は淡々とした文章ながら読み飽きることがない。キャシーの記憶と自分の記憶が混ざりあい、ヘールシャムやコテージの風景が目の前にはっきりと浮かぶ。キャシーの気持ちも、トミーの気持ちも、鼻もちならない部分のあるルースの気持ちも理解できてしまう。そして、提供を自分の未来として受け入れている彼女らの感情も、なんとなくストンと腑に落ちるのだ。「かわいそうだから続きを見たくない」という気持ちにはなりにくい。
本作の物語を追う側も、ヘールシャムの子供たちと同じようにならされていくのだろう。未来に何が待っているか小分けで知り、心構えをしているのである。
筆者は本作の映画を何度か見返し、何度も原作小説を読み返した。その都度、少しずつ違う感覚を味わっている。基本的にはキャシーやルースと同じ目線になっているが、今度は保護官の目線になってみたいと考えている。
そのときどんな感想を抱くのかは、別の機会に語ってみたい。
まとめ
『わたしを離さないで』はクローン人間やクローン技術という、センセーショナルになりがちな題材を扱った作品だ。しかし本作は、どこまでも静かで情緒的である。
見る(読む)人にとっては、「つまらない」や「感傷的すぎる」と思う人もいるだろう。しかし、筆者はこれでよいと考えている。人間は本来感傷的なものだし、冷静な文章だからこそキャシーの気持ちが理解しやすくなるからだ。
もしキャシーの立場に立ったらどうするだろうか。自分の使命をはっきりと理解したとき、どんな反応をするだろうか。もし、子供がどうあがいても産めないと知ったら……?
人生のあらゆる年齢、あらゆる局面で、再度鑑賞したい作品である。
公式映像資料(YouTube)
文章だけでは伝わらない空気を、映像として確認するための資料として掲載する。
🎥参考映像(出典:シネマトゥデイ公式チャンネル)映画『わたしを離さないで』予告編
◆カズオ・イシグロ作品紹介
海外SF映画シリーズ
◆おすすめの記事