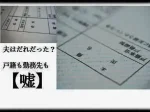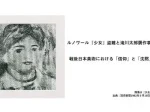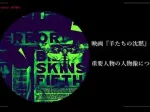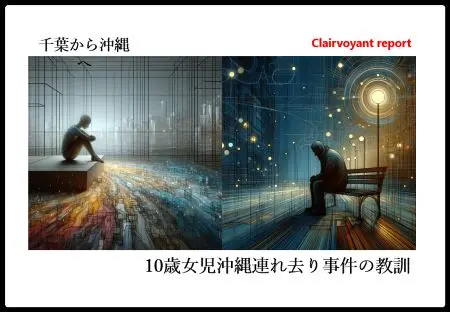
【本記事は事件の社会的考察を目的とし、犯罪を肯定・擁護する意図は一切ない】
2004年5月、千葉県から沖縄県へと跨がる未成年者誘拐事件が日本全国に衝撃を与えた。この事件は、住所、職業不詳の47歳、A容疑者によって引き起こされ、単なる犯罪行為にとどまらず、社会が直面している深刻な問題を浮き彫りにした。
事件発生時、A容疑者は10歳の女児を8日間にわたって連れ回し、その間、女児の健康や安全への懸念が高まった。幸いにも女児は無事保護され、この事件から多くの教訓が得られた。
事件概要
2004年5月某日18時頃、千葉県内に住む顔見知りの女児を誘拐した疑いで、A容疑者が逮捕された誘拐後、女児とA容疑者は千葉県内の宿泊施設付き公衆浴場に滞在し、その後は沖縄県内の民宿などに泊まっていた。
女児は母方の祖父母(祖父の年齢は54歳)や叔父(母親の弟)と4人暮らしで、A容疑者は以前から女児家族と顔見知りだったといわれる。女児は事件以前から家族に内緒で一人暮らしのA容疑者宅を訪ねていた。A容疑者と女児は以前にも連れ去りの事案があり、近隣住民や女児の祖父はA容疑者に対して警戒していたといわれる。
また、女児が「家に帰りたくない、沖縄に行こう」と言っていたという証言もあり、家庭内の問題を抱えていることが示唆されている。A容疑者は女児と「駆け落ち」、「周囲からの虐待から女児を守るための逃避行」のつもりであったのかもしれない。A容疑者は沖縄県での永住を目指して職を探し、女児は宿泊先の経営者にAを父親だと語り、宿泊者名簿にA姓の苗字と女児の名前を組み合わせた氏名を自ら書き込んだともいわれる。
最終的に沖縄市内の会社の駐車場で寝ていたA容疑者を捜査員が発見し、その後、沖縄県の海岸近くの店舗内で女児を保護した。
警察の調べに対して容疑を認めたA容疑者は、女児を連れ去った動機や行動について詳細を語り、その過程で女児を千葉から沖縄へ連れて行き、複数の場所で宿泊したこと、千葉県内の入浴施設で利用客に女児の身体を触ったなどの言いがかりをつけ、現金22万円を脅し取り、その金を沖縄行きの航空代金や生活費に充てたことなどが明らかになった。
Aの供述からは、女児に対する特定の悪意や害意よりも、歪んだ愛情や保護欲求が行動の背景にあることが示唆されているが、その後、A容疑者は未成年者誘拐などの罪で起訴され、裁判の結果、未成年者誘拐および恐喝の罪により懲役2年6ヶ月の判決が下された。
この判決は、Aが女児に対して抱いた歪んだ感情とその行動が女児の成長に及ぼした悪影響の深刻さを考慮してのものであった。
裁判過程でAは女児を保護しようとした意図があったと主張したが、裁判所はAの行為が女児に重大な心理的および身体的危害を与えたと判断した。また、裁判の過程で女児に対して性的加害が明らかになった。
しかし、Aは性的加害についての罪を問われることはなかった。Aが問われたのは、監護者の権利を侵害した未成年者略取誘拐と入浴施設の利用客を恐喝した罪だけである。Aは、性犯罪者として処罰されることもなく、小児性愛(障碍)として適切な治療を受けることもなかった。
それから約10年後、Aはメディアのインタビューに答え、自己の異常な小児性愛(障碍)傾向を認め、再犯の衝動と不安、社会から孤立した生活を送り、性犯罪への強迫観念に悩まされていることを明かしている。この事件は、子どもの安全と犯罪者の心理に関する深い問題を提起し、社会に対して再発防止と子ども保護のための体制強化の必要性を訴えた。
自己肯定化
Aは裁判の過程で自らの行為を自己肯定化している。Aは裁判の過程で、女児誘拐の動機は、女児の保護であり、性的加害の理由は、他の成人男性から性的加害を受けていた女児の性に対する積極的な感覚を止めるため「毒を持って毒を制する気持ちだった」などと述べ周囲を驚かせている(参考:河合香織『帰りたくない―少女沖縄連れ去り事件―』新潮文庫)。
これらのAの供述と行動から、小児性愛(障碍)、分裂的自己像、強迫観念と自己正当化、自己愛と幼児性、依存性と逃避といった心理的側面が考察される。これらは、彼の行為を受け入れ可能な形に変容させ、自らを正当化し、社会的責任から逃れようとする彼の試みを反映しているともいえるだろう。
また、Aは過去に成人男性から性的被害を受けたという。このAの過去の経験、特に小学生時代に同性(男性)から受けた性被害、Aの2回の離婚歴、そして無職で生活保護を受けている状況は、彼の性癖や嗜好、小児性愛(障碍)傾向に影響を与え、今回の事件につながった可能性も考えられるだろう。
これらの背景要因は、Aが事件を起こすに至った心理的状態を理解する上で重要な手がかりとなる。Aの抱える社会的地位の喪失、自尊心の低下、対人関係の不安定さなどが彼の心の奥底で複合的に絡み合い、Aを少女に対する性的行動へと導いたと可能性が考えられる。 さらに、Aは被害者の10歳の被害者女児から、「おい」、「バカ」など罵倒されていたが、それら女児の言動を黙認していたという(参考:河合香織『帰りたくない―少女沖縄連れ去り事件―』(新潮文庫)。このAの被虐的な性質および自信のなさは、彼の境遇や事件前の彼の生活状況に深く影響されていることが推察され、Aが大人の自立した女性に対して恐怖感を抱いていた可能性についても考察される。
保護・支配・利用
無垢な女性に対する(崇拝)信仰は、世界の多くの文化や宗教に見られる概念であり、無垢な女性(特に少女)に対する純潔や清らかさを特別視する価値観である。小児性愛者が相手の社会的・人間関係における経験の低さに注目する場合、これらの特性を利用して相手を支配しようとする動機が考えられる。
加害者は、被害者が性的、社会的、人間関係において未熟であればあるほど、自己の優位性を確立しやすくなり、これが加害者にとって魅力的な状況となる。未経験者であることは、加害者による操作とコントロールの容易さを意味し、年齢による社会的経験の低さは、被害者が加害者の言動に対して疑問を持ちにくく、反抗や抵抗を示しにくい状況を作り出す。
本事件のAは事件後のインタビューにおいて、自ら小児性愛(障碍)傾向があるとことを認めている。Aは自分の欲望のため10歳女児の未熟さを利用したともいえそうだ。
倫理的には、成人と未成年の関係は、自由意志、同意、当事者同士の力関係の不均衡、個人の福祉など、多くの複雑な問題を提起する。同意の問題について、成人と未成年の関係性での「同意」は、両者の力の不均衡や心理的影響のため、他の関係よりも問題が複雑になりがちである。
また、保護者と被保護者の関係は他の関係とは異なり、深い情動的絆や依存関係を含むため、同意が完全に自由であるとは限らず、倫理的評価では、個人の精神的および感情的福祉だけでなく、潜在的な子どもの福祉と社会全体への影響も重要な考慮事項である。さらに、保護者と被保護者の倫理を逸脱した関係が公になった場合の社会的スティグマと排除のリスクをもたらし、関係に含まれる個人の福祉に悪影響を及ぼす可能性がある。
これらを考えれば、Aが主張する保護/被保護の関係は本来の保護の意味を持たない。Aが保護の対象である女児に性的加害を行うのであれば、それは、女児の精神面に大きな影響を与え、事が発覚すれば女児に対する社会的スティグマと排除リスクを与えてしまうことは容易に想像できる。それは、保護ではない。Aの保護を目的とした関係という主張は倫理的に破綻している。
小説、映画作品との比較
本件事件でAが女児の言いなりになっていたという側面は、有名な小説『ロリータ』(ウラジーミル・ナボコフ著、1955.)や『痴人の愛』(谷崎潤一郎著、1925.)に見られるテーマと共通する点がある。これらの作品では、成人男性が若い女性や少女に対して強い魅力を感じ、その結果、彼女たちに対する自身の感情や行動がコントロールされる様子が描かれている。
『ロリータ』では、主人公の30代後半男性ハンバート・ハンバートが12歳の少女ロリータに強い執着を見せ、彼女に対する愛情と執着が彼の行動を支配する。しかし、物語が進むにつれて、ロリータがハンバートの感情や欲望をある程度操るシーンが見られ、彼女が彼に対してある種の力を持っていることが示される。
『痴人の愛』では、主人公の河合譲治(28歳)が若い娘、ナオミ(15歳)に対して深い愛情と支配欲を抱くが、ナオミは次第に譲治を支配する立場に立つ。ナオミは譲治の愛情を利用し、彼の行動や思考を操る存在となり、譲治はナオミに完全に支配されることになる。
映画『ウーナ13歳の欲動』の主人公レイは、近隣に住む当時13歳ウーナと性的関係を持ち、家庭に不満を抱えるウーナはレイと駆け落ち約束する。

画像リンク先は、記事『映画『ウーナ』作品解説:子供の頃に受けた傷が影響するもの』
その後、ウーナは警察に保護され、レイは未成年者との性行為で逮捕される。彼は4年間の服役を余儀なくされるが、出所後、名前をピートに変えて社会復帰する。ウーナは、事件が公になって以降、周囲から異様な視線を受け続け、その結果、性格と精神面に問題が生じてしまう。また、娘を案じる母親は、過保護になり、それがウーナの苦痛を増大させる。
レイは年齢の壁を乗り越え、本気で愛し合ったというが、彼の本意を知りたいウーナは大人になっても彼との関係について悩み続ける。レイが欲したのは自分の身体か心か――。
映画『ウーナ13歳の欲動』は、本事件と似た側面を持つ。それは、レイのウーナに対する行動は愛や恋愛感情からか、小児性愛障碍からか。レイは欲望のためにウーナを利用したのか、保護者の立場を取ろうとしたのか。それならなぜ、ウーナと関係を持ったのか、なぜ、発覚すれば(当然だが簡単に発覚する)大事になる13歳の子どもと駆け落ちしようとしたのか――などである。
これらの作品に共通する若い女性や少女が成人男性に対して一定の支配力を持つというテーマは、今回の事件におけるAの告白と通じる面があるが、小説や映画内での関係性と実際の事件との間には大きな違いがあることを忘れてはならない。文学作品や映画作品では複雑な人間関係や心理が芸術的に描かれているが、実際の事件では、被害者である少女、女児の人権や尊厳が侵害される深刻な犯罪になる。
当然だが、文学作品と実際の事件とを比較する際には、虚構と現実の違いを理解することが重要だろう。
報道によれば、事件当時Aが住んでいた部屋から10代前半の少女が出演するAV数点が押収されたとある。検察官はこれらのビデオはAの性的嗜好に関係し、Aの性的嗜好性が事件の動機と指摘する。
これら少女を対象とするAV、漫画、雑誌、写真集などは、80年代からのアンダーグラウンドカルチャーの大衆化と関係している。一方で、そもそも人間の内心の自由は物理的に束縛されるものではなく、人間の思考は倫理や現実の法律から自由であるべきだという意見がある。それにもかかわらず、その思考を行動に移すことは、社会の法律や倫理規範によって制約される。
このように、内心の自由と外界の制約の間に存在する緊張関係は、人間の行動と社会との関わり方において重要な役割を果たしている。人はその思考においては自由かもしれないが、その思考を具体化する自由は、他者の権利や社会の秩序を保護するために、必要に応じて制限される。 この概念は、個人が社会内でどのように振る舞うべきか、またどのように行動すべきかについての基本的な枠組みを提供する。社会における人間の「自由」は、「責任」と密接に関連しており、表裏一体であるとも言える。社会が機能するためには、個人の自由を尊重しつつも、その自由が他者の自由や権利とのバランスの上に成り立っている必要がある。このバランスが崩れると、加害者と被害者が生じることになるだろう。
被害者女児の家庭環境
被害者女児は、祖父母と叔父と暮らしていた。非常に複雑な生育環境・家庭環境で育ったことは容易に想像できる。女児は複雑な生育環境・家庭環境で育ち、幼少期から児童相談所の関与がある生活を送り、さらには近所の成人男性と性的意味合いを持つ関係があったとされる。女児のこれらの状況は、Aが主張するように女児が性的に早熟な傾向を示唆している可能性が高いとも考えられる。
近隣男性との関係は、女児が成人男性をコントロールするための経験となった可能性が考えられ、これらの経験は女児に、成人男性との関係において彼女の行動や選択に影響を与えていることが推測される。
しかし、これらの行動や関係性の形成には、女児自身の心理的な葛藤や苦悩が伴っている可能性も考慮されるべきである。不安定な家庭環境や早熟な性的意味合いを持つ経験は、彼女の心理的発達に複雑な影響を与え、成人男性との関係性におけるコントロールの試みが、自己保護の手段であると同時に、内心の不安や混乱の表れである可能性が考えられる。これらから、女児の経験を単純に被害者が加害者をコントロールする力として解釈することは適切ではないだろう。なぜなら、このような関係性の背景には、成人男性と女児の経験値の不均衡、女児の心理的な脆弱性、そして社会的な脈絡が存在しているからである。
本件事件を通じて浮き彫りになったのは、児童保護と性犯罪者への社会的対応の問題だけでなく、家庭環境や社会的な要因が個人の心理状態や行動にどのように影響を及ぼすかという複雑な問題である。この事件から得られる教訓は多岐にわたり、子どもたちの安全と健全な発達を守るために、社会全体での対応と理解の深化が求められている。
複雑な生育環境・家庭環境にいた女児に居場所はなかった。居場所のない女児は、週末になると近隣男性やAの家に泊まっていたといわれ、学校では虐めの対象とされていたようだ。 結論として、本件事件における被害者女児の行動や背景を理解し、事件を通じて浮かび上がる社会的な課題に対しては、法的、倫理的な観点からのみならず、教育的、心理的な支援の強化を含む多角的なアプローチが求められるだろう。このような事件が再発しないように、子どもたちの健全な成長を支援し、保護するための社会全体の取り組みが重要であるだろう。
疑似恋愛と家族的関係——映画と現実の交差点:映画が描く「孤独な大人と少女の関係」
『シベールの日曜日』や『レオン』は、孤独な大人の男性と、社会に居場所のない少女が出会い、互いに惹かれ合う関係を描いている。しかし、それは決して単純な恋愛関係ではなく、親子や兄妹のような「家族的な絆」も内包している。
『シベールの日曜日』では、戦争のトラウマを抱えたピエールと、親に捨てられた少女シベールの間に芽生えたのは、純粋な交流だった。二人は互いに心を通わせるが、社会はそれを許さず、最終的に悲劇を迎える。
『レオン』では、殺し屋のレオンと家族を惨殺されたマチルダの関係が描かれる。マチルダはレオンに対し恋愛感情を抱くが、レオンはそれを拒絶し、彼女を保護する立場を貫く。ここでも「擬似的な恋愛」と「家族的な絆」の間に緊張関係が生まれる。
疑似恋愛か、共依存か——事件との違い
映画における関係性は、最終的に「守る側と守られる側の関係」として成立している。しかし、今回の事件では、少女が「生存戦略」として加害者との関係を受け入れた点で大きく異なる。
映画では、少女たちが大人に依存するのは避けられない状況にあるものの、大人の側には性的な動機がない。しかし、現実の事件では、「保護」の名目のもとで関係が築かれたとしても、加害者の動機には支配や性的欲求が絡んでいる。
加害者が被害者を支配しようとしながらも、結果として少女に依存し、共依存関係に陥る。この構造は、映画が描く「孤独な大人と少女の関係」と似ているようで、その本質は大きく異なる。
社会はなぜこの関係を拒絶するのか
『シベールの日曜日』や『レオン』では、純粋な関係が社会によって誤解され、悲劇を迎える。しかし、現実の事件では、少女が大人の男性に依存すること自体が、危険な状況を生み出す。
社会がこうした関係に懐疑的なのは、「保護」と「支配」の境界が曖昧になりやすいためである。映画では関係が理想化されるが、現実には、支配と欲望の構造が入り込み、被害者の自由を奪う危険性がある。
「純粋な関係と犯罪の境界線はどこにあるのか?」という問いに対する答えは明確だ。子どもは保護されるべき存在であり、大人はそこに一切の支配を持ち込むべきではない。どれほど相手を思いやる感情があろうとも、未成年者との関係が社会的に拒絶されるのは、その根底にある「権力の非対称性」に起因している。
現実の事件が示すもの
本事件は、「疑似恋愛」や「家族的関係」が成り立たない現実を突きつけた。社会から孤立した大人と、家庭に居場所を見つけられなかった少女が出会ったとしても、それは決して純粋なものにはなり得ない。
映画が描くような「守るための愛」は、現実には存在しない。支配の構造が生まれる以上、それは「共依存」へと変質し、被害者にとって危険な環境を生み出す。
映画と現実の交差点にあるのは、「関係の理想化」という落とし穴である。社会がこの問題を正しく認識しなければ、同じような事件は繰り返されるだろう。
被害者の生存戦略としての「女性性」
本事件における被害者女児は、生存戦略として「女性」として振る舞う術を持っていたと考えられるだろう。これは単なる恋愛感情ではなく、家庭や社会に居場所を見出せなかったことからくる適応行動だった可能性が高い。
被害者女児は家庭内の問題を抱え、以前から成人男性との関係を築くことで自身の居場所を確保していた。加害者Aに対しても、単に従属するのではなく、疑似的な恋愛関係や夫婦関係を演じることで、自らの立場を守ろうとしたと推測できる。これは、多くの少女が不安定な家庭環境のもとで取る「生き延びるための手段」とも言える。
こうした適応行動は、しばしば被害者の「積極的な選択」と誤解されるが、実際には選択肢のない中での最適な生存戦略である。社会の中で本来守られるべき存在でありながら、被害者自身が「守られる」という発想を持てない環境にいた場合、自己を守るために「女性として振る舞う」ことが求められる。
このような「環境に適応するための生存戦略」は、社会的に守られるべき年齢の少女が、守られない現実の中で身につけざるを得なかった戦略である。その点において、社会からの孤立と生存戦略の結果として、被害者は「女性的な振る舞い」をせざるを得なかったのだろう。しかし、それは本来の意味での「女性としての成熟」ではなく、むしろ歪んだ形での自立だったと言える。
また、こうした被害者の行動は、社会全体が子どもを適切に保護できなかった結果として生じた現象でもある。被害者の生存戦略は、周囲の無関心や無力さによって育まれたものであり、単なる個人の問題ではなく、社会的な問題の表れとして捉える必要がある。
「女性だった被害者」と「女性的な加害者」
本事件では、被害者が「環境に適応するための生存戦略」を持っていた一方で、加害者Aもまた「環境に適応するための生存戦略」を持っていたと考えられる。
Aは、社会的に無力でありながら、被害者との関係性を維持するために、受け身的な姿勢を取りつつ、状況を利用する狡猾さを持っていた。これは、単なる加害者と被害者の構図では説明しきれない「共依存関係」に近い。
文学作品『ロリータ』や『痴人の愛』では、少女や若い女性が一見従属的な立場でありながら、最終的には男性を支配する関係へと転じる。このような「関係性の逆転構造」は、本事件にも見られる特徴の一つである。Aは被害者をコントロールしようとしながらも、被害者の行動や言動に影響を受け、自らの立場を変化させていった。
Aは被害者との関係の中で、「保護者」の立場を取ることで自身の存在意義を見出していた。しかし、被害者が彼に対して一定の影響力を持つようになったことで、その立場は揺らいでいった。疑似夫婦・疑似恋愛関係が成立する中で、Aは当初、保護者としての立場を装いながら支配しようとした。しかし、被害者が彼に対して要求を強めていくにつれ、Aは逆に彼女に依存し、関係の力学が変化していった。
この点で、本事件は単なる性犯罪の枠を超え、「共依存の果てに生まれた歪んだ関係」として理解する必要がある。Aが被害者を支配しようとしながらも、結果として被害者に精神的に依存し、関係の力学が揺らいだように見えるのは、共依存的な関係性の特徴である。
被害者の「環境に適応するための生存戦略」と加害者Aの「女性的な狡猾さ」が交錯し、両者の関係は単純な加害・被害の関係では説明しきれない複雑な構造を持つに至ったと言える。
「疑似恋愛」と「共依存」が生み出した異常な関係性
本事件の本質は、加害者が被害者を利用しただけの単純な犯罪ではなく、疑似的な恋愛関係・夫婦関係を通じた共依存の構造にある。
加害者Aは、被害者に対して「保護する」という立場をとりながら、同時に精神的に依存していた。被害者もまた、自らの居場所を確保するために加害者との関係を利用していた。
しかし、いかに共依存的な関係が成立していたとしても、これは加害者の欲望と支配のもとに形成された異常な関係であり、犯罪であることに変わりはない。被害者が「女性」として振る舞っていたとしても、それは適応戦略の一環であり、決して主体的な選択ではなかった。
また、この関係性が共依存であったとしても、それはあくまで被害者の立場の弱さに根ざしたものである。加害者Aは、自らが主体的に関係を築いたつもりでいても、実際には被害者の行動に影響され、「支配者でありながらも被害者にとって必要な存在であろうとする」という矛盾を抱えていた。
このような共依存関係が生まれる背景には、家庭環境の不安定さ、社会の無関心、そして加害者自身の孤立といった要素が複雑に絡み合っている。事件の本質を理解するためには、単なる加害者の異常性だけでなく、この関係を生み出した社会構造にも目を向ける必要がある。
また、こうした「疑似恋愛」「共依存」が生まれた要因として、加害者Aの「環境に適応するための生存戦略」だけでなく、被害者自身が持たざるを得なかった「女性としての戦略」を分析することが、事件の全体像を理解する上で不可欠であろう。
まとめ
本件事件は、未成年者の保護と性犯罪者、小児性愛(障碍)への対応に関して、社会が直面している課題を浮き彫りにするものである。事件から学ぶべき最も重要な教訓は、児童保護のための具体的な措置の強化と性犯罪者への再犯防止策の確立である。
子どもたちが安全な環境で成長できるように、学校教育や地域社会での啓発活動を強化することが重要であるだろう。子どもたち自身が危険を察知し、適切な対応を取ることができるように、安全教育の推進が求められる。
また、子どもが抱える家庭内の問題に対しても、早期に対応し、支援を提供する体制を整えることが不可欠である。教育機関や地域社会は、児童の安全を確保するために予防教育や安全な環境の提供に積極的に取り組む必要がある。
なお、2022年(令和4年)の『警察白書統計資料』によると、2021年(令和3年)中に警察によって保護された児童の数は4,882人で、これは2020年の5,526人や2019年の5,553人からの減少を示している。ただし、近年、「トー横キッズ」と呼ばれる10代前半の居場所のない若者たちの存在がメディアによって明らかにされ、彼らが犯罪の被害に遭うケースが問題となっている。
さらに、加害者には、厳しい法的措置だけでなく、小児性愛(障碍)傾向者や性犯罪者に対する効果的な治療プログラムや支援体制の整備も、再犯のリスクを減少させ、社会全体の安全を高めるために不可欠である。
「子ども家庭庁」性犯罪の再犯に関する資料によると「有罪確定後5年間のうちに再び性犯罪に及び、有罪確定した者の割合の性犯罪再犯率は、13.9%(1484人中、207人)、小児わいせつ型の性犯罪で有罪確定した者のうち、それ以前に2回以上の性犯罪前科を有している者のそれらの前科が小児わいせつ型であった者の割合は84.6%(13人中、11人)である。この数値は再犯率ではないが、小児わいせつ型の性犯罪に及んだ者の中に、複数回の刑事処分を受けた後も小児わいせつ型の性犯罪を繰り返す者が一定数存在することが認められる」(参考・引用:外部リンク:子ども家庭庁「性犯罪の再犯に関する資料こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議 第2回会議配布資料」2023年7月19日)とあり、母数は少ないものの「小児わいせつ型」性犯罪者が同様の犯罪を繰り返す傾向が見て取れる。
この事件は、単に一つの犯罪事件として終わるのではなく、社会全体で子どもたちの安全を守り、性犯罪を減らすための取り組みを見直し、強化するきっかけとなる。また、加害者と被害者双方の心理的な側面にも注目を促し、加害者の心理状態や背景に対する深い理解は、再犯防止策を策定する上で重要な情報を提供する。
一方で、被害者の心理的なケアや支援も、彼らが経験したトラウマを乗り越え、健全な発達を促進するために重要である。 被害に遭った子どもたちの心のケアに加え、加害者の更生と再犯防止に向けた継続的なサポートと、そのための社会的な体制を強化することが、今後の課題として残されている。
また、このような事件が繰り返される背景には、日本の児童保護の不備と、孤立した子どもへの支援不足がある。社会が未成年者を適切に守れなかった結果、彼女は生存戦略として加害者との関係を受け入れるしかなかった。この構造が変わらない限り、同様の事件は繰り返される。
社会が未成年者を適切に守れる仕組みを作らなければならない。
◆参考資料
読売新聞2004年5月16日付
毎日新聞2004年5月16日付
毎日新聞2004年5月17日付
産経新聞2004年5月17日付
読売新聞2004年6月5日付
『女児連れ回し男初公判誘拐、恐喝とも否認千葉地裁』読売新聞2004年7月31日付
『小5女子児童誘拐男に懲役4年を求刑』読売新聞2005年3月26日付
『小5女児連れ回し被告に懲役2年6月「成育への悪影響重大」地裁判決』読売新聞2005年5月3日付
『10歳女児誘拐事件から13年幼女愛好男が「私はまた必ずやる」』週刊新潮2017年9月28日付
河合香織『帰りたくない―少女沖縄連れ去り事件―』新潮文庫,2010.
◆オススメ記事
◆戦後の沖縄で発生した事件



















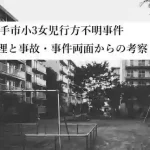







のアイキャッチ画像_edited-150x112.webp)