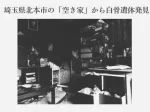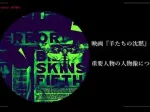AI技術の進化は、私たちの暮らしだけでなく、文化や創作のあり方すら根底から揺さぶろうとしている。映画やドラマの脚本はAIに学習され、俳優の顔と声はデジタルで複製され、知らぬ間に“もうひとりの自分”が画面の中で動き始める。
2023年、米国で起きた『WGA』と『SAG-AFTRA』による大規模ストライキは、こうした技術進化への警鐘であった。まさにそのタイミングで配信されたドラマ『ブラック・ミラー』シーズン6の一編「ジョーンはひどい人」は、フィクションの形を借りて、AIとエンタメ産業の摩擦点を鋭くえぐる作品となった。
本記事では、同作のあらすじとテーマを概観するとともに、ハリウッドのストライキ運動、AIと創作をめぐる法的・倫理的課題、さらには一般市民にまで開かれつつある「デジタル肖像の時代」について多角的に考察する。
※本記事には、ドラマ『ブラック・ミラー』“ジョーンはひどい人”の核心的なネタバレが含まれています。
AIは俳優、脚本家、クエイターの仕事を奪うか?
2023年5月、全米脚本家組合(WGA:Writers Guild of America)は、AIによる脚本の学習および制作への使用制限、ならびにストリーミング再生に応じた報酬体系の確立を要求し、ストライキに突入した。
これに続き、7月からは全米映画俳優組合=アメリカテレビ・ラジオ芸能人連盟(SAG-AFTRA:Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists)もデジタル肖像の無断使用や適正報酬の欠如に抗議し、ストライキを開始した。
ほぼ同時期の2023年6月15日、英国の人気SFドラマ『ブラック・ミラー』のシーズン6がNetflixにて配信開始された。その中の一編『ジョーンはひどい人』は、こうしたAI技術とデジタル肖像を巡る問題を鋭く風刺的に描いている。
『ジョーンはひどい人』のあらすじと要点解説
OTT(Over-The-Top)プラットフォーム「Streamberry」社は、インターネット経由で映像コンテンツを提供するサービス形態をとっており、量子コンピューターとディープフェイク技術を用い、8億人の利用者を主人公とする無限のドラマシリーズを制作する計画を進めていた。主人公のジョーンもその一人であり、彼女の日常は知らぬ間にドラマとして世界中に配信される。
ジョーン(演:アニー・マーフィ)は、大手企業に勤める管理職。職場では中間管理職として板挟みに苦しみ、私生活ではかつての情熱的な恋人と婚約者との間で心が揺れる。ある日、彼女は同社の新作『ジョーンはひどい人』が自分を模した内容であることに気づく。
ドラマでは、サルマ・ハエックがジョーン役を演じ、ジョーンの行動が過度に誇張されて描かれていた。誤解された言動が波紋を広げ、ジョーンは仕事、婚約者、友人すべてを失う。
契約書に目を通さず同社の利用規約に同意していたジョーンは、デジタル肖像の使用を合法的に許可していた。法的手段が困難と知った彼女は、サルマ・ハエックの倫理観に訴えかける反道徳的行為を実行することで、主演女優の協力を得ようとする。
やがて2人は連携し、同社の量子コンピューターを破壊すべく行動を開始。だが、そこで語られる驚愕の事実は、ジョーン自身もまたデジタル肖像による存在であるという現実を突きつける。 物語は第三のジョーンの登場とともに幕を下ろすが、それが現実なのか仮想なのかは明確にされない。視聴者に「自己とは何か」「現実とは何か」という問いを突きつける構造となっている。
ハリウッドストライキとAI規制の核心
全米脚本家組合(WGA:Writers Guild of America)と、全米映画俳優組合=アメリカテレビ・ラジオ芸能人連盟(SAG-AFTRA:Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists)のストライキは、AI技術の急速な発展に対し、創作者およびパフォーマーの権利が著しく損なわれる可能性への抗議として始まった。
WGAは、映画やテレビの脚本を手がける作家たちによって構成される組織であり、その目的は脚本家の労働条件の向上、作品の著作権の保護、報酬の適正化にある。一方、SAG-AFTRAは、俳優、声優、ラジオパーソナリティ、ダンサーなど、映像・音声メディアに関わるあらゆるパフォーマーを代表し、その職業的権利と地位を守るための活動を行っている。
脚本家にとっての最大の懸念は、AIが過去の脚本を大量に学習し、作家の創造性を模倣した新たな作品を生み出すことによって、自らの職能が希薄化し、報酬や雇用の機会が減少することである。これは著作権侵害のリスクを孕みながらも、現行の法制度では対応しきれないグレーゾーンにある。
俳優に関しては、AIによって自動生成されたエキストラや、本人の許諾なしに使用されたデジタル肖像(いわゆるディープフェイク)によって、実際の出演機会が奪われ、出演料の低下、さらには自分の顔や声が無断で利用されるリスクが深刻化している。
また、従来のDVD販売による一括収入モデルと異なり、現代のストリーミング配信では再生回数に応じた利益配分が主流となりつつあるが、その分配構造が透明性に欠け、出演者や脚本家の利益が十分に確保されていないという問題もある。そのため、両組合は、公平かつ持続可能な報酬体系の導入を求めている。
技術革新と社会ルールの再構築
AI技術の進化は、映画、テレビ、音楽、ゲームといったエンタメ業界の根幹そのものを揺るがす可能性を持っている。従来、人間の創造性と身体性に依存していた芸術表現や物語の創出が、機械によって模倣・生成されるようになれば、職能や文化的価値の定義も再考を迫られるだろう。
一方で、こうした新技術の出現を過剰に恐れ、全面的に拒絶する姿勢は、技術革新に対応できない社会の硬直化や、イノベーションの停滞を招きかねない。技術進歩は必然であり、問題はその利用の仕方と枠組みである。
よって、今求められるのは、AIや量子コンピューティング、ディープフェイクといった先端技術を前提とした、新たな法制度や労働契約、倫理規範の策定である。技術と人間社会が対立するのではなく、共生するための制度設計こそが急務であり、個人の尊厳と創造性を守るための枠組みが求められている。
デジタル肖像の民主化と新たな消費モデル
今後、一般市民が自らのデジタル肖像を活用し、個人的なドラマや映画を自在に制作・消費する時代が本格的に到来する可能性が高い。AIやディープフェイク技術、さらには低コスト化された合成映像編集ツールの普及により、プロフェッショナルな制作環境が個人にも開放されつつある。たとえば、憧れの俳優やアイドル、架空のキャラクターと自分自身が共演する映像を生成したり、歴史的事件や名作映画の世界に自らを投影することも技術的には十分可能となりつつある。
具体的には、AIが生成した映像の中で「推し」と共演し、恋愛や冒険、戦闘といったシーンを再現するほか、タイタニックの船上に立つ自分や、宇宙戦争で活躍するヒーローとしての自分など、従来では不可能だった体験が映像化され、視覚的に享受できるようになるだろう。また、それらは個人の趣味や感性に合わせたカスタマイズが可能であり、パーソナライズドな没入型エンターテインメントが新たな市場として発展することが見込まれる。
その結果、個人が物語の受け手である消費者から、主体的に物語をつくりあげるコンテンツ創造者へと変化する「共演型コンテンツ市場」が形成され、新しい形のエンタメ経済圏が誕生するかもしれない。
また、AIを用いて既に死亡した俳優や歴史上の著名人の肖像を再現し、映像作品を制作する動きも現実のものとなりつつある。技術的には過去の写真や映像をもとに精巧なデジタル肖像を生成し、かつての俳優を新作映画やCMに「出演」させることが可能になっている。
しかしながら、こうした試みは「死後の肖像権」や「パブリシティ権」といった法的課題を伴う。日本では死後の肖像権について明確な法規定は存在しないものの、著名人の遺族や権利管理団体が商業的使用に対し抗議・訴訟を起こす事例はすでに存在する。
特に米国などでは、パブリシティ権が財産権として相続される場合も多く、無許可での使用には高額な損害賠償が科される可能性がある。
さらに、本人の意図や価値観と反するような役柄で使われた場合、倫理的問題も顕在化するだろう。今後、こうしたデジタル再現に関しては、生前に「AI使用の可否」を明示する契約=デジタル遺言のような制度が必要になる可能性が高い。これは、AI時代の文化的・法的インフラの整備として、今後の議論が不可欠な領域である。
まとめ:『ブラック・ミラー』が描く問いと未来
『ジョーンはひどい人』は、AIとデジタル肖像の問題を題材にしつつ、「現実とは何か」「自己とは誰か」「認識とは何か」というSFの普遍的テーマを内包している。
登場人物たちが直面する「自分自身が誰かを知らない」「映し出される自分が本物かどうかわからない」といった葛藤は、まさに私たちが情報化社会において日々感じているアイデンティティの揺らぎを映し出している。
情報が氾濫し、SNSや仮想空間において複数の「自己」を演じることが常態化する現代において、この作品の提示するテーマはフィクションという枠を超えて観る者に突き刺さる。
これらのテーマは、1999年公開の『マトリックス』や2021年公開の『フリー・ガイ』といった作品でも繰り返し描かれてきたが、もはやそれは映画の中の空想ではなく、私たちが日常の中で直面しはじめている現実そのものである。
AIによって生成された自分の顔、音声、人格が現実の自分よりも多くの人に消費され、他者によって「定義される」存在としての自己が浮上してきている。果たして「本物の自己」とはどこに存在するのだろうか。
また、他者にとっての「私」が、AIやアルゴリズムによって最適化され、加工された虚像であるとすれば、私たちはもはや自分のイメージを自分でコントロールできない。これは単なる技術的問題ではなく、現代人の精神構造そのものを揺るがす重大な問いでもある。
かつては「鏡」によって確認されていた「私」という存在が、今やアルゴリズムや他者の視線を通してしか把握できないという状況が生まれている。
このように、現代のテクノロジー社会は、個人のアイデンティティと現実の構造そのものを再定義するフェーズに入っている。『ジョーンはひどい人』はその渦中にあって、我々に静かに、しかし確実に警鐘を鳴らす。
――深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ――(フリードリヒ・ニーチェ『善悪の彼岸』より)
『ジョーンはひどい人』は、その深淵の入口に我々を立たせ、問いを投げかけてくる。
◆参考資料
『アメリカの俳優労組がストライキ、過去43年で最大規模映画イベントなどに影響も』BBCNEWSJAPAN,2023年7月14日配信
◆SF映画・漫画・アニメから考察する時事問題
◆ダークな世界、社会派映画・ドラマ