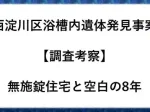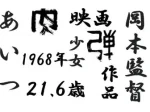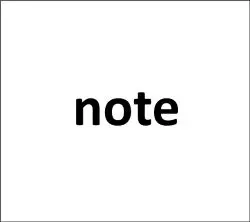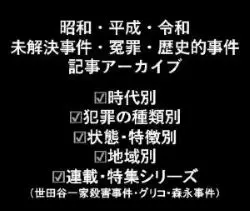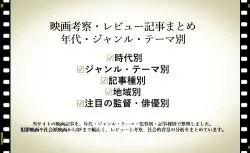永遠の異邦人フランツ・カフカ(Franz Kafka)
20世紀の初め――ドイツのナチ政権が欧州を征服する前―1924年6月3日、一人の人間がこの世を去った。彼は1883年7月3日、現在のチェコ共和国の首都「プラハ」のユダヤ人家庭で長男として生まれ、成人になると公務員的な職業に従事した。彼の名前はフランツ・カフカ(Franz Kafka)20世紀を――いや、人類を――代表する作家の一人だ。
彼が生まれた当時のプラハは、オーストリア=ハンガリー帝国に支配されていた。彼の厳格な父親はチェコ語を話し、母親はドイツ語を話した。彼の生まれたチェコ(ボヘミア)は、1918年にドイツ系のオーストリア=ハンガリー帝国から独立を成し、スラブ系のチェコスロバキア共和国が誕生する。
ドイツ系民族が支配するスラブ系民族の居住地域に生まれたユダヤ人のカフカ。チェコ語を話すユダヤ人父親とドイツ語を話すユダヤ人母親の間に生まれた永遠の異邦人のカフカ――彼の作品には「鳥を探す鳥籠」の話もある――このような背景を持つカフカには『変身』『審判』『城(この作品は未完)』『アメリカ』などの長編作品や『変身』など有名な中編作品もあるが――カフカは謎めいた多くの短編作品を人類に遺してくれた。
写真はビーチで撮影されたカフカと友人マックス・ブロートといわれる。2人はプラハ大学在学中に知り合い、友人関係は1924年カフカが31歳の若さで他界するまで続いた。
カフカは自分の死の後には原稿を焼却するよう遺言するが、友人マックス・ブロートはカフカの遺言を破り『審判』『城』など人類を代表する傑作を世に送り出した。
このマックス・ブロートの誠実な裏切りに感謝したい。
今回はカフカの短編傑作『家のあるじとして気になること(『父の気がかり』)』『雑種』に登場する二つの奇妙な「命」、オドラデクと羊猫について考察したいと思う。
オドラデク あらすじと考察
チェコスロバキア共和国誕生の前年の1917年に書かれた『家のあるじとして気になることDie Sorge des Hausvaters』には、カフカが創り出した奇妙な、そして、有名なオドラデクが登場する。
『家のあるじとして気になること』の冒頭は以下のとおりだ。主人公が「オドラデク」と呼ぶこの奇妙な「命」の名前の由来について述べているが、その言葉の起源は、はっきりわからない。そして、このオドラデクという名前を誰が名付けたかもわからない。そもそも、このオドラデクという奇妙な「命」が「いつ」からこの世界にいるのかもわからない。
第一の説。オドラデクという言葉はスラブ語が起源で、それは語形からも明らかだとされている。第二の説。ドイツ語こそが起源であり、スラブ語はその影響を受けたにすぎない。いずれにせよ、どちらの説も頼りない。とりあえずもっともらしく考えるとすれば、どちらも的はずれで、そもそもそんなことをしても、この言葉の意味がわかるわけではない、となる。
家のあるじとして気になること フランツ・カフカ 大久保ゆう訳 青空文庫
なお、「オドラデク」という言葉はチェコ語の動詞”odraditi”(いさめる)からつくられた造語とのヴィルヘルム・エンリヒ(1909-1998)の仮説もあるが、カフカ自身はオドラデクについて何も語っていない。
オドラデクの見た目は、ぼろぼろの糸が巻き付いた星型の糸巻きのような形だ。その星型の糸巻き状の身体からは一本の短い棒が出ている。そして、この短い棒には、この棒と垂直な棒がついており、その垂直な棒と星の一つの角を利用して二本足のように歩き回る。動きは俊敏であるが、まったく動かないこともある。オドラデクは主人公の家に「いる」。いつからいるのかはわからないが、「いる」。だが、数か月にわたり姿を見せないこともある。また、オドラデクは、主人公と会話らしきこともでき、主人公の質問に答えることもあるが、何も答えないこともある。そして、「肺を使わずに笑う人」のように笑うこともある。
この正体不明なオドラデクと暮らす主人には不安がある。
どうでもいいことだが、わたしはこう考えてみるのだ。これから先、やつはどうなるのだろう。死ぬことがあるのだろうか? 死ぬものはみな、あらかじめ何らかの目標を持ち、何らかのやることをかかえている。そして、そのためにあくせくする。だがオドラデクの場合、こういったことが当てはまらない。もしかすると、やつはこれからも先、わたしの子どもや孫の足下で、糸をだらりとひきずりながら、かさかさ鳴くというのだろうか? そりゃむろん、やつが誰にも害をなさないということはわかっている。だが、ぼんやりと、やつがわたしの死んだあともやっぱり生きているにちがいない、などと思うと、わたしはどうも悩ましくてしかたがない。
家のあるじとして気になること フランツ・カフカ 大久保ゆう訳
一家の長である主人公は、自分が死んだ後もオドラデクが生きることに不安を持っている。その不安はなんだろう?主人公はオドラデクを排除しない。主人公はオドラデクの不思議な容姿に怯えるているわけでもない。オドラデクの肺の無い人のような笑い声に耐えられないわけでもない。主人公は永遠に生きるかもしれない存在に不安を持っている。
主人公の思う「命」は、本来、目的を持ち、その目的のために「あくせく」しながら生き、死んでいくものだが、オドラデクには生きるための目的が「無い」ように見える。だからこそ、永遠に生きるのではないか?目的も無く生きることはオドラデクにとって幸福なことなのか?目的も無く永遠に生きる可能性があるこの不思議な「命」オドラデクを子や孫に相続したとして子や孫は受け入れられるのだろう?
主人公には三つの不安があるのかもしれない、一つはオドラデクを次代への負の遺産として考える家長の立場での不安。
もう一つは、説明可能で有限な存在である人間には理解できない非合理的で無限な存在に対峙した人間としての不安。
最後の一つは、目的も無く永遠に生きる可能性のあるオドラデクに対する父親的な心配からの不安。
『雑種』羊猫 あらすじと考察
カフカの短編『雑種』は、半分が猫、半分が羊という奇妙な「命」とその奇妙な「命」を父親からの唯一の遺産として相続した男性の話である。
この奇妙な「命」に名前はない。父親の遺産として相続した当初は、猫の特徴よりも羊の特徴が強かった。その後、この奇妙な「命」の見た目や仕草にある羊と猫の割合が半々となり、さらに犬のように甘える仕草をしたり、人間のように共感の涙を流しているようにも見えたりと――主人公はこの奇妙な「命」から様々な動物の特性を感じ取る。
主人公はこの奇妙な「命」の涙を流すように見えるなどの仕草から感じる人間的な心――共感性する心―から父親からなかなか良い遺産を相続したなどと考えている。
そして、主人公はこの奇妙な「命」の「命」の終焉の時まで面倒をみようとも思うが、この奇妙な「雑種」から感じる人間的な振る舞いや思慮深げな目を前にすると――この奇妙な「雑種」から肉切包丁を使って「当然の処置をしてくれ」とせがまれているように感じ――物語は終わる。
ただし、当然だが、この奇妙な「命」と主人公のその後は書かれていない。この奇妙な「命」と主人公はどうなるのか?これこそカフカが我々へ与えた命題の一つかもしれない。
『家のあるじとして気になること』『雑種』カフカの宇宙の二つの命
20世紀を代表する作家カフカの短編『家のあるじとして気になること』と『雑種』には、2つの奇妙な「命」が登場する。この二つの奇妙な「命」の所有者(同居人、飼い主)の立場はそれぞれに違う。
オドラデクの同居人は次代への相続に懸念を感じる父親。
羊猫の同居人は父親からなかなか良いものを相続された息子。
また、この二つの奇妙な「命」にも違いがある。
- オドラデクには由来は不明だが「オドラデク」という名前がある。
- 羊猫には名前がない。
- オドラデクはコミュニケーションを好まない。
- 羊猫には共感性があるように思われる。
- オドラデクの命は無限だと思われる。
- 羊猫の命は有限だと思われる。
- 小説『オドラデク』の主人公は被相続人である。また、他の家族や近隣住民は登場しない。
- 小説『雑種』の主人公は相続人である。また、他の家族は登場しないが、近所の子ども達が登場する。
カフガが創造した二つの奇妙な「命」とその「命」の所有者(同居者、飼い主)が感じた不安。主人公はカフカの分身なのか?この二つの奇妙な「命」こそカフカの分身なのか?それとも、二人の主人公と二つの奇妙の「命」の両方ともがカフカの分身なのか?
カフカはそれらを答えない。それらの答えは読む側に委ねられ、幾多の答えが生まれてきた。
だからこそ、カフカの抱いた個人的な不安が人類共通の不安へと昇華し、時代と国境を越え多くの人の心に響くだろう。
カフカは自分の死後、書き溜めた多くの作品を破棄するように遺言したといわれている。だが、その遺言は誠実な友人達により裏切られ、人類はカフカの偉大な作品を相続することができた。
自分が創り出した作品を死後に破棄するよう遺言したカフカ。なぜ、カフカは自分の作品が人類に相続されることを拒んだのだろうか?カフカにとって自分の作品はオドラデクのような存在だったのか?羊猫のような存在だったのか?自分の作品に不安を感じていたのだろうか?
最後にオドラデクと羊猫の共通点を一つだけ上げてみよう。
それは、この二つの奇妙な「命」に同族はいないということ。
そして、カフカがなぜ、遺稿を焼却しようと考えたのか、それを考え続けたい。永遠に答えは出ないが――それこそがフランツ・カフカだ。
★参考、引用文献
カフカ短篇集 岩波書店 (1987/1/16)池内紀
※写真 ビーチのカフカとマックス・ブロート
解説: Franz Kafka and Max Brod on the beach. Date unknown.
日付:1907年
原典:リンク先1976年の創刊のスペイン日刊新聞『El País(エル・パイス)』
作者:不明
あなたにお薦めの記事 独自視点の文学 考察シリーズ