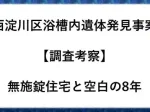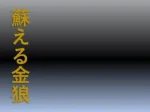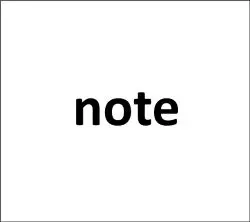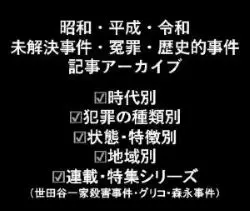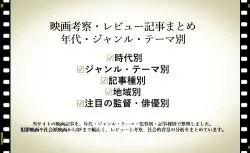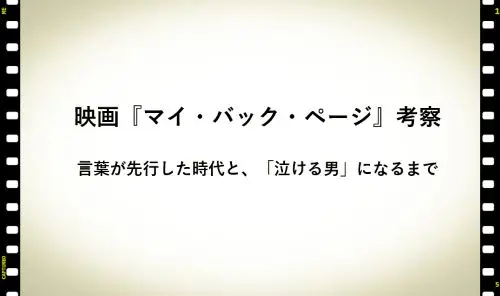
1970年代初頭、日本では「革命」という言葉が、まだ生きているように見えていた。
だが同時に、その言葉はすでに現実から乖離し始め、誰かの人生を照らすよりも、誰かを縛り、追い立てるものへと変わりつつあった。
映画『マイ・バック・ページ』(2011年)は、そうした時代の終わり際に立ち会った若き記者の視点から、言葉と行動、理想と生活のあいだに生じた致命的なずれを描いた作品である。
本作が扱うのは、武装闘争の成否でも、思想の正しさでもない。
むしろ、「語った言葉を、誰が、どこまで引き受けたのか」という問いそのものだ。
作中で繰り返し問われるのは、「人間である」とはどういうことか、という一見単純で、しかし危険な問いである。
理念の名のもとに他者の人間性を切り捨てることと、絶望や弱さを自分自身の内部で引き受けること――その分岐点に、本作の登場人物たちは立たされている。
本記事では、映画『マイ・バック・ページ』を、実際の事件の再現や時代総括としてではなく、言葉が先行し、人がそれに追いつこうとしたとき、何が失われ、何が取り残されたのかを描いた物語として読み解く。
理念の時代を通過したあとに、なお人が生きていくために残されていたもの――その輪郭を、静かに見つめ直していこう。
映画概要
映画『マイ・バック・ページ』は、2011年に公開された日本映画である。原作は、川本三郎によるノンフィクション作品『マイ・バック・ページ ある70年代の物語』(平凡社)。
1970年代初頭に実際に起きた『朝霞自衛官殺害事件』と、その周縁にいた若き記者の体験をもとに書かれた同書を、映画として再構成した作品である。
監督は山下敦弘、脚本は向井康介。主人公・沢田雅巳を妻夫木聡が演じ、武装闘争を志向する若者・梅山(片桐優)役に松山ケンイチ、『週刊東都』の先輩記者・中平武弘役に古舘寛治、雑誌表紙モデルであり、沢田に異なる価値観を提示する女子高校生・倉田眞子役に忽那汐里が起用されている。
本作は、2011年の第84回キネマ旬報ベスト・テンにおいて、日本映画ベスト・テン第3位を獲得するなど、批評的にも高い評価を受けた。
映画『マイ・バック・ページ』は、実在の事件を背景に持ちながらも、事件そのものを説明する映画ではない。
言葉が現実を先行し、役割が人を縛り、やがて取り返しのつかない地点へと押し出していく過程を、ひとりの記者の視点を通して描いた、時代と人間の距離を問う物語である。
あらすじ
東大安田講堂が陥落し、政治の言葉は摩耗し、運動は内向きになり、「革命」という語が現実感を失いつつあった1970年代初頭――『週刊東都』編集部の記者・沢田雅巳は、学生運動の熱が冷めつつある時代の空気のなかで、次の取材対象を模索している。
そんな折、沢田は編集部の先輩・中平武弘から、武装闘争を志向する若者グループの中心人物・梅山(本名:片桐優)を紹介される。
沢田の目に、梅山は、既存の左翼運動を批判しながらも、なお「本物の革命」を信じようとする若者として映る。
その語る言葉は過激で、粗削りでありながら、どこか切実で、時代から取り残された若者の焦燥を帯びていた。一方で、年長者である中平は、梅山の言葉のなかに拭いがたい欺瞞を感じ取っている。沢田は記者として、梅山の言葉に耳を傾け、記事として記録していくなかで、取材は次第に距離を縮め、観測と共感の境界は曖昧になっていく。沢田自身もまた、冷めきれない何かを胸に抱えながら、梅山たちの語る「行動」に引き寄せられていく。
出典:シネマトゥデイ映画『マイ・バック・ページ』予告編
一方で梅山たちは、言葉だけでは満たされなくなっていく。語った理想に追いつくため、彼らは行動を求め、後戻りできない地点へと踏み込んでいく。革命はもはや理念ではなく、自分たち自身を縛る約束へと変わり始める。
やがて、「言葉よりも暴力」を主張する梅山たちは、取り返しのつかない事件を起こす――。
映画『マイ・バック・ページ』は、本来は「社会の目」であるはずの記者・沢田雅巳が、その視点を失っていく過程として描いた物語である。
安田講堂陥落(1969年)、三島由紀夫の自決(1970年)を経て、歴史の大きな物語を傍観するしかなかった者、そこに間に合わなかったと感じる者、そして新たな目的を見出せないまま1970年代を生きる若者たちが、「時代に爪痕を残したい」という普遍的な欲求を抱え、その行き場を失い、挫折へと向かっていく姿そのものである。
登場人物解説
本作に登場する人物の多くには、実在のモデルが存在する。しかし本記事では、実在のモデルに関する詳細な解説はできるだけ控え、映画のなかで描かれる彼らを、それぞれが固有の内面と選択を持つ「独立した人物」として扱う。
なぜなら本作は、史実を再構成するドキュメントではなく、登場人物たちの言葉と行動、そして時代と再出発を描くための物語だからである。
沢田雅巳:本物であろうとした記者
主人公の沢田雅巳は、1969年春に入社した新人記者であり、東大法学部卒という経歴を持つ。本来の希望は、左翼雑誌として評価されていた『東都ジャーナル』だったが、彼が社会に出た時点で、全共闘運動はすでに衰退局面にあり、政治の現場はもはや「流行り」の対象ではなくなっていた。
沢田が任されるのは、500円だけを持って東京を放浪する企画『東京放浪日誌』など、運動の中心から距離のある仕事である。
彼は取材の際、偽名と偽の身分を用いて露天商やフーテンといった社会の辺境に生きる人々と接するが、そこに身を置きながらも当事者にはなりきれず、常に観察者である自分自身に対する後ろめたさを抱えている。
安田講堂の陥落を遠くから眺め、社会の辺境に観察者として立ちながら、大人になりきれないセンチメンタルな感情を抱え続ける沢田が、『京西安保』メンバーを名乗る梅山にシンパシーを感じたのは、必然だったのかもしれない。
梅山(片桐優):何者かになろうとした演者
梅山は、武装闘争を志向する若者グループの中心人物として登場する。しかし彼は、いわゆる職業的な活動家ではない。
日大で『哲学芸術思潮研究会』を立ち上げるものの、その活動は思想的に体系化されたものとは言いがたい。
梅山は、猟銃店を襲い銃と弾薬を強奪した『京西安保』のメンバーであると偽り、沢田に接近する。革命や東大紛争の英雄に憧れながらも、彼は一貫して、自分が何をしたいのかを言語化できていない。
梅山の周囲には『赤邦軍』のヘルメットが置かれ、毛沢東やチェ・ゲバラのポスターが貼られているが、それらは思想の表明というよりも、自分を大きく見せるための装飾であり、どこか「革命を装うための仮装」の道具のようにも映る。
自衛隊から銃を奪うことを目的とした『朝霞自衛官殺害事件』の決行の日、梅山は食事をしながら漫画を読んでいる。そこには、極端な行動と、拍子抜けするほどの罪悪感の欠如が同居している。
梅山は、映画『真夜中のカーボーイ』(1969年)のダスティン・ホフマンが涙を流す一場面を引き合いに出し、「あれは僕だ」と語る。しかし、その言葉が彼の本心に根ざしたものなのかどうかさえ、定かではない。
その落差は、彼が覚悟の化身ではなく、理想の自分を演じ続けるために、自らその役割へと踏み出していった人物であることを雄弁に物語っている。彼は、言葉と流行によって作り上げた自分自身の像から、最後まで降りることができなかった。
その意味で梅山は、行動に突き進んだ者というよりも、自己像を維持するために、行動を演じ続けてしまった人物なのである。
映画『マイ・バック・ページ』の二つの言葉
映画『マイ・バック・ページ』には、物語全体の倫理的な緊張を象徴する二つの言葉がある。
それは一見、誠実で、人間的で、暴力とは無縁に見える言葉だ。
しかし本作は、それらの言葉がどのように現実と接続され、いかなる矛盾や断絶を生み出したのかを、静かに描き出している。
以下では、「人間である」という言葉が孕んだ決定的な矛盾と、「泣ける男」という言葉が示す、もう一つの分岐点について検討する。
“人間である”という言葉が生んだ決定的な矛盾
一つは、沢田雅巳と『週刊東都』の先輩記者・中平武弘との会話に登場する、――ジャーナリストの前に、人間だろう――という言葉である。
この一言は、冷静な「社会の目」として事象から距離を保とうとする職業「ジャーナリスト」への批判であり、同時に、理念や理想、党派性に回収される以前にあるはずの「人間性」への回帰を促す言葉として響く。
立場よりも良心を、役割よりも感情を。
その主張自体は、きわめて誠実に見える。
しかし、この映画が扱う現実を踏まえたとき、この言葉は避けがたい矛盾を孕む。
映画『マイ・バック・ページ』の背景にある『朝霞自衛官殺害事件』において、殺害されたのは「国家」でも「体制」でもない。それは、職業として自衛官であった、一人の人間である。
彼は、一人の人間として生活を持ち、家族を持ち、固有の人生を生きていた存在だ。それは、考える余地のない事実だろう。
それにもかかわらず、事件に至る思想の内部では、その人間性は意図的に剥奪されていく。「自衛官」という属性、「国家装置の一部」という記号によって、個人は抽象化され、敵として再定義されてしまう。その結果、「人間のための正義」を強く語っていたはずの思想が、別の「人間」を殺害するという行為へと帰結した。
ここにあるのは、単なる倫理の破綻ではない。より正確に言えば、「人間」という言葉の独占が生んだ、論理の強制的な切断である。
革命思想において、「人間である」という言葉は、普遍的な概念として機能していなかった。それは、苦悩し、迷い、理想に殉じようとする「自分たち」を指す言葉として用いられ、その外側にいる者――国家に属する者、役割を担う者――は、あらかじめ人間性を剥奪された存在として扱われた。
つまり、「人間であること」は他者を包摂する言葉ではなく、自分たちの内側だけを温める免罪符として機能していたのである。
映画は、この矛盾を明示的に断罪しない。活動家たちは、冷酷な狂人としてではなく、むしろ傷つきやすく、不器用で、どこにでもいそうな若者として描かれる。彼らは確かに悩み、迷い、「人間であろう」としていた。
だが、その「人間性」は外側に向けては開かれなかった。結果として、「人間を回復しようとした試み」は、「別の人間性を破壊する行為」へと反転していく。
泣ける男:弱さを引き受ける者と、押しつける者
もう一つ印象的な言葉がある。
『週刊東都』のモデルとされる倉田眞子の、――わたしは泣ける男が好き――という台詞だ。
泣くという感情を抑えることこそが男らしさだと考える沢田雅巳に対し、彼女は、『ファイブ・イージー・ピーセス』(1971年)や『真夜中のカーボーイ』(1969年)に登場する男たちの姿を重ねながら、人間的な弱さをさらけ出す在り方を語る。
倉田眞子の語る「泣ける男」は、弱さや挫折を他者に転嫁しない存在である。それは、絶望や恐怖、悲しみを、暴力へと変換するのではなく、自分自身の内部で引き受ける姿勢を意味している。
実際、彼女のモデルとされる女優・保倉幸恵は、22歳という若さで自ら命を絶っている。
その理由は明らかではなく、この行為の是非を論じる立場に本記事はない。だが少なくとも、それは、他人の命を代償として差し出す選択ではなかった。
梅山たちが、思想の内容ではなく「行動によって言葉を完結させた存在」として、憧れの対象とした三島由紀夫が、最終的に選んだのもまた、同じ方向であった。
彼は、自らが語り、掲げた思想と、その行き着く先にある絶望のすべてを、自分自身の身体で引き受けた。
それに対し、梅山たちが選んだのは、自分たちの「人間性」を証明するために、別の人間の「人間性」を奪うという行為だった。
まとめ
映画の終盤、沢田雅巳は犯人隠避の罪で懲役10月、執行猶予2年の有罪判決を受け、新聞社を去る。理想と理念を信じ、それに殉じようとした若き記者は、「社会の目」の役割を失い、ただの一個人として都市をさまようことになる。
その彼が、偶然立ち寄った居酒屋で再会するのが、かつて「500円だけを持って東京を放浪する企画『東京放浪日誌』」の取材で出会った元露天商のタモツである。
タモツは、沢田の本名も知らない。彼が事件に関わったことも、新聞社を辞めたことも知らない。
彼は、結婚し、子どもを持ち、店を切り盛りしながら、生活を続けている。そこには理念も、革命もない。あるのは、日々の労働と、家族と、酒と、食事という、ごく平凡な時間だけである。
沢田は酒を飲みながら、涙を流す。それは敗北の涙でも、後悔の涙でもない。かつて彼が軽視し、見落としてきた「生活」が、目の前に確かに存在していることに気づいた瞬間の涙である。
理想や理念は、人を熱狂させる。だが、誰かと食事をし、子どもを育て、店を続けるという営みは、声高に語られることなく、ただ静かに人間の「歴史」を支え続けている。
沢田が最後に見つめたのは、思想ではなく、物語でもなく、誰かの生きた人生そのものだった。そのとき彼は、はじめて「泣ける男」になったのだ。
それは、弱さを他人に押しつけないこと。
絶望や恐怖を、暴力へと変換しないこと。
そして、「人間である」という言葉を、誰かの排除のためではなく、生活の側から引き受け直すという選択である。
『マイ・バック・ページ』が最後に差し出すのは、革命の失敗談でも、青春の挫折譚でもない。
それは、理念の時代を通過したあとにしか辿り着けない、静かで、もしかすると手遅れだったかもしれない「人間性」の回復である。
――生きてればいいよ――
沢田を肯定も否定もせず、疑いさえもしないタモツの何気ない一言が、酒とともに沢田の心に沁み込み――彼は、ただ肩を震わせて泣ける男になった。
◆関連記事
◆報道と映画・ドラマ
◆社会派の日本映画・ドラマ