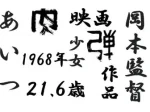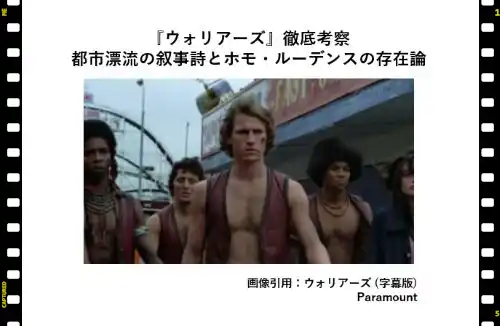
1979年に公開された映画『ウォリアーズ』(The Warriors)は、単なるギャング映画の枠を超え、都市空間・制度・共同体の解体と再構成というテーマを孕んだ、神話的構造を有する作品である。
本記事では、古典ギリシャ文学『アナバシス』(クセノポン著)との構造的共鳴を手がかりに、都市という「場」における排除と越境、漂流と帰還の意味を考察する。
また、ヨハン・ホイジンガの「ホモ・ルーデンス」や、ジョルジョ・アガンベンの「ホモ・サケル」といった哲学的概念を援用し、スワンをはじめとする登場人物たちが、いかに「例外状態」の都市空間を通過し、遊戯的主体として新たな関係性と時間性を創出していくかを分析する。
都市空間、暴力、共同体が交錯する本作は、ポストモダン都市における実存的倫理の寓話といえるだろう。
カルト的人気:映画『ウォリアーズ』概要
映画『ウォリアーズ』(原題:The Warriors)は、アメリカ・ニューヨークを舞台に、ギャング集団「ウォリアーズ」が敵対勢力の追跡を受けながら、拠点であるコニーアイランドへの帰還を目指す一夜の逃走劇である。
本作はソール・ユーリックによる1965年の同名小説を原作とし、その物語構造は古典ギリシャ文学『アナバシス』(クセノポン著)に着想を得ている。監督ウォルター・ヒルの演出は、1970年代アメリカにおける都市の荒廃と暴力的混沌という社会的リアリティを反映しつつ、その都市空間を制度的秩序の崩壊後に出現する『例外状態』として描き出している。
これにより、単なる逃走劇にとどまらず、荒廃した「都市空間」が神話的帰還譚の「舞台」へと変貌を遂げる構図が浮かび上がる。
公開当時は暴力描写が一部観客の過激な反応を招き、上映中止となる劇場もあったが、次第に本作はカルト的評価を獲得する。
視覚的に洗練された美術設計、ギャングたちの象徴的なコスチューム、秩序崩壊後の「都市空間」という舞台装置が結びつき、神話的構造とサブカルチャー的感性が高密度で融合した、極めて特異な作品世界が形成されている。
あらすじ:ギャング神話としての「帰還」と「脱出」の構造
物語は、ニューヨーク・ブロンクスのヴァン・コートランド・パークにおいて、休戦協定のもと、各地から選抜された約100組のギャング・チームの代表者たちが一堂に会する大集会から始まる。
この集会で、カリスマ的指導者セイリス(最大勢力「グラマシー・リフス」のリーダー)は、抗争の終結と、総勢6万人に及ぶギャング勢力の連合化を提唱する。その目的は、既存の支配勢力であるマフィアおよび約2万人の警察力を凌駕し、都市の実効支配を確立することであった。
しかし演説の最中、セイリスは突如として暗殺される。犯人は「ローグス」の首領ルーサーだった。彼の行動には、明確な動機も組織的利害も見出せず、あたかも秩序の成立そのものを嘲笑うような、逸脱的で衝動的な暴力だった。この無意味な犯行の責任は、理不尽にもその場に居合わせた辺境的ギャング「ウォリアーズ」に押しつけられる。
リーダーのクリオンは直後に他のギャングに捕らえられ、残された8名のメンバーは、新たに指揮を執るスワンのもと、ニューヨーク市内を縦断しながら自らの縄張りであるコニーアイランドへの帰還を目指す。
この逃走劇は、単なる生還の物語ではない。断片化された都市の主権構造を彷徨い、暴力と身体性の連鎖を経て進む彼らの旅は、まさに「選別的生存」の過程である。
物語終盤、真の加害者が露見し、ウォリアーズの冤罪は晴らされる。しかし彼らが手にするのは、社会的回復や名誉ではなく、ただ「帰還の達成」という最小限の生存経験にすぎない。スワンは帰還を果たしたコニーアイランドにおいて、同行してきた女性マーシーに対し、この地を離れる意志を語る。マーシーもまた、その選択に共鳴し、未来を共にする姿勢を見せる。
この「帰還」は、単なる原点回帰ではなく、もはや荒廃の象徴と化したコニーアイランドを経由し、都市との関係を再定義する通過儀礼である。とりわけスワンにおいて、その意味は際立っている。彼は逃走の過程を「刹那的な暴力のゲーム」として消費することなく、終始、帰還という目的の完遂を優先しつづけた。そして、都市空間との関係を未来志向で見据えていた。
一方、他のメンバーたちは、物語の随所で感覚的快楽や衝動的欲望に支配される場面を見せる。女性刑事による囮捜査に軽率に引っかかり、あるいは女性ギャングの誘惑と罠に陥るなど、都市空間を一過性の享楽の場として反射的に消費する彼らの姿勢が描かれている。
これらの描写は、明確な目的意識と一貫した倫理観を保持し続けるスワンとの対照構造を浮き彫りにし、物語における中心的主題の一つを強調していると言えるだろう。
『ウォリアーズ』という神話:物語構造と暴力の意味
映画『ウォリアーズ』は、ニューヨーク都市圏の異邦的領域を横断しながら、拠点であるコニーアイランドへの帰還を目指す過程を描いている。
しかし、この空間的移動は単なる都市内の地理的遷移にとどまらない。それは、神話的時間を内包しつつ、通過儀礼として構造化された、社会批評的なメタフィクションである。
本章では、本作に潜在する「神話性」と、そこにおける暴力の意味作用を検討し、ギャングという存在を単なる逸脱者ではなく、社会的主体として再評価するための理論的枠組みを提示する。
ギャング映画か?それとも現代の叙事詩か
映画『ウォリアーズ』の構造は、ホメロス的叙事詩に典型的な三幕構成――すなわち「出発」「試練」「帰還」――に厳密に準拠しており、この意味において本作は、クセノポンの『アナバシス』と明確な構造的対応関係を有している。
都市という異郷=敵地からの離脱と、同胞の待つ故郷=「自己の共同体」への回帰という運動は、単なる地理的移動ではなく、儀式的な物語構造――いわば「帰還譜」――として成立している。
この「帰還譜」とは、敵意と暴力に満ちた環境下で連続的に課される通過儀礼の連鎖を意味し、登場人物たちのアイデンティティと生存可能性を更新する装置として機能する。彼らが通過する各エリアは、それぞれ異なる暴力の形象と権力構造に支配されており、その旅程は、都市空間における文化的異物性と自己の立ち位置を反復的に映し出す場となっている。
本作において彼らは、覇権や貨幣的利益の追求者ではない。むしろ、冤罪による暴力的死からの逃走と、共同体的空間への回帰という、生存それ自体を主目的とする存在である。
この運動は、勝利者の凱旋ではなく、近代的制度秩序から排除された敗者たちの神話であり、都市的暴力装置に抗しながら遂行される「儀式的移動」としての意味を帯びる。
このように捉えるならば、『ウォリアーズ』は、断片化された都市空間を巡るサバイバルの旅を通じて、「共同体的帰属の再獲得」という現代的テーマを、古典的叙事詩の枠組みの中で再演する試みと位置づけることができる。
都市を遊ぶ者たち:『ウォリアーズ』におけるホモ・ルーデンスと制度外の倫理
映画『ウォリアーズ』の構造は、深い象徴性と社会構造の暗喩を孕んでいる。物語は、カオス的な都市空間の中をひたすら本拠地に帰還しようとする一団の旅路を描きながら、現代都市における遊戯的共同体の成立と崩壊、あるいはそれを生きる者たちの美学を浮かび上がらせる。
彼ら「ウォリアーズ」は、ヨハン・ホイジンガが『ホモ・ルーデンス』で示した「遊びこそが文化の起源である」という視点に照らせば、既存の規範や階層秩序の外側で独自のルールと美意識を体現する遊戯的主体として捉えられる。また、日本における応用例としては、宮崎学のいう「愚連隊=ホモ・ルーデンス」という視座が想起される。
『ウォリアーズ』のギャングたちは、制度的統治の網目をすり抜け、かつての国家的共同体や家族といった帰属単位を持たずに都市空間を漂流する。この意味で彼らは、「例外状態」に置かれたホモ・サケルであり、同時に新たな遊戯的共同体(ルーデンス)を形成するポテンシャルを秘めている。
このように、『ウォリアーズ』は、都市における遊戯性、共同体の生成、排除と越境、暴力と美の倫理といった主題を交差させながら、単なるアクション映画の枠を超えて、ポストモダン都市における実存的闘争を描き出しているといえるだろう。
まとめ:出来事としての都市、漂流する主体『ウォリアーズ』の時間性と存在論
映画『ウォリアーズ』が提示するのは、制度的秩序が失効した都市という「場」を舞台に、法の外部を漂流する主体が、自らの時間性を更新していく出来事の物語である。
スワンを中心とするギャングたちは、暴力の連鎖と選別的排除のなかを移動するが、それは単なる逃走ではない。断片化された都市を縦断する過程で、彼らは生きるとは何か、属するとは何かを身体をもって問い直すことになる。
その運動は、制度秩序の外部に生じた「例外状態」の中で生成される、新たな関係性と応答可能性を通じた「出来事」であり、それが彼らの時間性を更新しうる「場」となる。
特にスワンの姿勢は顕著である。彼はこの旅を「刹那的な暴力の遊戯」として消費せず、あくまで「帰還=完遂」という時間的志向性を持って通過し続けた。だが、彼が最後に語るのは、帰還の完成ではなく、そこから再び旅立つ意思である。
スワンは、帰還によって閉じられるべき叙事詩の構造を逸脱し、既存の「場」——すなわち仲間たちと共有していたコニーアイランドという疑似的な家族的空間——から卒業し、マーシーという新たな関係と共に、未知の「場」の創出へと歩み出す存在として描かれる。
この姿勢は、現代における「場」の喪失と「時間」の無規定性を内在させた都市的生に対し、「出来事」としての生を肯定する立場を示唆しているといえそうだ。
映画『ウォリアーズ』は、もはや意味が約束されない都市空間において、それでも歩み続けようとする者たちの「存在論的倫理」を、神話形式のなかに封じ込めた「歴史」に遺る作品なのである。
◆60年代-80年代の海外映画考察