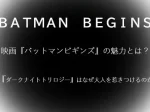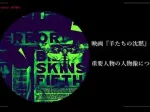2022年12月7日(現地時間)、ドイツ連邦検察庁は、クーデター計画の容疑により、旧貴族出身の71歳の男、極右政党関係者、Qアノン信奉者、元軍人らを含む21名を逮捕したと報じられた(参照:BBC NEWS JAPAN「ドイツ、クーデター計画容疑で25人逮捕」2022年12月7日配信)。
この報道から想起されるのは、かつてアドルフ・ヒトラーが主導した「ミュンヘン一揆」(1923年)と、現代ドイツにヒトラーが復活するという設定の風刺映画『帰ってきたヒトラー』(2016年日本公開)である。
映画『帰ってきたヒトラー』とは何か
本作『帰ってきたヒトラー』は、ティムール・ヴェルメシュによる同名小説(2012年発表、日本語訳は2014年河出書房新社刊)を原作とし、ダーヴィト・ヴネント監督により2015年に映画化されたドイツ作品である。
物語は、第二次世界大戦終結から数十年を経た2010年代のドイツに、ヒトラーが突如として蘇るという設定に基づく。復活したヒトラーは、テレビ関係者に発見され、やがて社会風刺的なテレビ番組の一企画として「ヒトラー芸人」として現代社会に送り出される。
興味深いのは、作品がドキュメンタリー的手法を用い、実在の市民や政治家と即興で対話を重ねるという形式を採っている点である。この手法により、観客はフィクションと現実の境界が曖昧になる中、現代社会における不寛容や不信、排外主義の萌芽を直視させられる構造となっている。
あらすじと分析:蘇ったヒトラーが照らす現代社会の歪み
2014年10月、ベルリン市内の旧総統地下壕跡地近くでテレビ撮影を行っていたザヴァツキは、突如現れたヒトラー風の人物と遭遇し、その様子を撮影する。失職中であった彼は、この映像をテコにテレビ局への復帰を試み、ヒトラー(本人)を現代ドイツ各地に同行させ、その様子を番組として収録していく。
後にヒトラーから小物扱いされるクリストフ・ゼンゼンブリンクは、憂さを晴らすかのようにフリー社員のザヴァツキに解雇を言い渡す。失意の中、自宅に戻り撮影した映像を確認するザヴァツキ。そこにはヒトラーに似た人物が映りこんでいる。ザヴァツキは、テレビ局への復帰を目指し、ヒトラーそっくりの「芸風」を持つヒトラー(本人)に現代ドイツを闊歩させる企画を練り2人はザヴァツキの母親の車に乗り撮影の旅を開始する。
ベルリン、ハンブルグ、ドイツ北部のズュルト、ドレスデン、ミュンヘン――撮影当初は、闊歩する目的だった企画が変化を遂げ、現代に蘇ったヒトラーが国民と政治的な会話をする企画となり、ヒトラー自身が現代ドイツ国民の政治への不満、生活への不満などを聞いて歩くようになる。
国民はヒトラーを前にしながら賃金の悩み、移民問題、難民問題、外国人嫌悪、外国人排斥、民主主義の問題、選挙への不信、政治家への不信、環境問題、愛国心などを語り、問題解決のために「収容所が必要だ」「移民を追い出せ」などという者もいる。勿論、現代に現れたヒトラーにドイツのためにならいなど言い放ち嫌悪を剝き出しにする者も少なからずいるが――。
ドイツに民主主義が根付いていないと直感するヒトラー。それは1930年代と同じだ。ヒトラーは、犬種の違う犬の交配を例えに人種論を語る。それこそ1930年代と同じだ。現代ドイツ人とヒトラーの会話からヒトラーが1930年代と同じく人間の裡にある人種差別の匂いを嗅ぎ、彼ら彼女らにキーワードを与えナチズムの種を撒いているようにも見える。
ヒトラーは、時代錯誤の制服と勲章(第一次世界大戦で授与された戦傷章、一級鉄十字章)を身に纏い、オペラ歌手パウル・デフリーントから指導を受けた独特の発声とジェスチャーと沈黙を使いTVやSNSで「ヒトラーのコスプレ芸人」的な立ち位置の人気を得るが――やがて人々は、「ヒトラーのコスプレ芸人」の主張、価値観、人間力などに魅了されていく――そこには、1930年代のアドルフ・ヒトラー人気に通じるものがあるようだ。
戦い続けろという神の真意で2014年に蘇ったと考えるヒトラーは、人類の偉大な発明コンピューターとインターネットを使い新たな帝国を築き始める。当初はヒトラーの時代を知らない若い世代(SNSを頻繁に利用するZ世代など)に消費される新たな、一風変わったYouTubeスターのような扱いを受けるが、やがて、民間TV会社「my tv」の女性副局長フランツィスカ・クレマイヤー達もヒトラーのカリスマ性と話題性に魅了される。
人気の政治的コメディ番組『クラス・アルター』の生放送に出演したヒトラーは、得意の沈黙の力と効果を利用し――聴衆の意識を支配した瞬間――演説を始める。
TVから垂れ流される低俗な番組への批判、子供の貧困、老人の貧困、失業、過去最低の出生率、こんな国では誰も子どもなど生まない等々。
私はテレビと戦う。我々が奈落を知り、克服すようになるまで。20時45分より、反撃放送を行う。
映画『帰ってきたヒトラー』字幕版
ヒトラーは一夜にしてドイツ全土のスターになる。ヒトラーが主演したTV番組の視聴率は非常に高い。国民はヒトラーに魅了され「好き/嫌い」に関わらず注目される存在となり、映画撮影の企画が進み――だが、ヒトラーはヒトラーだった。彼は物真似芸人ではなかった。反民主主義と人種差別主義思想のヒトラーだった。
本作が示すのは、「ヒトラーを笑うこと」が果たしてどこまで可能かという問いである。観客は、滑稽な存在として登場したはずの彼が、人々の共感を得て支持されていく過程を目撃する。これは、かつてナチズムが台頭した1930年代と驚くほど類似している。
ヒトラーの笑えない魅力:『帰ってきたヒトラー』が突きつけるもの
ヒトラーは強者を賛美する人間だ。ナチズムはニーチェの「超人思想」を都合よく誤読しながら、強者を賛美する。
犬の死体に怯えるザヴァツキを腰抜け、堕落者と叱咤し、独身のザヴァツキに「攻撃あるのみだ!」と助言もする。(ナチは鋼鉄の意思という言葉を好む)。
勇気に欠け、軟弱で優柔不断なザヴァツキにヒトラーは年長の友人のように兄のように父親のように振る舞う。時に悪戯もする。映画『帰ってきたヒトラー』は、人間臭いヒトラーが「意図的」に描かれている。そう、1930年代のヒトラーは、国民の理解者、救世主、アイドル、国民を守る父親、国民に慕われる兄貴、女性から愛される存在でもあったのだ。
第二次大戦後に創られた多くの映画、小説のなかのヒトラーは悪魔的な人間だ。我々はホロコーストや戦禍により焼け野原となった戦後の欧州や戦争で死んだ多くのドイツ人、近隣諸国の国民を知っている。人類史上を代表する「悪」、「悪魔的な存在」だけのヒトラーならば、1930年代のドイツ国民は彼を支持しなかっただろう。
採食主義者で酒、煙草を嗜まず、贅沢を嫌い、軍服やナチ制服に第一次大戦で授与された勲章だけを付け、禁欲的な独身(事実婚のエヴァ・アンナ・パウラ・ブラウンの存在は隠されていた。なお、ヒトラーとエヴァは1945年4月29日正式に結婚。4月30日、2人は自殺する)を演じたヒトラー。
ヒトラー専属の写真家ハインリヒ・ホフマンが撮影した当時のヒトラーの写真やプロパガンダ用に創られた映像には、英雄的カリスマ性が強く演出されたヒトラーが残っている。
だが、エヴァ・ブラウンが撮影したといわれるベルクホーフ山荘(オーバーザルツベルク)で愛犬と戯れるヒトラーの映像が残っている。子どもたちや国民に笑顔を見せるヒトラーの映像が残っている。
「悪」が悪魔の姿をして現れるのなら「悪」を遠ざけることは簡単だ。サイコパスの連続殺人鬼が魅力的な人間であるのと同じように世界中に「不幸」をばら撒く人間も魅力的な一面を存分に見せる。ドイツ民族のために全身全霊を捧げるドイツ民族の英雄のようにも映る。
映画『帰ってきたヒトラー』のなかのヒトラーは、人間的な魅力を持つ、頑固だがカリスマ性を持つリーダー(総統)のようでもある。
ヒトラーの過激な発言は、SNSやYouTubeで若い世代から人気を得る。ヒトラーの過激な発言に戸惑いながらも彼を不満の代弁者、難民排斥など現代タブーの代弁者と見なす言説が現れる。
そう、ヒトラーを無条件に笑えない現状、ヒトラーの言説を完全否定することが出来ないドイツ国民の不満が「ヒトラー」(記号化のヒトラー)を通じて可視化され始める。 我々が「ヒトラー」を笑い続けるために必要なことはなにか?映画『帰ってきたヒトラー』は、元貴族、元軍人などによるクーデター計画の発覚により逮捕者が出た2022年12月現在も問われ続けている。
2022年12月のドイツクーデター計画(未遂)事件の衝撃
現地時間2022年12月7日、ドイツ連邦検察がクーデター計画の容疑で71歳の元貴族、極右政党関係者、Qアノン信奉者、元軍人など計21人を逮捕したとの報道がなされた(参考:ドイツ、クーデター計画容疑で25人逮捕 議事堂襲撃を画策と BBC NEWS JAPAN 2022年12月7日配信)。
上記の報道から思い出されるのは、アドルフ・ヒトラーの「ミュンヘン一揆」とヒトラーが現代(2010年代のドイツ)に蘇り騒動を起こすコメディ映画『帰ってきたヒトラー』(2016年日本公開)だ。
ディープステート(闇の政府)絡みの陰謀論を信じる者たちとユダヤ陰謀論を信じたアドルフ・ヒトラー(ヒトラーなど当時のドイツ人は、帝政ロシアの秘密警察が書いたといわれる歴史的な偽書『シオン賢者の議定書』を信じていた)。アドルフ・ヒトラーの時代から約100年の歳月が流れたが人は「信じたいもの」や「信じるもの」を「信じ」世界を眺めてしまうのだろう。
先ずはヒトラー内閣成立からヒトラー(ナチ党)独裁までの簡単な流れを記そう。
アドルフ・ヒトラー(1889年4月20日-1945年4月30日)率いるナチ党は、1932年7月の選挙で第一党となる。1933年1月30日には、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領(ユンカー/ドイツ東部の地主・貴族階級出身の元陸軍元帥)がヒトラーを首相に任命、ヒトラー内閣が誕生する。
同年2月27日、「国会議事堂放火事件」が発生し、左派政党(ドイツ共産、ドイツ社会民主党)党員が逮捕・弾圧される。
1933年3月23、悪名高い「全権委任法」(ヒトラー政府はヴァイマル憲法を無視した立法権を得る)が公布され、ヴァイマル共和政/ワイマール共和制(ドイツ共和国)の民主主義は解体される。
戦後のドイツは、上記の1920年代後半から30年代、そして、1945年5月まで続いたナチ政権を教訓とし、「戦う民主主義」を掲げたが――ヒトラーとナチ一派は、選挙による政権奪取の前、「ミュンヘン一揆(1923年11月8日-9日)」と呼ばれるクーデター未遂事件(ナチ突撃隊などによる武装蜂起)を起こした(1924年5月の裁判によりヒトラーは5年の禁固刑を受けるが同年12月に仮釈放される)――民主主義は非常に脆い制度だともいえる。
かつて『シオン賢者の議定書』(帝政ロシアの秘密警察が作成したとされる偽書)を真実と信じたアドルフ・ヒトラー。当時のドイツ国民がそうであったように、現代においても人は「信じたいもの」を選び、現実をそのフィルター越しに見る傾向がある。ヒトラーの時代から100年近くが経過しても、この傾向は変わっていないように見える。
コメディとしての価値:『帰ってきたヒトラー』の演出力
本作は、コメディ映画としても高い完成度を誇っている。ヒトラーを風刺的に描いた作品としては、チャーリー・チャップリンによる『独裁者』(1940年)が著名であるが、その後の多くの映像作品では、ヒトラーは一貫して「悪の象徴」としてシリアスに描かれてきた。
しかし、「悪」を笑うことは、時にその本質的恐怖をより鮮烈に浮かび上がらせる。『帰ってきたヒトラー』もまた、そうした映画である。
作中には、『ヒトラー〜最期の12日間』(2004年)を意識したパロディ演出が挿入されている。テレビ局の視聴率低迷に苛立つ副局長クリストフ・ゼンゼンブリンクが、怒号を飛ばす場面は、まさに敗戦間際のヒトラーを模した演出である。このような手法により、現代の「小物」が、過去の「巨悪」と重ね合わされる構造が浮かび上がる。
本作が描くヒトラー像は、観客にとって「笑ってはいけない笑い」である。笑いながらも、その笑いが内包する不穏さと危うさから逃れることはできない。『帰ってきたヒトラー』の魅力とは、まさにその「逃げ場のなさ」にある。
言説は消費される:『帰ってきたヒトラー』が映し出す現代の言論空間
『帰ってきたヒトラー』が描くもう一つの核心は、「言説が理念や思想としてではなく、コンテンツとして消費される時代」において、ヒトラーの言葉がどのように作用しうるかという問題である。
本作のヒトラーは、かつての演説と同様の口調で語り、人種や国家、移民問題についての強硬な言説を再び公言する。だが、それが現代社会において通用するのは、もはやその言葉の中身ではなく、「刺激的で拡散されやすい語り口」という“メディア適性”によるものに他ならない。
現代のSNS、YouTube、テレビメディアは、内容の真偽や倫理性よりも、反応と再生数、バズと話題性を優先する。ヒトラーの言説は、その過激さゆえに「バズる言葉」として流通し、視聴率や再生回数といった数字の文脈で評価されていく。
ここにおいて、言説は「思想」ではなく「素材」となる。視聴者はヒトラーの発言に驚き、笑い、時に共感すら示すが、その反応は一過性のものであり、深い思索や批判的吟味には至らないまま、次なるコンテンツへと移っていく。つまり、言説は「消費」されているのである。
カリスマは再現可能か?:アルゴリズムとナチズムの親和性
さらに重要なのは、現代社会における「注目経済(attention economy)」とナチズム的言説の構造的親和性である。ヒトラーの言葉は、端的で単純明快、情緒的で敵を明示し、自己と他者を明確に区分する。この「感情を煽る語り」は、SNSのアルゴリズムが最も好む形式である。
結果として、ヒトラー的言説は、YouTubeやX(旧Twitter)といったプラットフォーム上で拡散されやすく、現代の「バズ」と非常に親和性が高い。かつてナチスがポスター、映画、ラジオといった当時のメディアを最大限に利用したように、現代のヒトラーもまたアルゴリズムの中で“カリスマ性”を再現しうるのである。
ヒトラーがかつて国民の間に築いた「共感の共同体」は、いまや「視聴回数の共同体」へと形を変え、民主主義の根幹を脅かす可能性を内包している。
なぜ人はヒトラーを“クリック”するのか
現代の人々は、ヒトラーの演説や過激な発言を“視聴”し、“共有”する。しかし、その多くは歴史的・倫理的な問いを伴わない“態度なき視聴”である。これは、単なる娯楽や話題として言説を消費することの危険性を示している。
人々はヒトラーを「笑える存在」として受容することで、自らの内面にある憎悪や排除の感情を正当化する装置として機能させてしまう。それはまさに、彼の言説が「過去のものではなく、現在の我々の中にも根を張っている」ことを意味する。
言説の「文脈なき再生産」と倫理の終焉
ヒトラーが語る言葉は、その歴史的背景や政治的文脈を切り離された状態で再生産されていく。TikTokで切り抜かれ、字幕が付けられ、パロディとして使い回されるうちに、その言葉は「過去の悲劇を想起させる記号」ではなく、「刺激的で映える言葉」としての価値を獲得していく。
ここにおいて、倫理の抑制力は剥がれ落ち、再生産される言説が、歴史の文脈を失った「記号的暴力」として流通することになる。ヒトラーはその象徴として極めて強力であり、『帰ってきたヒトラー』はその構造を可視化する装置でもある。
ヒトラーが「商品」になった時代に生きるということ
本作が問いかけるのは、ヒトラーという人物の再評価ではない。むしろ、我々がどのように「ヒトラーという言説」を扱い、反応し、再構成しているかという現代社会の姿そのものである。
ヒトラーは今や、アイコンであり、商品であり、アルゴリズムに最適化された「コンテンツ」となった。そしてその過程で、我々は彼の言葉が孕む本質的な暴力性や排他性を見失いかけている。
『帰ってきたヒトラー』は、こうした「言説の消費社会」において、ヒトラーを再び“招き入れる”我々自身の姿を映し出している。だからこそ、この映画は笑えない。いや、笑えるからこそ、恐ろしいのである。
まとめ
本作は、単なる風刺映画ではない。表層的にはコメディの体裁をとりながらも、その核心は極めて冷徹である。「もしヒトラーが現代に復活したら」という仮定のもとで、現代人がいかにして過去と同じ過ちを繰り返し得るかを、静かに、しかし鋭く提示する。
演説、ジェスチャー、沈黙の使い方、そしてメディアの利用――それらを駆使して再び大衆を惹きつけるヒトラーの姿は、過去の歴史が単なる過去ではなく、いまもなお潜在的に社会の中に息づいていることを如実に示している。
『帰ってきたヒトラー』は、歴史に対する忘却がもたらす危険を、ユーモアを装いながらも深く抉る作品である。現代に生きる我々は、ヒトラーを笑えるだろうか――あるいは、笑っているうちにまた彼を迎えてしまうのだろうか。
あなたにオススメ ナチスを描いた映画考察 ヒトラーが登場する漫画考察
実在のナチ関係者をモデルにした登場人物を描いた映画
海外社会派映画